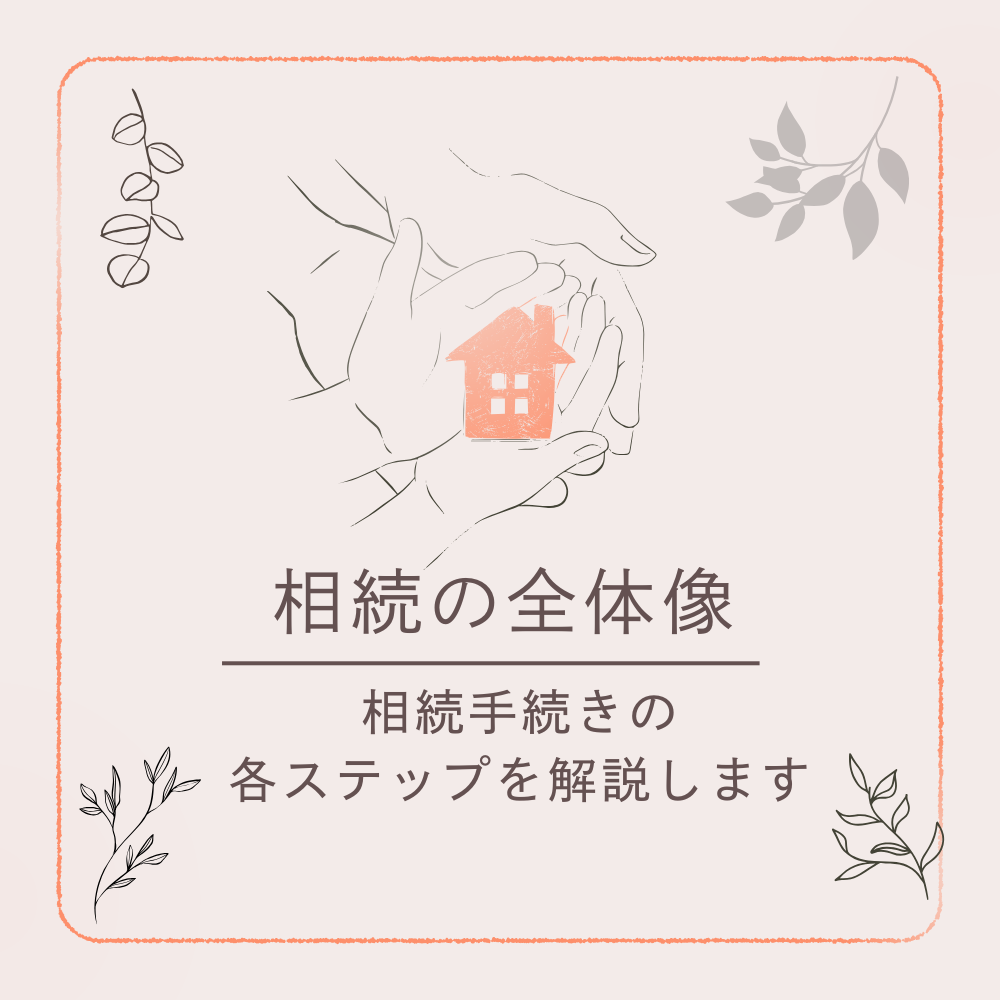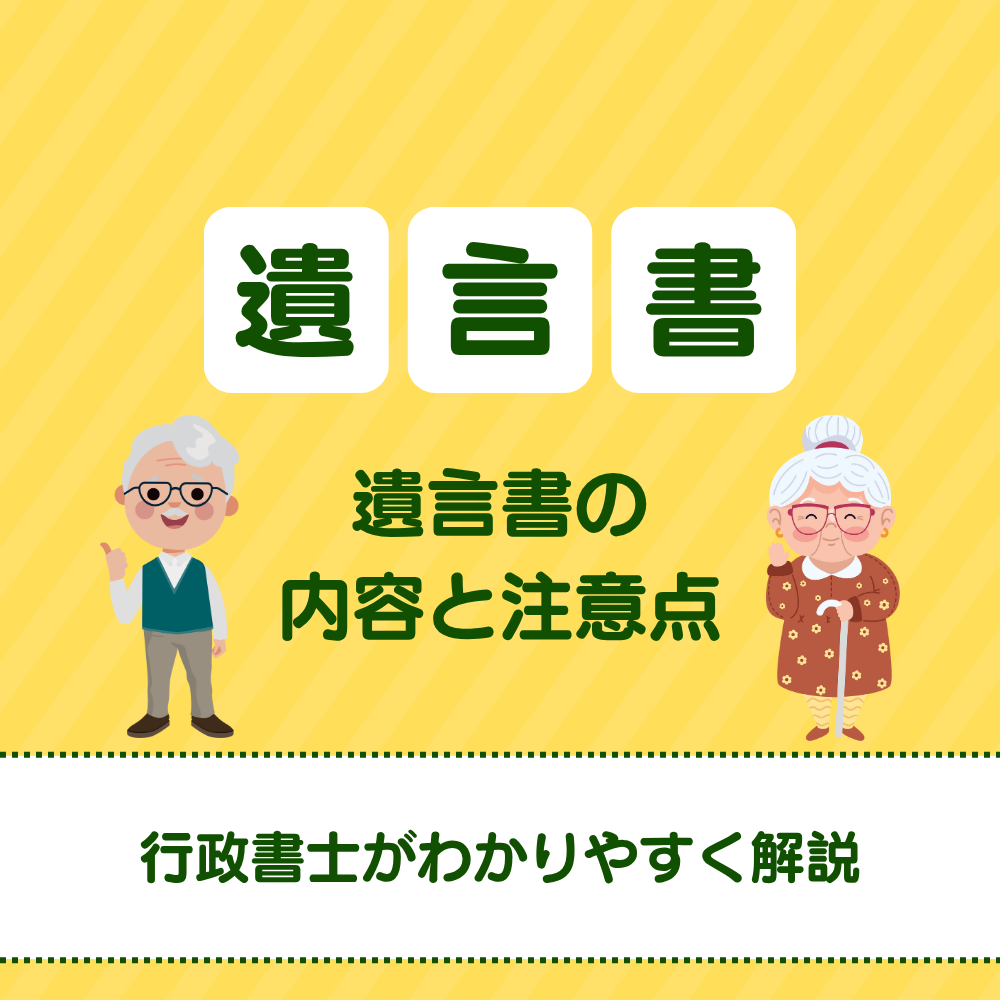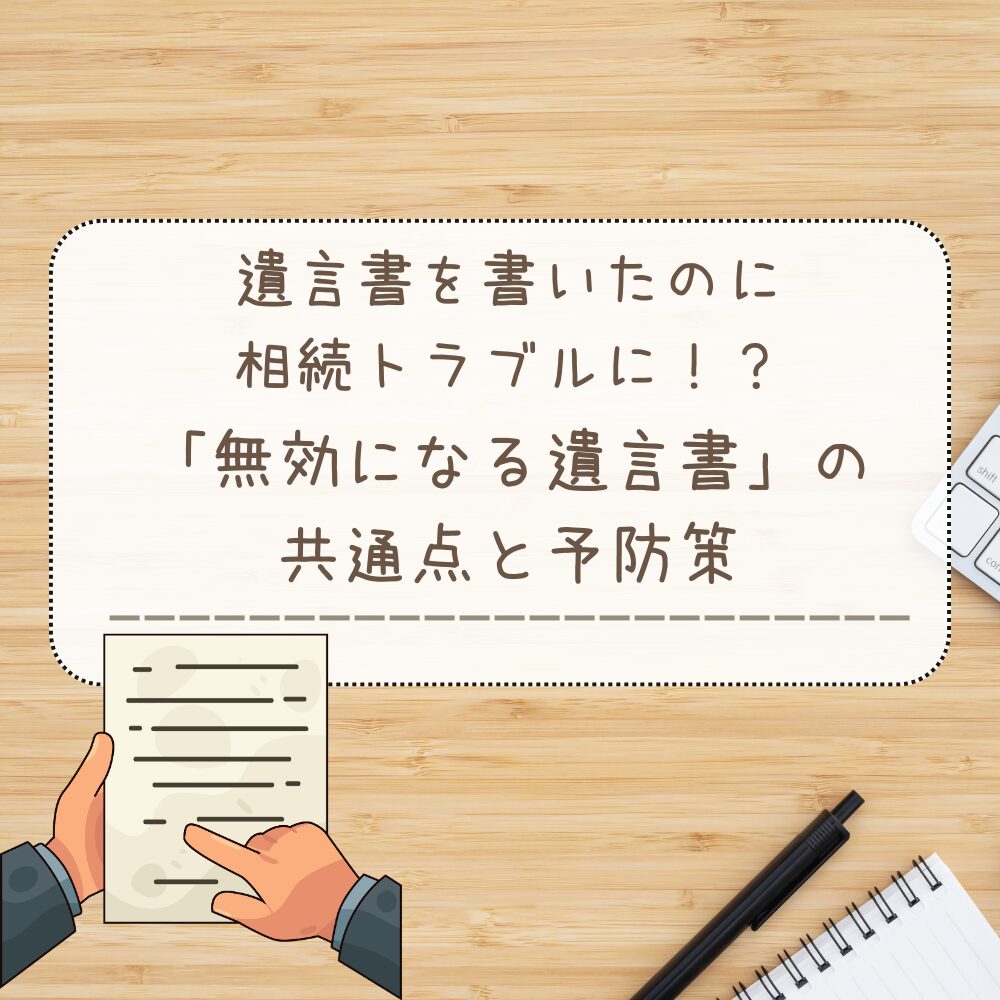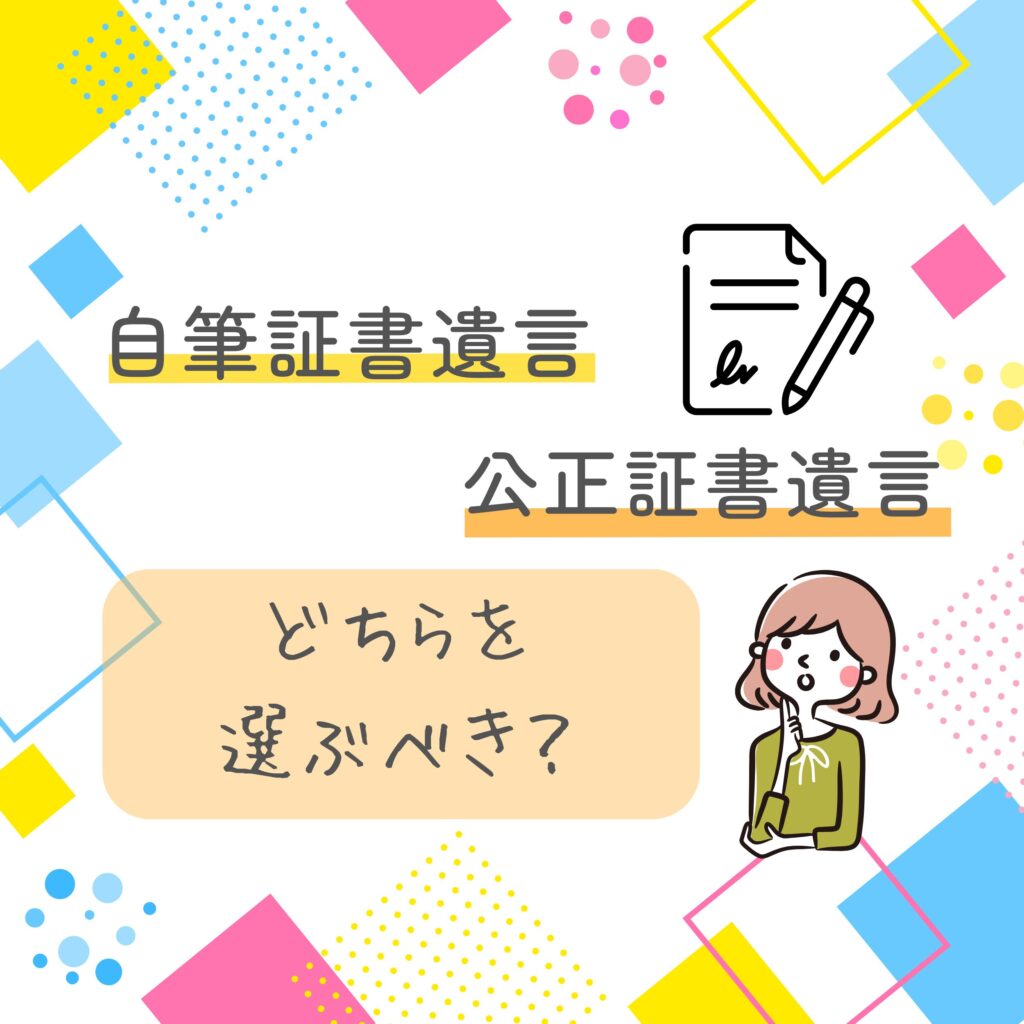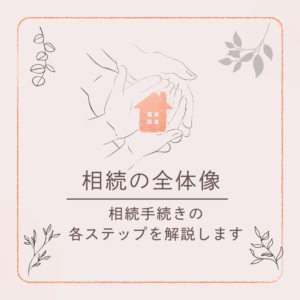相続で出てくるワードの解説と相続の流れ
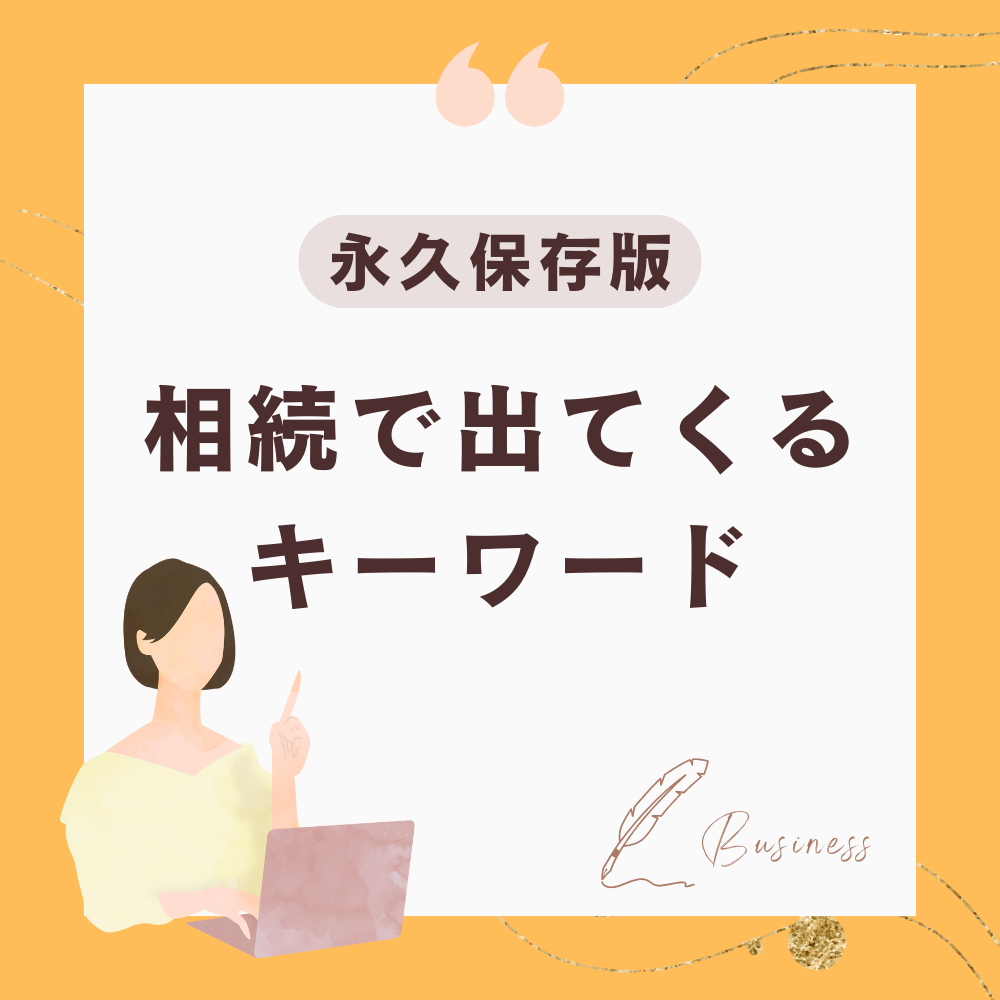
目次
はじめに
この回では相続でよく出てくる用語をピックアップして解説していきます。
被相続人
亡くなった人
相続人
被相続人の財産を受け取る人(配偶者・子など)
遺産分割協議書
相続人全員で相続財産の分け方を話し合った内容を記した書類
遺言書
被相続人が遺した意思を記した文書(自筆、公正証書など)
自筆証書遺言
遺言者が全文・日付・氏名をすべて自筆で書いて作成する遺言書
遺言執行者
遺言の内容を実現する人(遺言で指定される)
公正証書遺言
公証人が作成する正式な遺言書で、遺言者が口頭で内容を伝え、それを公証人が文書にまとめて作成・署名・保管します。
第一順位
被相続人の「子(直系卑属)」を指します。つまり、相続が発生した際に最優先で相続権を持つ人たちです。
第二順位
被相続人の父母、祖父母など。被相続人に子(第一順位の相続人)がいない場合に相続権を持つ人たちのこと。
第三順位
被相続人に「子(第1順位)」も「父母などの直系尊属(第2順位)」もいない場合に相続権が発生する人たちです。主に兄弟姉妹が該当します。
直系卑属
自分より下の世代にあたる血族のことを意味します。相続においては、被相続人の「子・孫・ひ孫」などがこれに該当します。
直系尊属
自分より上の世代にあたる血族のことを指します。相続においては、父母・祖父母・曽祖父母などが該当します。
戸籍謄本
戸籍に記載されているすべての情報をコピー(謄写)した公的な証明書類です。相続や婚姻、出生・死亡の証明、公的手続きなどで広く使われます。
単純承認
被相続人の財産(プラスもマイナスも)すべてをそのまま相続すること
相続財産
被相続人が死亡時に所有していたすべての財産や権利・義務のこと
相続放棄
被相続人の財産(プラスもマイナスも)を一切相続しないことを選択する法的手続き
みなし相続財産
民法上の相続財産には含まれないが、相続税の課税対象とされる財産のこと
✅ みなし相続財産の代表例
種類 説明 備考 死亡保険金 被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人の場合 非課税限度あり(500万円 × 法定相続人の数) 死亡退職金 被相続人の死亡により勤務先から支給される退職金 非課税限度あり(同上) 定期金に関する権利 年金受給権など、死亡により開始する継続収入 稀なケースですが課税対象 被相続人が負担していた保険料の一時金等 被相続人が保険料を払っていたが、他人が受け取るもの 実質的には被相続人の財産とみなされる ✅ 民法と税法での違い
分類 民法上 税法上(相続税) 死亡保険金 相続財産ではない(直接受取人に帰属) 相続税が課税される(みなし相続財産) 死亡退職金 相続財産ではない 同上 遺族年金 相続財産ではない 非課税扱い(相続税もかからない)
相続の流れ
次に相続の流れを簡単にまとめました。
基本的な流れは以下の通りです。
✅ 相続の全体的な流れ
時期目安 手続き内容 概要 ❶【死亡直後】 死亡届の提出(7日以内) 市区町村に提出。火葬許可証の発行も ❷【~1か月以内】 葬儀・埋葬、関係機関への連絡 勤務先、保険会社、年金事務所など ❸【1か月以内】 相続人の調査・確定 戸籍謄本を収集(出生から死亡まで) ❹【1~2か月】 相続財産の調査 不動産、預金、株式、借金などを調査 ❺【3か月以内】 相続方法の選択 単純承認/限定承認/相続放棄(家庭裁判所へ申述) ❻【~4か月以内】 準確定申告(被相続人の所得税) 死亡年の所得税を相続人が申告・納税 ❼【~6か月以内】 遺言書の有無確認・検認 自筆証書遺言は家庭裁判所で「検認」必須 ❽【~6か月~1年】 遺産分割協議・協議書作成 相続人全員で財産の分け方を合意し文書化 ❾【10か月以内】 相続税申告・納付 基礎控除を超える場合は税務署へ申告・納税 ❿【適宜】 各種名義変更・解約 不動産登記、預金口座の名義変更、株式移管など
✅ 専門家の関与ポイント(行政書士・司法書士・税理士)
専門家 主な業務 行政書士 戸籍調査/相続関係説明図/遺産分割協議書作成/遺言書作成支援 司法書士 不動産の相続登記(名義変更) 税理士 相続税の申告・納税手続き/税務調査対応
おわりに
今回は当事務所の記事で相続を主に取り上げていますが、
意味を忘れてしまったなどがあったときにこの記事で確認できるようにしました。
お役に立てていただければ幸いです。
※その他関連記事は下記よりご覧ください