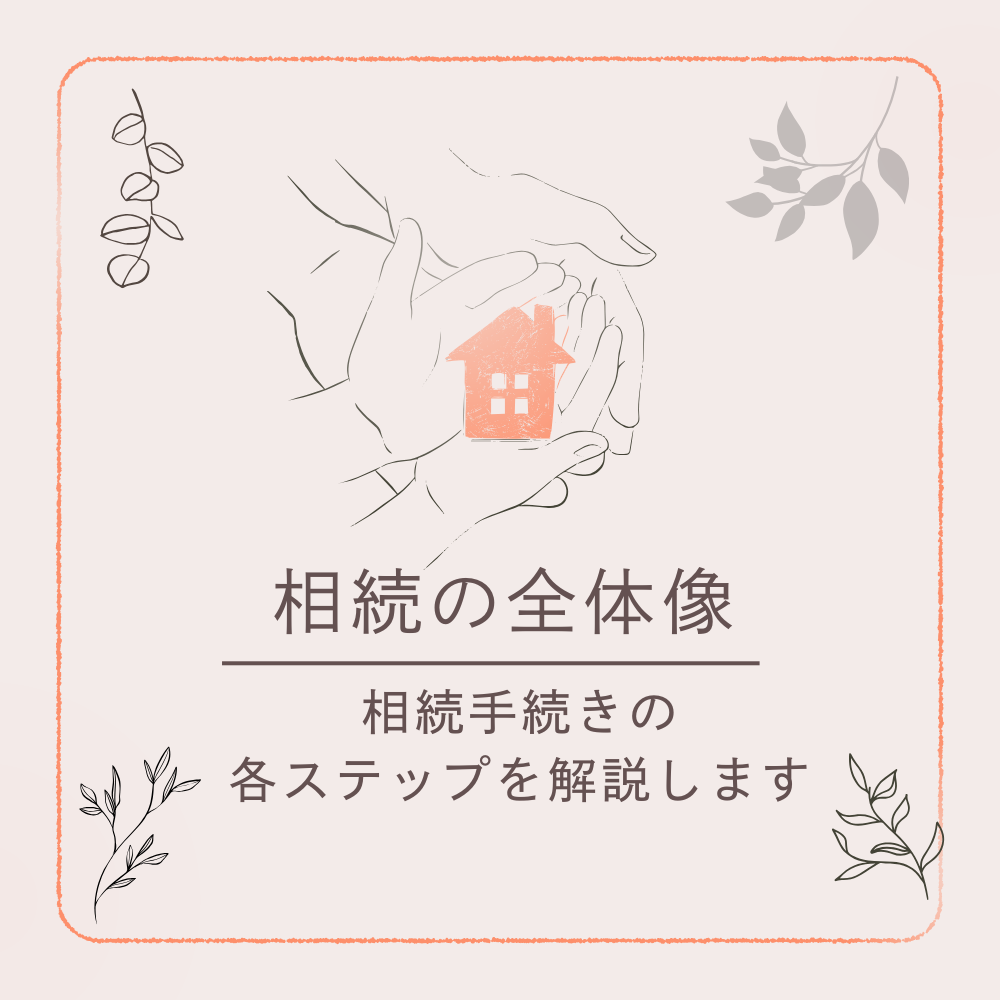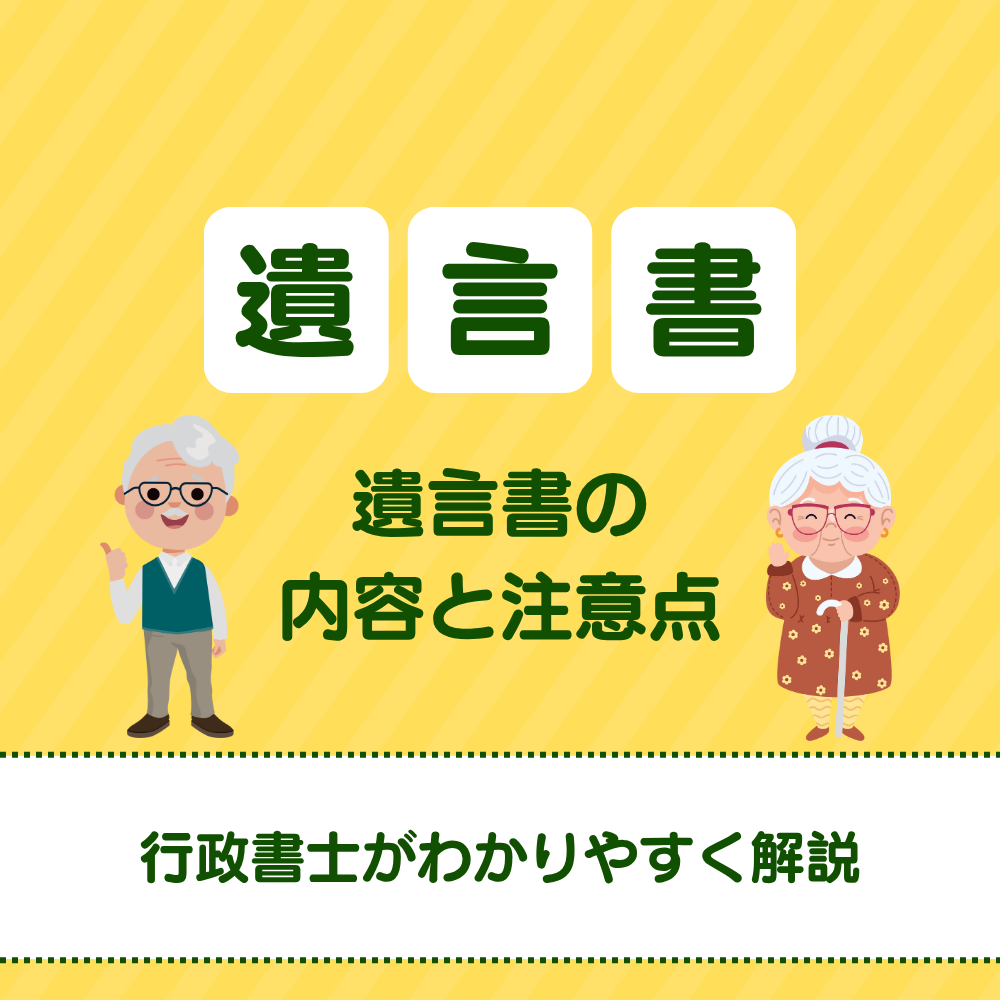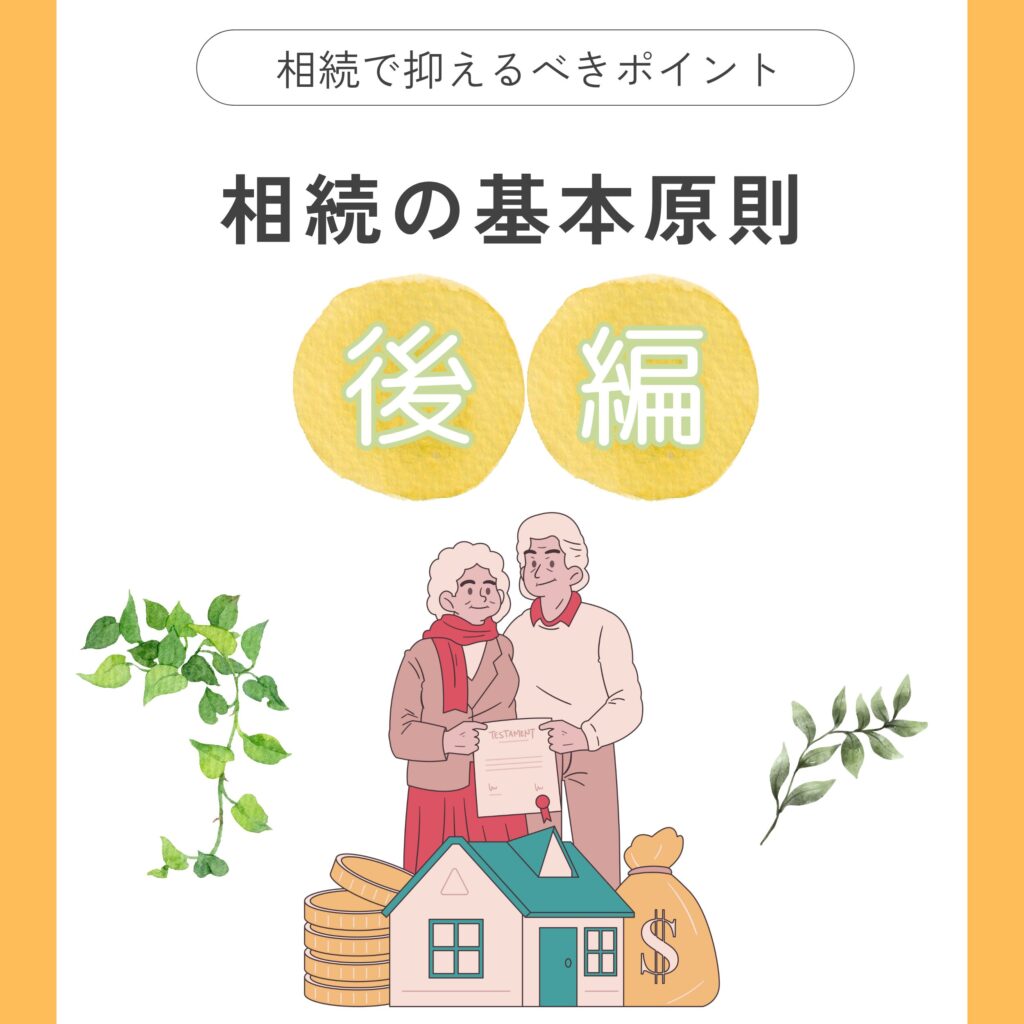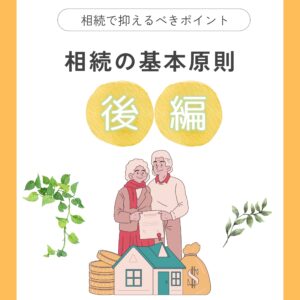これだけ抑える!相続の基本原則~前編

目次
はじめに:メインは民法!
相続の法律には相続税法などがありますが、主なところは民法典に記載があります。
民法の第5編は相続であり、第882条から第1050条まで条文があります。
とにかく長いですが、債権(第399条から第724条まで)と比べるとそのまま条文通りに読み進められるため、
比較的条文でも読みやすい内容になっています。
....とはいえ法律なのでやっぱりわかりにくい。
なので今回は相続の基本原則について前編と後編に分けてお伝えしたいと思います。
本篇では主に「相続人の範囲」についての解説になります。
相続の基本原則
相続を学ぶ際にまず抑えるべき条文は以下の条文です。
民法 第882条(相続の一般的効力)
相続は、被相続人の死亡によって開始する。
民法 第886条(相続に関する胎児の)
第1項
胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。
第2項
ただし、死体で生まれたときは、この限りでない。
民法 第887条(子及びその代襲者の相続権)
第1項
被相続人の子は、相続人となる。
第2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した場合、または相続権を失った場合には、その者の直系卑属がこれを代襲して相続人となる。
第3項
第2項の規定による代襲者が、さらに相続の開始以前に死亡した場合、または相続権を失った場合には、その者の直系卑属がこれを代襲して相続人となる。
民法 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第1項
一 被相続人に子がないときは、直系尊属が相続人となる。ただし、祖父母よりも父母が優先する。
二 被相続人に子も直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人となる。
三 前二項の場合において、相続人が被相続人の養子であったときは、その養子の直系卑属は、これを相続人とする。
民法 第890条(配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
ここを抑える!民法 第882条(相続の一般的効力)
内容は「相続は、被相続人の死亡によって開始する」です。
「被相続人」とは亡くなった人を指します。
被相続人のワードはめちゃくちゃ条文に出てきて大事ですので、本記事ではフリガナふります!
次に「相続」はその被相続人(亡くなった人)が死亡した時点で、自動的に開始されます。
....自動的にです。止めようとしてもできません。
ここを抑える!民法 第886条(相続に関する胎児の権利能力)
まず第1項、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」
これは相続が発生したとき、被相続人(亡くなった人)の子として胎児が存在していた場合、
その胎児は「生まれている」とみなされるため相続人となります。
しかし第2項の「死体で生まれたときは、この限りでない」というものがあり。
胎児が死産だった場合は、相続権は認められません。つまり相続権はなかったものとみなされます。
ここを抑える!民法 第887条(子及びその代襲者の相続権)
まず第1項です。内容は「被相続人の子は、相続人となる」です。
子は法定相続人であり、配偶者と子は第一順位の相続人です。
子は嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)、非嫡出子(婚姻外の子)、養子も含まれます。
後編で法定相続分の話をしますが、
法定相続分では、まず最初に相続人となるのが配偶者、
子がいれば配偶者と子、
子がいなければ配偶者だけ ※親がいれば配偶者と親ですが後編で解説します
配偶者も子もいなければ、両親(父親・母親が優先というものはありません)
両親も先に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。
ちなみに兄弟姉妹、法律用語では「けいていしまい」と呼びます。
すごくどうでもいい情報すみません...
次に第2項、内容は「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡した場合、または相続権を失った場合には、その者の直系卑属がこれを代襲して相続人となる」です。
上記の条文では聞きなれないワードが出てくるので確認していきます。
直系卑属とは子のことです。
条文に「子」と直系卑属という同じような意味で言葉の違うものがあるので、
全部「子」に統一してくれよ!!って誰もが思うかと思います...。
細かい意味の違いはありますので、検索はGoogle先生をご利用ください。
ちなみに親のことは直系尊属といいます。
解説に戻りますが、
この条文は被相続人(亡くなった人)が死亡する前に、すでに第一順位である「子」が亡くなっていたら相続はどうなるのか?という話です。
この回答は「代襲する」です。
これは代襲相続といい、子が相続開始前に死亡した場合などには、その子(=被相続人の孫)が相続人になります。
つまり子の子(被相続からみたら孫)が第一順位として相続します
親にはいきません。
ちなみに子がいなくて両親しか相続人がいない場合においても、親を代襲して祖父母に代襲することはありません。
あくまで子の場合の話です。
次に第3項、
内容は「第2項の規定による代襲者が、さらに相続の開始以前に死亡した場合、または相続権を失った場合には、その者の直系卑属がこれを代襲して相続人となる」です。
代襲相続するはずの孫も亡くなっていたら相続はどうなるの?という話です。
これは「再代襲相続」といい、
代襲者(孫)がさらに死亡していた場合は、その子(=ひ孫)が相続することができます。
こうやってどんどん続きます。
無制限に続きます。
ここを抑える!民法 第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
本篇最後の内容になります。
親と兄弟姉妹の話が出てきます。
繰り返しになりますが直系尊属は「親」のことです。
第1項1号の条文の内容は「被相続人に子がないときは、直系尊属が相続人となる。ただし、祖父母よりも父母が優先する。」です。
この条文だけを見ると、亡くなった時に子がいない場合は直系尊属(親)が相続します!とあり、
あれ?配偶者は?...となりますが、
民法890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」とあるので、
配偶者がいれば、配偶者と直系尊属(親)が相続人となります。
次に第1項2号の内容ですが、内容は「被相続人に子も直系尊属もいないときは、兄弟姉妹が相続人となる」です。
条文の内容は兄弟姉妹について定めており、
子も親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となり、
配偶者がいれば配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
そして兄弟姉妹にも「代襲相続」があります。
つまり代襲すれば甥・姪が相続人となります。
しかし注意したいのは、
代襲相続は甥・姪までであり、再代襲の制度がありません。
これは無制限ではなく、相続の複雑化を避けるために甥・姪までと定めています。
3項は養子がいる場合の話でより複雑な話になりますので割愛します。
以上が前編となります。
おわりに
今回の内容を抑えると後編の話も入りやすくなりますので、
読み返して確認いただけますと幸いです。
ご質問等ありましたらご連絡ください。
※その他関連記事