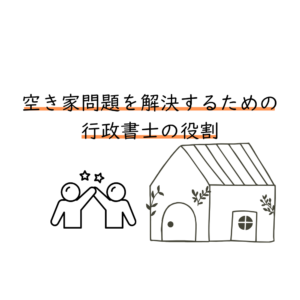行政書士が解説!営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)申請の流れと注意点

目次
はじめに:注目が集まる「営農型太陽光発電」
近年、「農業の維持」と「再生可能エネルギーの普及」を両立させる取り組みとして、
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)が全国的に注目されています。
営農型太陽光とは、
農地の上に支柱を立てて太陽光パネルを設置し、その下で作物を栽培する仕組みです。
つまり、太陽のエネルギーを「農業」と「発電」でシェア(共有)することから
「ソーラーシェアリング」と呼ばれています。
一方で、この事業を始めるには複数の法令や手続きが関わるため、
行政書士による専門的なサポートが不可欠です。
本記事では、行政書士として知っておくべき「営農型太陽光発電の申請の流れ」や
「許可のポイント」「注意点」をわかりやすく解説します。
営農型太陽光発電とは?その仕組みと目的
営農型太陽光発電の目的は、
農地の有効活用と農業所得の向上にあります。
従来、太陽光発電を設置するには農地を「非農地化(転用)」する必要がありましたが、
営農型の場合は農業を継続しながら発電が可能です。
営農型太陽光の特徴は次の3つです。
1.農業と発電の両立が可能
パネルの下で農作物を栽培できるため、農業をやめずに収益を増やせます。2.農地の有効活用
耕作放棄地の再利用や、収益性の低い土地の活性化に寄与します。3.再エネ普及への貢献
地域の脱炭素化や地球温暖化対策にも貢献できる、社会的意義の高い仕組みです。
営農型太陽光発電に必要な主な法的手続き
営農型太陽光発電を導入するには、複数の法律に基づく申請や届出が必要です。
行政書士が関わる主な手続きは次のとおりです。
(1)農地法に基づく「一時転用許可」
営農型太陽光では、農地に支柱を立てるため、
農地法第4条または第5条に基づく「一時転用許可」が必要になります。
通常の太陽光発電のような「恒久転用」ではなく、
最大10年間の期間限定の転用許可となるのが特徴です。
・農地法第4条許可:自己所有の農地を自ら転用する場合
・農地法第5条許可:他人の農地を転用目的で取得・賃借する場合
この許可申請では、「営農を継続する具体的な計画(営農計画書)」の提出が必須です。
(2)営農計画書の作成
営農型太陽光の許可審査では、
「営農が実際に継続できるかどうか」が最重要視されます。
そのため、行政書士は以下のような内容を具体的にまとめた営農計画書を作成します。
・栽培作物の種類・作付面積
・作業体系(播種・収穫時期、使用機械など)
・光量・日照の確保方法
・農業収入と発電収入の見通し
・営農継続のための体制(人員・機材など)
特に「日射量シミュレーション」や「パネル配置図」など、
技術的データの添付が求められることもあります。
営農計画書が不十分だと、
農業委員会の審査で却下されるケースもあるため注意が必要です。
(3)再生可能エネルギーに関する手続き(FIT/FIP)
太陽光発電による売電を行う場合は、
経済産業省への「事業計画認定(FITまたはFIP制度)」が必要です。
これは、発電した電力を固定価格で買い取ってもらう制度であり、
認定がなければ電力会社と接続契約を結ぶことができません。
申請者には大まかに以下の資料を整えること必要があります。
・発電設備の概要・配置図
・農地転用許可証の写し
・事業計画書(収支・スケジュール)
・地権者との賃貸借契約書、同意書
この手続きは農地法申請と並行して進めるケースが多く、
申請スケジュールの管理が重要になります。
(4)電力会社との系統連系申込み
電した電力を送電網に接続するには、
電力会社との「系統連系申込み」が必要です。
設備容量や設置場所によっては接続可能容量に制限があるため、
早期の確認が求められます。
行政書士が直接申請を行うことは少ないものの、
関連書類の整備や地権者の同意書作成などをサポートします。
4. 行政書士が関わる主な書類とサポート内容
営農型太陽光発電の申請では、
以下のように行政書士が関与できる業務範囲があります。
書類名 内容 行政書士の役割
農地法第4条・第5条許可申請書 農地転用の根拠書類 申請書作成・代理提出
営農計画書 営農継続の証明資料 企画・記載支援
賃貸借契約書・同意書 地権者・事業者間の権利関係整理 契約書文案の作成
位置図・配置図 パネルや農地区画の位置関係 図面作成補助・添付
事業計画書 FIT認定・金融機関提出用 収支計画・資金計画の整備
行政書士は、単なる「書類作成代行者」ではなく、
事業全体を設計するコーディネーターとしての役割を担います。
5. 営農型太陽光発電の許可基準と審査のポイント
営農型太陽光発電の許可審査では、以下の3つの観点が重視されます。
1.営農の継続性
実際に農業が行われるか、営農計画が現実的かを審査。過去の農業実績や耕作者の体制も評価対象です。
- 太陽光パネル下で作物が十分に育つか
- 日射量・パネル配置・高さが適切か
- 農業を継続できる人員・機械・ノウハウがあるか
- 営農計画書の収支・作業計画が現実的か
農業委員会は、過去の営農実績や作付計画の実現性を確認します。
2.太陽光設備の安全性・撤去計画
支柱の基礎が浅く、農地に不可逆的な損傷を与えない構造であるか、撤去時の計画が明示されているか。・支柱の基礎が浅く、農地を恒久的に破壊しない構造であること
・パネルの取り外し・撤去が容易で、原状回復可能であること
・落下・感電・風害などの安全対策が講じられていること
3.土地利用の妥当性
最後に審査されるのが、土地利用全体の妥当性です。
農地法の許可が下りても、他法令との整合が取れていないと事業は進められません。・土地が農振地区内か(除外不要型営農かどうか)
・都市計画法の用途地域(市街化調整区域など)
・森林法・景観条例・自然公園法などの制限
・農業用水・道路・隣地への影響
・関係者の同意(地権者・隣接地所有者など)
これらの基準を満たすためには、
現地調査・地目確認・関係機関との事前協議を丁寧に行うことが重要です。
6. よくあるトラブル・注意点
営農型太陽光発電は、制度的にまだ新しい分野のため、
次のようなトラブルも見られます。
・許可を得たが、営農が継続されず許可取り消しとなった
・パネル配置が過密で作物が育たない
・農地転用許可期間(10年)を更新せず、違法状態になった
・地権者との契約トラブル(賃料・撤去費用など)
契約段階でのトラブル防止策を盛り込むようになります。
たとえば、
「撤去費用は事業者負担とする」
「営農報告書を毎年提出する」
「契約終了時に原状回復する」
といった条項を覚書や契約書に明記しておくことで、後々の紛争を防げます。
7. 福島県・郡山市のローカルルールにも注意
福島県では、独自の「営農型太陽光ガイドライン」の取り扱いをしています。
特に郡山市をはじめとする自治体では、
農業委員会・農政課・再エネ推進課など複数部署との調整が求められ、
地域ごとに書類様式や審査基準が異なります。
郡山市の場合、
・営農型太陽光発電導入に関する事前相談制度
・農地法申請に加え農振除外・用途地域確認の必要性
・再エネ設備撤去計画書の添付義務
などがあります。
8. 行政書士が支援することで得られるメリット
営農型太陽光発電は、農地法・電気事業法・再エネ特措法・建築基準法など、
複数の法制度が関係する複雑な事業です。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
・手続き全体のスケジュール管理がスムーズ
・農業委員会や役所との調整を代行してもらえる
・書類不備や審査落ちのリスクを大幅に軽減
・許可後の更新手続き・報告書作成まで一貫対応
まとめ:営農型太陽光発電は行政書士の新たな活躍分野
営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)は、
「農地を守りながら収益を生み出す新しい仕組み」です。
しかし、制度的にはまだ発展途上であり、申請手続きも複雑です。
行政書士がこの分野に関与することで、
農家・事業者双方の橋渡し役として、地域の再エネ推進に貢献できます。
今後、営農型太陽光は「農地転用」や「再エネ導入支援」といった
行政書士業務の中でも重要なテーマになっていくでしょう。
当事務所では「営農型太陽光」の申請を取り扱っておりますので、
営農型太陽光を検討しており申請にお困りの場合は、
当事務所へご相談ください。
※農地法に関する記事は下記より