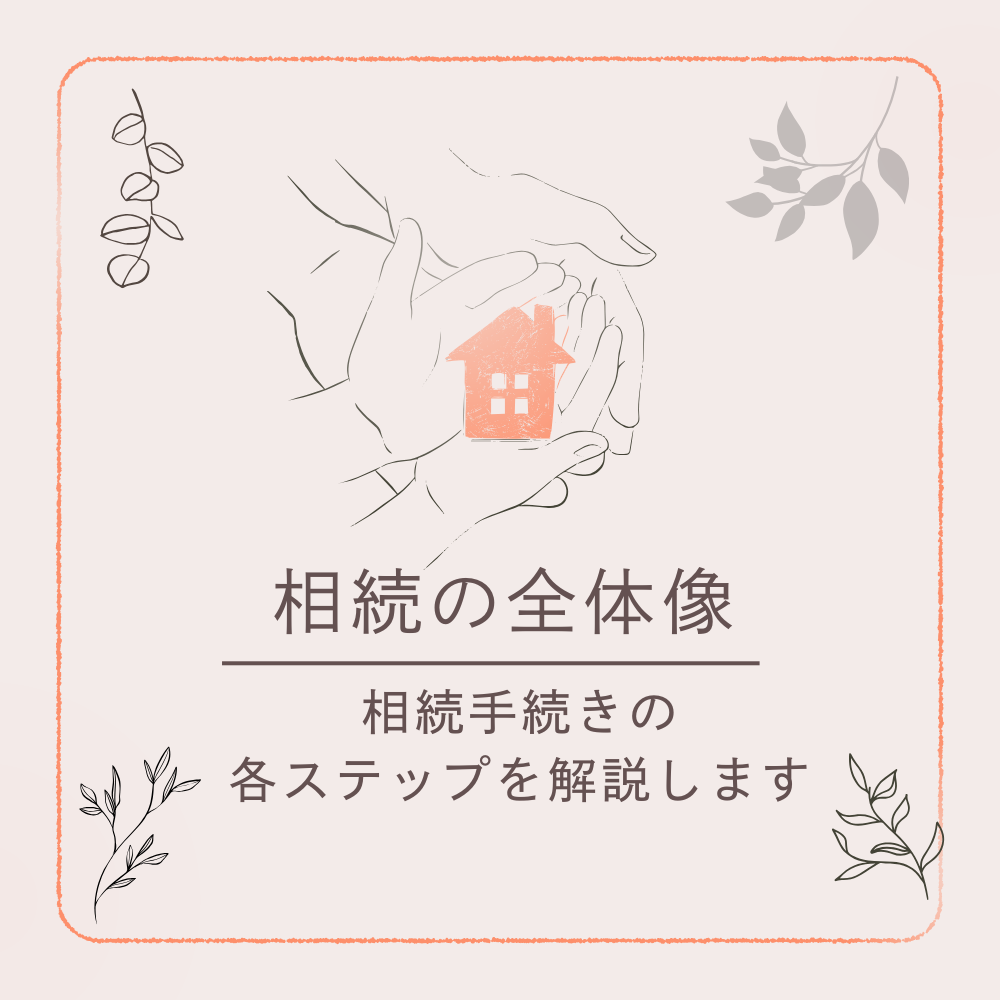親が元気なうちに家をどうする?知らないと損する任意後見制度の話

目次
はじめに
最近、「親が高齢になって実家をどうするか悩んでいる」という話を聞きます。
いつかは必ず訪れる「相続」について漠然とした不安があるようです。
実家の将来について何も話し合わずにいた結果、相続後に空き家となり、
売ることも貸すこともできず困っているというケースは少なくありません。
実はこの問題、親が元気なうちにできる対策があるのです。
それが「任意後見制度」です。
任意後見について、そして法定後見制度との違い
「後見制度」とは、認知症や知的障害、精神障害などで、
判断能力が不十分な人を法律的に支援する仕組みです。
本人の意思を尊重しつつ、生活・財産・法律行為を安全に行えるよう、
家庭裁判所が選んだ「後見人」などが代理・支援する制度です。
後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、
相続対策として「任意後見制度」の利用が期待されています。
任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が低下したときに備えて、
本人が“元気なうちに”信頼できる人(任意後見人)を選んでおく制度です。
✅ 任意後見制度の概要
項目 内容 制度名 任意後見制度(民法第652条の2〜) 対象者 将来に備えたい「判断能力がある本人」 契約方法 公正証書による任意後見契約 発効タイミング 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したとき 主な内容 財産管理、契約手続、役所対応など、本人の生活支援全般
🧠 任意後見と法定後見の違い
比較項目 任意後見 法定後見 始まる時期 元気なうちに契約、発動は将来 すでに判断能力が低下した時 後見人の決定方法 本人が選ぶ 家庭裁判所が決める 契約の自由度 高い(内容を細かく設定できる) 制限あり(法律上の範囲に限る) 必要書類 公正証書+発動時に医師の診断書など 医師の診断書などで即開始
📖 民法の該当条文 ※念のため!
● 民法第652条の2【任意後見契約の定義】
任意後見契約とは、本人が精神上の障害により判断能力が不十分となった場合に、
自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について、
あらかじめ契約によって委任することをいう。
👉 ポイント:
- 判断能力が十分なうちに契約
- 将来に備えるための事務委任契約
- 内容は柔軟に設計可能(財産管理・身上監護など)
● 民法第652条の3【公正証書の要件】
任意後見契約は、公証人によって作成された公正証書によってしなければ、その効力を生じない。
任意後見契約は公正証書で作成し、任意後見人は代理権目録の範囲内で代理します。
公正証書ということで公証人との面談もあります。
✅ 任意後見契約における公証人面談の目的
目的 内容 ① 本人の判断能力の確認 認知症などで意思能力がない状態では契約できないため、公証人が「理解しているか」を直接確認 ② 本人の自由意思の確認 誰かに無理に契約させられていないかを確認(圧力・詐欺の防止) ③ 契約内容の説明 公証人が契約条項を読み上げ、本人に説明・同意を求める
○面談の流れ(一般的なケース)
- 日時予約(公証役場にて)
- 必要書類の提出(契約書案・本人確認書類など)
- 当日:面談と公正証書の読み聞かせ(30分〜1時間)
- 公証人が契約の趣旨・内容を読み上げる
- 本人に「理解しているかどうか」を質問
- 問題なければ署名・押印し、契約が成立
- 契約書交付(正本・謄本)
では次に法定後見制度についても簡単にみていきます。
✅ 法定後見制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が低下した人 |
| 利用開始 | 家庭裁判所に申立て → 裁判所が後見人を選任 |
| 後見人の役割 | 本人に代わって、財産管理・契約・行政手続きなどを行う |
| 法的根拠 | 民法第7条~ |
🔍 法定後見の3つの類型(本人の判断能力に応じて分類)
| 類型 | 判断能力 | 支援内容 | 例 |
|---|---|---|---|
| ✅ 後見 | 常に判断できない | 代理権・取消権(広範囲) | 重度の認知症など |
| ✅ 保佐 | 著しく不十分 | 一部に同意権・代理権 | 中程度の認知症・知的障害 |
| ✅ 補助 | 不十分なことがある | 同意権・代理権(一部) | 軽度の精神障害など |
🛠 申立人になれる人(誰が手続きできる?)
- 本人(自分で申し立てられる場合も)
- 配偶者・子ども・親族
- 市区町村長(親族がいない、または同意が得られない場合)
法定後見制度は家庭裁判所が指定した後見人が担当することになり、
第三者が財産を管理することも大いにあり得ます。
そして一度法定後見制度を利用するとやめようにもやめられないので、
ずっと財産を管理されるようになるため、私は法定後見制度は推奨しません。
任意後見制度の場合、後見人の多くは親族が担当します。
配偶者(夫から見て妻)を後見人でも良いのですが、
年齢が近い場合は夫が認知症になる前に、妻が認知症になる可能性もありますので、
子が後見人としてはふさわしいかと思います。
本人の法律行為を代理するのというのは,
自分の分身となって動いてもらうようなイメージになりますので、
相当信頼関係が築けていないと第三者が任意後見の後見人になることは難しいかと思います。
任意後見と空き家の関係性
では、空き家と任意後見制度がどのように絡んでくるのでしょうか。
法定後見制度と任意後見制度を比べると、
財産の処分の際に違いが出てきます。
法定後見制度の場合、空き家となった家を売却したいと考えたときに、
成年後見人が了承すればすんなり売りに出せるわけではありません。
家庭裁判所に申し出を行い、家庭裁判所から許可がでないと処分ができないため、
「不当に安く売買されている」と判断される場合は家庭裁判所からの許可が下りず、
空き家の売却もできないことになります。
一方、任意後見制度の場合、後見人が不動産の処分も任されている場合は、
家庭裁判所、任意後見監督人への確認も不要で売却することができます。
法定後見制度のように「売れるかわからない不動産」は買主からの印象はとても悪いため、
処分しやすくするためには「任意後見制度」を活用して売却すべきだと思います。
任意後見制度のデメリット
良いことばかり話をしましたので、次はデメリットについてみていきます。
❗任意後見制度のデメリット7選
1. 契約しても“すぐ”効力は発生しない
- 任意後見契約を結んでも、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してからでないと効力は発生しません。
- つまり「契約だけでは動けない」ため、緊急時の対応には向かない。
2. 公正証書の作成が必要で、やや手間がかかる
- 契約は必ず公証役場で公正証書として作成する必要があります。
- 手数料(1〜2万円程度)+印紙代+必要書類の準備など、手続きがやや煩雑。
3. 任意後見監督人の報酬がかかる
- 任意後見が開始されると、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人(多くは弁護士・司法書士)に月額1万~3万円程度の報酬が発生します。
- 本人の財産から支払うとはいえ、長期にわたると負担になります。
4. 任意後見人の権限に制限がある
- 法律で明確に代理できる内容が限られ、すべての法律行為ができるわけではありません。
- 特に「遺言の作成」「死後の手続き」「医療の同意」「生命保険の契約」などは対象外。
- → 必要に応じて「死後事務委任契約」や「財産管理委任契約」との併用が必要。
5. 悪用・トラブルのリスクもある
- 契約内容や後見人選定が適切でないと、財産の流用や意思の不一致などのトラブルに発展する可能性があります。
- 監督人制度があるとはいえ、身内同士での不透明な契約には慎重さが求められます。
6. 判断能力の「境界線」があいまいで発動のタイミングが難しい
- 「いつから後見を開始すべきか」は医師の診断や家庭裁判所の判断に委ねられます。
- そのため、「まだ始まらないの?」「もう限界なのに…」という家族のジレンマが起きやすい。
7. 広く知られておらず、理解されにくい
- 任意後見制度は制度自体がまだ認知度が低く、本人や親族が制度の仕組みを理解しにくいことがあります。
- 特に高齢者本人が「必要ない」と思いがちで、契約までに時間がかかることも。
おわりに
任意後見制度を推奨する理由は、行政書士としてだけでなく、
家族・地域・財産を守る実務的な視点からも非常に合理的かつ安心できる制度だからです。
✅ 任意後見制度を推奨する5つの理由
① 本人の「意思」が元気なうちに反映できるから
任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに「誰に、何を、どう任せるか」を自分で決められる制度です。
→ これは自己決定権を最大限尊重する仕組みです。🟢 推奨理由:
「誰に」「どういうことを」「どのようにしてほしいか」を契約に書けるため、将来の不安を事前にコントロールできます。
② 判断能力が失われた後でもスムーズに手続きできるから
認知症などで判断能力を失うと、たとえ家族でも──
- 銀行口座が使えない
- 不動産の売却ができない
- 施設への入所契約ができない
という「法的な壁」が立ちはだかります。
🟢 推奨理由:
任意後見契約があれば、こうした法律行為を円滑に進める代理人を前もって指定できるため、家族の手続き負担を大きく減らせます。
③ 法定後見よりも自由度が高く、柔軟に備えられるから
項目 任意後見 法定後見 後見人の選び方 本人が自由に選べる 家庭裁判所が決定 始まるタイミング 本人の意思で契約→後から効力発生 申立て後すぐ発動 契約内容 自由に設定できる 法律の定型業務に限定される 🟢 推奨理由:
「親しい人に支援してもらいたい」「柔軟に決めたい」などの希望を反映できるのは任意後見ならではです。
④ 空き家・相続・施設入所など現実的な課題に対応できるから
例えばこんな場面でも、任意後見は力を発揮します。
- 実家が空き家になる前に、後見人が売却手続きを代理
- 介護施設への入所手続きをスムーズに進行
- 相続対策として「生前整理」「名義変更」などを行う
🟢 推奨理由:
「実家が売れない」「介護の同意がとれない」「相続手続きが滞る」といった問題を事前に防げる制度的な備えです。
⑤ 家族の安心・負担軽減になるから
高齢の親を持つ子ども世代は、仕事・育児・介護と多忙です。
任意後見制度があれば、家族間で「誰が何をするか」をあらかじめ整理でき、トラブル回避と負担軽減につながります。🟢 推奨理由:
「自分の親には、自分が後見人になってきちんと支える」ことを制度として確保できます。
遺言は「死後の財産配分」の話になりますので、生前手続きをカバーできませんが、
任意後見制度は「生前の手続き」をカバーすることができます。
また死後においても遺言で「葬式はこうしてほしい」と書いても法的拘束力がなく、
遺言でもカバーできない内容があります。
そのような場合は任意後見の他に「死後事務委任契約」とものが存在します。
「死後事務委任契約(しごじむ いにんけいやく)」とは、
本人が亡くなったあとに必要になる事務手続きを、
信頼できる人にあらかじめ委任しておく契約です。
遺言では対応できない「死後の現実的な手続き」を円滑に進めるために、
任意後見契約や遺言とセットで活用されることが多い制度です。
📋 死後事務で委任できる代表的な内容
手続き 内容 死亡届の提出 市区町村役場への届出 火葬・埋葬の手続き 火葬場の予約、埋葬許可申請など 病院・施設の清算 入院費・入所費の支払い、退去手続き 住民票・年金・保険の返納 健康保険証・マイナンバーカードなどの返納 公共料金・携帯電話等の解約 ガス・水道・スマホ・NHKなどの契約解除 遺品整理・賃貸物件の退去 不用品処分、部屋の明け渡し、家財の管理 ペットの引き渡し 飼育者への引き継ぎ、施設委託など 葬儀に関する事項 規模・方法・場所などの希望(実行義務なし)
✅ 遺言と“併用すべき”制度(補完的に使うべきもの)
カバーできない点 補う制度 認知症時の備え 任意後見契約・財産管理委任契約 死後の事務(葬儀・解約など) 死後事務委任契約 生前贈与・財産整理 民事信託・生前贈与契約 遺言内容の実行 遺言執行者選任+専門家サポート
当事務所では任意後見契約書の作成や財産管理契約の作成を行っています。
将来的に実家に戻る予定はなくかつ親がひとりで住んでいるという事例で多く活用していますので、
もし活用を検討される場合は当事務所にご相談ください。
その他用事務所における相続業務については下記よりご覧ください。