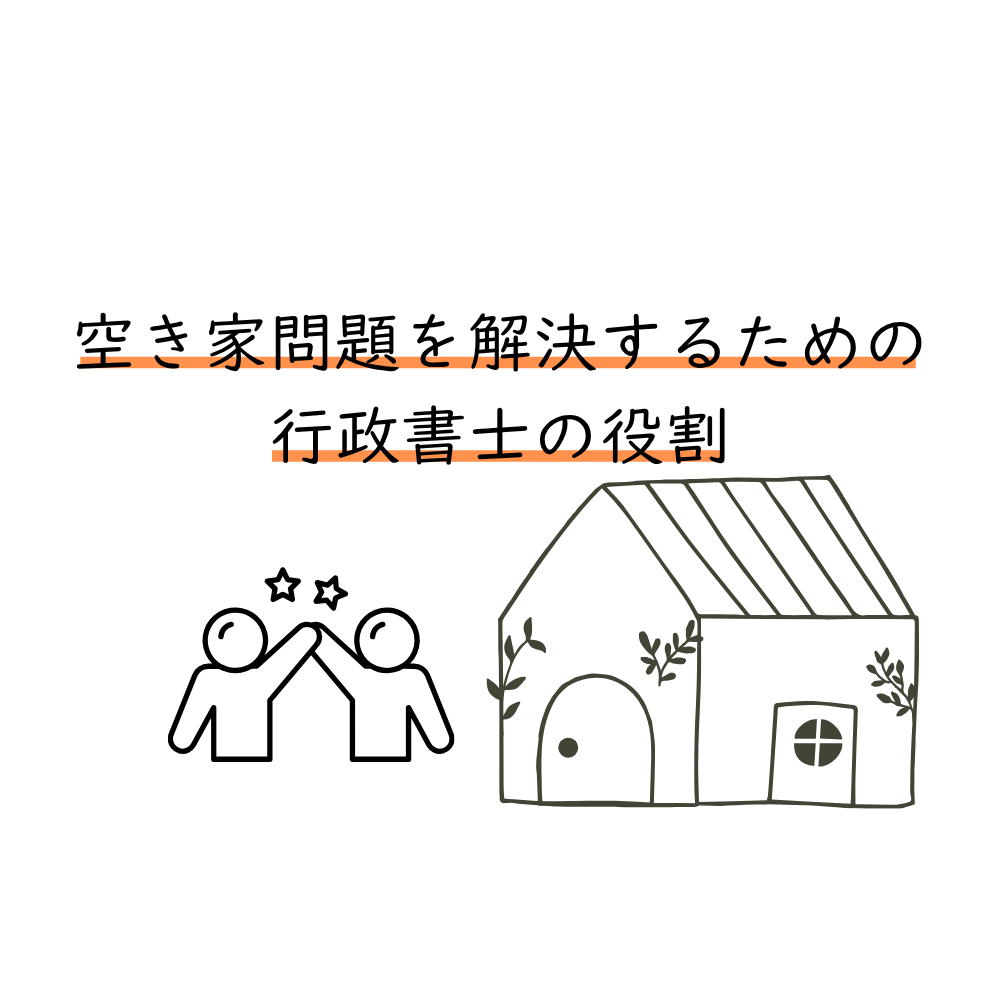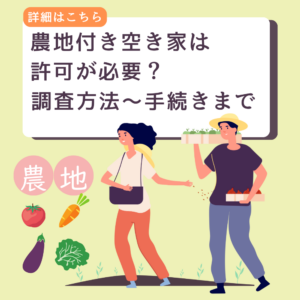郡山市の行政書士が解説!不動産調査の基本とチェックポイント

目次
はじめに
土地や中古住宅、マンションを購入したあとに『こんな制限があったなんて…』と後悔する方が少なくありません。
不動産調査は、トラブルを防ぎ、安心して不動産を利用するための第一歩です。
今回の記事では、郡山市で不動産手続きを数多く行う行政書士が、
不動産調査の基本をわかりやすく解説します。
不動産調査の全体像
不動産調査とは、対象地について 法的・物理的・権利的・利用的な制約や可能性を明らかにする作業 です。
大きく分けて次の4分類で整理します。
区分 内容 主な資料・調査先
① 権利関係調査 所有者・抵当権・地上権・賃借権・相続関係 登記簿謄本、固定資産課税台帳など
② 法令上の制限調査 都市計画、建築、農地、森林、道路、河川などの制限 市役所(都市計画課・開発建築法務課・道路保全課)など
③ 現況・地形・インフラ調査 接道、上下水道、電気、ガス、境界、地目 現地確認、公図、地積測量図、航空写真、上下水道台帳
④ 利用可能性・市場性調査 用途地域・建蔽率・容積率、地価、周辺環境、利便性 都市計画図、地価公示、Googleマップ、ゼンリン地図
調査としてまず取り組むものとしては書類関係を収集です。
①場所の確認(地図、Googleマップ)
②都市計画情報(地番、都市計画、道路の関係)
③登記簿謄本の取得(所有者の特定、抵当権の有無、その他差押の登記などを確認)
④ライフラインの確認(水道局の上下水道図面、受益者負担金の有無、都市ガス区域かプロパンガスか)
※ガスに関しては現地のガスメーターで都市ガスかプロパンガスか判断します
なぜ現地確認の前かと言うと、書類の段階でどのような物件なのか?についてある程度、見込みができるからです。
最初に現地確認→次に書類の収集ですと現地と図面関係の整合性が取れないと再度現地へ赴くようになってしまいますので、
実務上、書類収集からはじめるとスムーズです。
権利関係調査
調査の手順について解説しましたが、まず行う必要があるのが権利関係調査です。
所有者が自分で調査を行う場合は例外ですが、まず「所有者」の特定が大事です。
Netflixの人気ドラマ「地面師たち」でも「不動産詐欺」についてのストーリーが展開されていましたが、
ドラマのように運転免許証や印鑑証明書まで偽造されると本人確認書類として問題無いとして、
詐欺事件に騙される可能性があります。
ドラマでも「所有者でない第三者」として地面師たちがやり取りをしていたことから、
「所有者でない第三者」が間に入ってコンタクトを取っている、
「売却を急ぎたい」の案件は特に慎重になるべきです。
所有者の特定は「登記簿謄本」で権利を確認します。
2025年4月より相続登記の義務化がありますので、相続登記をしていない場合は、
相続人間で話し合いをして遺産分割協議書類の作成を行い、司法書士の先生に登記をお願いする作業が出てきます。
登記事項についての確認事項は以下の通りです。
登記事項(読むべきポイント) — 表題部 / 甲区 / 乙区
- 表題部(表示):所在・地番/家屋番号・地目・地積・構造・床面積 → 現況と一致するか(地番違い、未登記建物が無いか等)
- 甲区(所有権):登記名義人(氏名・住所)・共有か単独か・移転履歴・登記原因・日付 → 実際の所有者と一致するか、所有者が死亡していないか、住所が古くないか確認。
- 乙区(負担/担保など):抵当権・根抵当・地上権・地役権・賃借権(登記されていれば)・差押・仮登記 → 根抵当の極度額、順位、差押えの有無は重大リスク。
- 仮登記・仮差押:契約上の優先権や競売回避に影響。
- 閉鎖登記情報(過去の抹消情報):過去の権利変動や担保履歴把握に有用。
不動産が共有で所有している場合(持分2分の1など)は、
持分だけの売却は持分者で自由に売却できますが、
通常は持分すべての売却になることが多いですので、
持分全部の場合は持分者全員で契約書を取り交わすようになります。
法令上の制限調査
不動産調査における法令上の制限調査とは、
対象不動産の「利用・開発・建築などに対して、
どの法律が制約をかけているか」を確認する調査です。
調査するのは主に役所調査になります。
役所調査は役所に行かなくても、
「郡山市地理情報システム」である程度調査はできます。
〈郡山市地理情報システム〉
https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/130/6476.html
確認すべき項目は主な内容は以下の通りです。
都市計画・建築関係
項目 主な根拠法令 確認内容 都市計画区域・用途地域 都市計画法 市街化区域/調整区域、用途地域(第一種住居など)、容積率・建ぺい率、地区計画、都市計画道路の有無 建築基準法制限 建築基準法 接道義務(42条道路)、高さ制限、日影規制、防火・準防火地域、建築確認申請の有無、検査済証の有無 開発行為の制限 都市計画法29条 宅地造成・建築物建築のための開発許可要否
上記の他、不動産調査における「道路の調査」は、
建築・開発・農地転用・売買・境界確定など、あらゆる業務の根幹になる重要項目です。
特に、建築基準法上の「接道要件(42条道路)」の確認を誤ると、
建築不可地や転用不可地に該当してしまうこともありますので要注意です。
道路調査の全体像と確認項目は下記の通りです。
※専門性が高いこともあり、調査に関しては専門家にお願いするのがベストです
道路調査の基本項目(全体像)
調査項目 主な確認内容 担当部署・資料 (1) 道路の種別 公道 or 私道か。管理者は誰か(国・県・市・個人)。 市道課、県土木事務所、道路台帳、公図 (2) 建築基準法上の道路種別(42条道路) 1項1号~5号道路/2項道路か。接道義務を満たすか(幅員4m以上・2m以上接道)。 建築指導課、道路台帳図、公図、航空写真 (3) 幅員 4m以上あるか(2項道路の場合中心後退要)。 現地実測+道路台帳 (4) 道路中心線・境界線 敷地と道路の境界確定(道路境界確定図の有無)。 ※確認できるようでしたら (5) 通行権・位置指定道路 私道の場合:通行承諾、位置指定番号の有無、管理者同意。 建築指導課、所有者、位置指定道路台帳 (6) 道路の接続形態 どの地番に接しているか、間口幅(2m以上)。 現地確認+地図測量 (7) 道路の現況 アスファルト舗装か、未舗装か、水路・側溝の有無。 現地調査 (8) 公道への到達経路 公道までの連絡通路が確保されているか。 現地+公図で連続確認 (9) 法定外公共物 水路・里道・法定外道路が通っていないか。 財産管理課(市役所) (10) 埋設物・占用物件 ガス・水道・電柱など。道路占用許可必要か。 各管理会社・市道占用担当課
🔹建築基準法上の「道路」分類(第42条)
建築の可否を決める最重要ポイントです。
区分 概要 典型例 42条1項1号道路 道路法による道路(国道・県道・市道など)。 公道(道路台帳あり) 42条1項2号道路 都市計画法等に基づく開発道路。 開発分譲地の新設道路 42条1項3号道路 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に既に存在していた幅4m以上の道。 古くからの集落道 42条1項4号道路 特定行政庁が指定した道(指定道路)。 古い市街地の主要生活道路 42条1項5号道路 位置指定道路(建築基準法43条1項に基づく)。 分譲地開発で民間が造成した道路 42条2項道路 幅4m未満で特定行政庁が指定する既存道路(セットバック要)。 古い住宅地の細い道路
🔹私道の調査ポイント
調査観点 確認内容 所有者 登記簿で所有者確認(複数の場合は共有者一覧)。 通行権 通行承諾書・覚書・地役権設定登記の有無。 管理状況 排水・舗装・除雪・修繕費負担方法。 位置指定番号 建築指導課で位置指定の有無(指定年月日・番号)を確認。 セットバック要否 2項道路・非指定の場合、後退が必要。 他人地通行 私道を経由して公道に出る場合は通行権の確認必須。
現況・地形・インフラの調査
「現況・地形・インフラ調査」は、不動産の現地実態を把握し、登記・都市計画・法令情報との整合性を確認するための重要な調査フェーズです。
現地と図面が異なる場合もあり、現地をよく確認する必要があります。
主な調査内容は下記の通りです。
インフラ調査の内容
区分 確認項目 担当課・資料 上水道 本管の有無・口径、管径、引込の有無・口径 上下水道局・水道課 下水道 公共下水・浄化槽区分、負担金の有無 下水道課 雨水排水 雨水管・側溝・宅地排水経路 主に現地 電気 電柱・引込線の有無。 東北電力(送配電) ガス 都市ガス供給区域か、プロパン利用か ガス事業者・供給区域図
水道管が他人の土地に埋設されている場合、所有者から所有権に基づく物件排除請求権を行使された場合、
水道管を撤去する必要性も出てきますので、水道管がどこに位置しているかはとても重要な情報になります。
利用可能性・市場性調査について
物件調査は上記で完了していますが、
「利用可能性・市場性調査」は、不動産の“法的に利用できるか”だけでなく、
「経済的に価値を生み出せるか(活用できる不動産かどうか)」を判断する最終ステージの調査になります。
解説した調査内容と重複がありますが、
主な確認事項は以下の通りです。
利用可能性調査の内容(=使えるかどうか)
分野 調査項目 主な確認内容・判断ポイント 法的制限 都市計画・用途地域 建築可能用途(住居・店舗・工場等)、建ぺい率・容積率、開発許可要否 建築基準法 接道要件・防火地域・高さ制限・斜線制限など 農地法・農振法 農地転用可能か、営農継続の可否、転用手続きの難易度 森林法・自然公園法 転用・伐採許可の要否、環境規制 物理的条件 地形・高低差 建築可否・造成費・排水方向 地盤・地質 建築コスト(杭・改良の要否) 接道・インフラ 上下水道・電気・ガスなどの利用可否 環境条件 周辺環境・騒音・日照 住居・商業・工業いずれに適しているか 災害リスク 洪水・土砂災害区域など建築制限の有無 権利関係 所有・抵当・賃借 開発・売却・転貸に支障がないか
利用可能性、市場性を調査することにより、物件の価値を計算します。
上記の作業を行うことにより、地価公示価格、固定資産税評価額などの公的機関の資料をもとに、
不動産の評価額を算出することもできます。
最後にこれまでの内容を踏まえた総合チェックポイントをまとめました。
不動産調査 総合チェックリスト(郡山市版)
【Ⅰ.権利関係調査】
No チェック項目 内容確認 資料・確認先 結果・備考 1 登記簿確認(表題部) 所在・地番・地目・地積・家屋番号を確認 登記簿謄本 2 所有者・住所 所有名義人・住所・共有関係を確認 登記簿謄本 3 甲区(所有権) 登記原因・移転履歴 登記簿謄本 4 乙区(抵当・根抵当) 抵当権・根抵当・仮登記・差押等の有無 登記簿謄本 5 相続・会社関係 相続未登記・法人登記変更の有無 戸籍・商業登記簿 6 賃借関係 登記・契約書・現地占有状況 聞取・現地調査 7 境界確定 境界確定図・官民査定の有無 土地家屋調査士・市役所
【Ⅱ.法令上の制限調査】
No チェック項目 内容確認 法令・担当部署 結果・備考 1 都市計画区域 区域区分(市街化/調整) 都市計画法・都市計画課 2 用途地域 種別・建ぺい率・容積率 都市計画課 3 高度地区・防火地域 高さ・構造制限 建築基準法・開発建築法務課 4 開発許可要否 宅地造成・建築行為の可否 都市計画法29条・都市計画課 5 道路種別 建築基準法上の道路(42条1項・2項) 開発建築法務課・道路保全課 6 農地・農振地域 農地転用許可要否、農振除外要否 農業委員会・農政課 7 森林 保安林・伐採許可要否 森林法・県森林整備課 8 河川・水路 河川区域・占用許可の要否 河川法・河川課 9 景観・風致 景観計画区域・届出要否 景観法 10 防災・災害区域 土砂・洪水・地すべり・盛土規制 水防法・盛土規制法・防災課 11 文化財 埋蔵文化財包蔵地内外 文化財保護法・教育委員会
【Ⅲ.現地・ライフライン関係調査】
No チェック項目 内容確認 確認方法・部署 結果・備考 1 地目・現況 登記地目と現況の一致 現地調査・写真 2 境界杭 境界杭の有無・越境物 現地・確定測量図 3 高低差・地形 前面道路との高低差、傾斜の有無 現地確認 4 法面・擁壁 構造・老朽化・安全性 現地調査 5 地盤 盛土・埋立・軟弱地盤 地盤情報・過去航空写真 6 道路接道 間口幅・42条該当性 道路台帳・現地確認 7 上水道 本管・引込・メーター有無 上下水道局 8 下水道 公共下水・浄化槽区分 上下水道局 9 雨水排水 側溝・排水方向・越境排水 現地 10 電気・通信 引込線・電柱・光回線 東北電力・通信業者 11 ガス 都市ガス供給区域か ガス事業者 12 環境 騒音・臭気・眺望・日照 現地確認・周辺調査
【Ⅳ.利用可能性・市場性調査】
No チェック項目 内容確認 確認資料・方法 結果・備考 1 用途適性 建築・転用・開発可否 都市計画・農地法 2 立地・交通 駅距離・幹線アクセス 地図・現地確認 3 周辺環境 商業・教育・医療施設 現地・マップ 4 地価水準 公示地価・取引事例 地価公示・REINS等 5 賃料・需要 賃貸需要・賃料相場 不動産サイト・統計 6 地域動向 人口推移・再開発計画 市統計・都市計画情報 7 想定活用 戸建・賃貸・店舗・太陽光等 総合判断 8 総合評価 利用可・条件付可・不可 各調査結果総合
おわりに
本テーマだけでもかなりボリュームがありますが、基本的な話になります。
実際の不動産取引になると、より細かな法令の調査をする必要がありますが、
一度にこの記事でまとめるのが困難でありましたので、
各テーマを設けて取り上げていきたいと思います。
今回の記事は、不動産調査の初心者向けの記事として書きました。
本テーマに関するご質問等ありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。
※関連記事は下記より