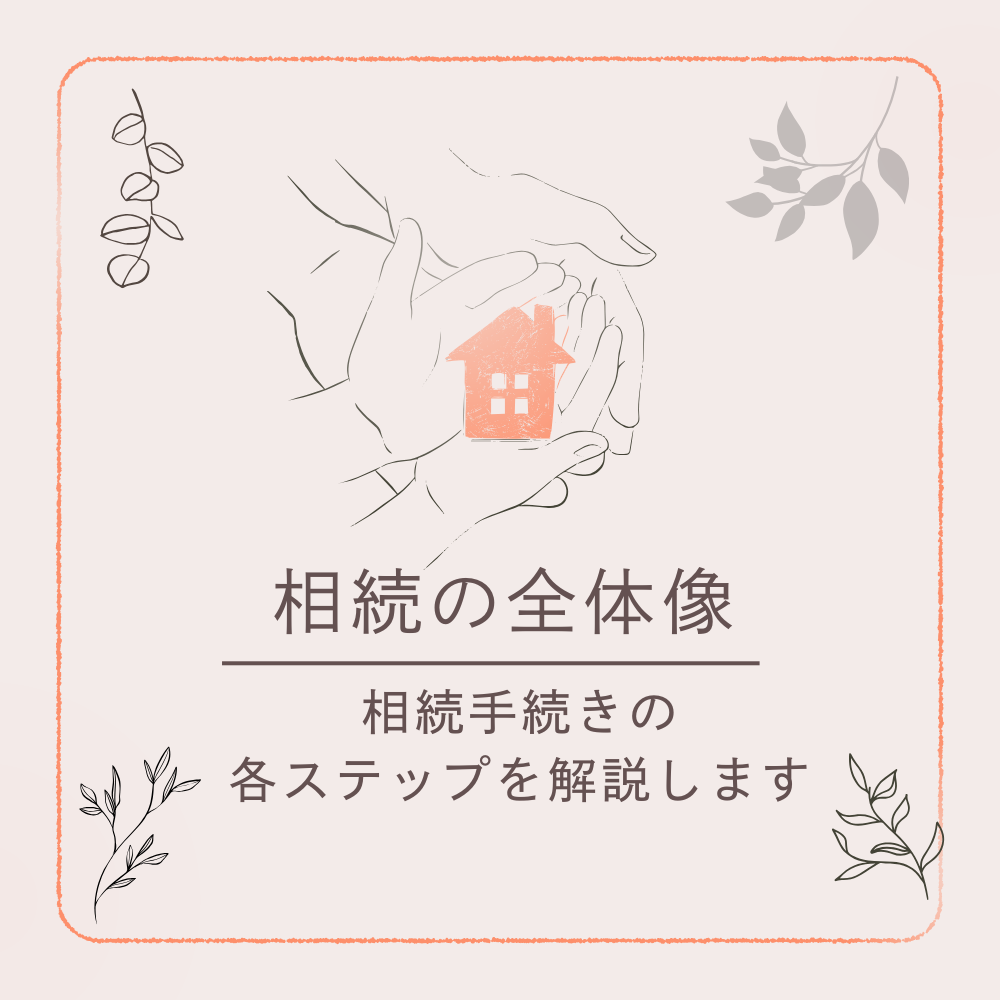これだけ抑える!相続の基本原則~後編
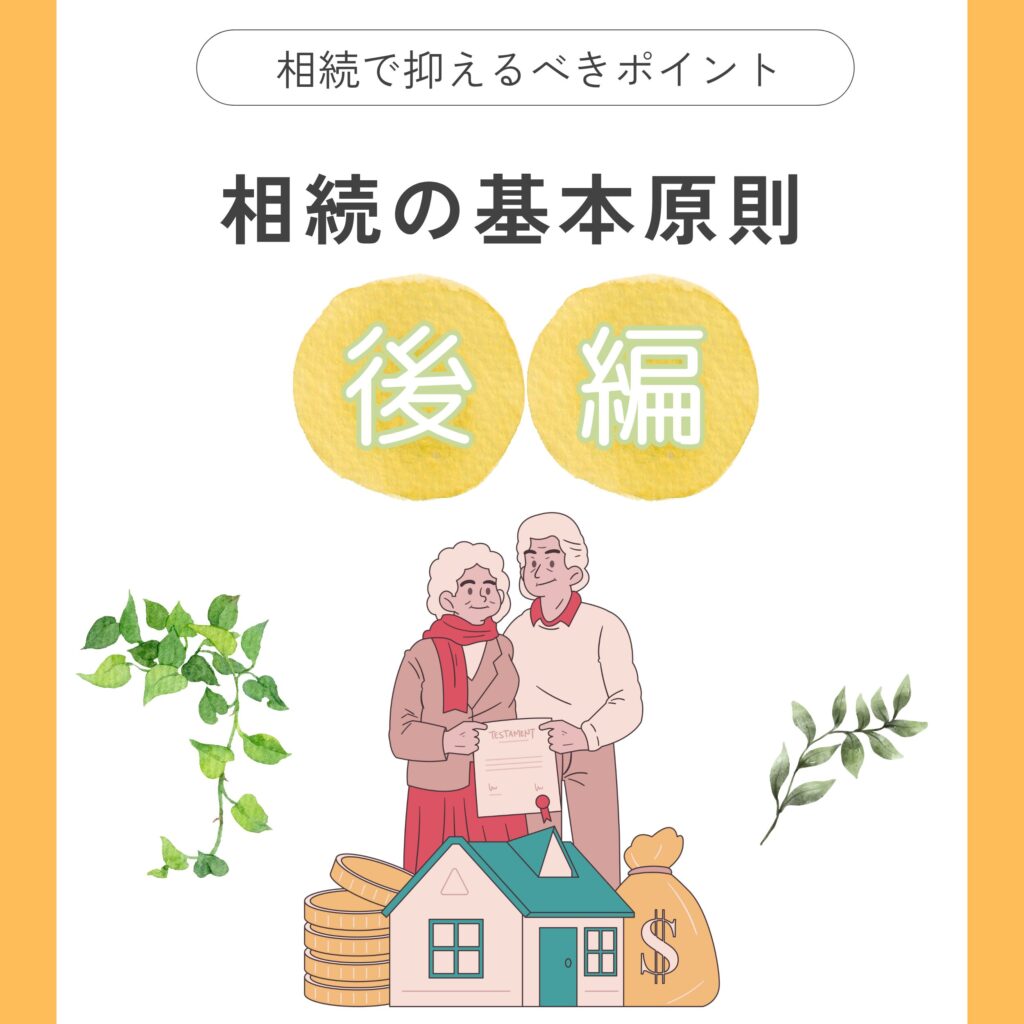
目次
はじめに:相続財産と相続分について
前編では主に「相続人の範囲」は誰どこまでか?という話がメインでありましたが、
後編では「相続財産」と「相続分」が主な話になります。
相続財産は民法第896条から899条の2、相続分は民法第900条から905条に記載があります。
これらすべての条文を確認するのは基本原則といえないため、一部抜粋した形で基本原則とさせていただきます。
まずは該当する条文を確認していきます。
相続の基本原則
民法896条の条文
(相続の一般的効果)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
民法897条(祭祀に関する権利の承継)
- 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従い、祖先の祭祀を主催すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って承継者を定めたときは、その指定に従う。
- 前項の権利を承継すべき者がない場合、又は判明しない場合は、家庭裁判所が承継者を定める。
民法898条(相続財産の共有関係)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
民法899条(相続財産の帰属)
相続財産は、相続開始の時に、相続人に帰属する。
民法第900条(法定相続分)
被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹及び配偶者の相続分は、次の各号に掲げる場合に従って、これを定める。
- 被相続人に子があるときは、配偶者と子が相続人となり、相続分は、配偶者が二分の一、子が二分の一とする。
- 被相続人に子がなく、直系尊属があるときは、配偶者と直系尊属が相続人となり、相続分は、配偶者が三分の二、直系尊属が三分の一とする。
- 被相続人に子も直系尊属もなく、兄弟姉妹があるときは、配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、相続分は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一とする。
- 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、その相続分は、各自、等しいものとする。
- 子が数人ある場合において、その中に養子があるときも、養子の相続分は、実子と同じとする。ただし、特別養子の場合を除く。
民法第901条(代襲相続人の相続分)
代襲相続人の相続分は、被代襲者(本来相続するはずだった人)の相続分による。
民法第903条(特別受益者の相続分)
第903条
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
その受けた利益(=特別受益)は、遺産の前渡し(=「持戻し」)とみなして、相続分を計算する。ただし、被相続人が、その利益を相続分に算入しない旨の意思を表示したときは、この限りでない。
② 前項の場合において、相続分を計算した結果、特別受益の額がその者の相続分に相当する額を超えるときは、その者は、他の共同相続人に対してその超過額を返還する義務を負わない。
ここを抑える!民法 第896条について
民法第896条では財産の範囲について書いています。
相続人は、被相続人(亡くなった人)のプラスの財産(不動産、預貯金、債権など)だけでなく、マイナスの財産(借金、債務、保証債務など)も引き継ぎます。
相続人はそのまま承認すれば(単純承認と言います)すべての財産を引き継ぎようになるため、借金などがあればその債務を引き継ぐようになります。
マイナスの財産が多く、相続してもマイナスになる場合は相続放棄(相続人としての権利をなくすこと)の手続きを行います。
※相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述書の提出をすることにより相続放棄が可能です
相続されない財産として「一身に専属するもの」とあります。
これはその人だけの権利であるものが該当し、「免許資格」や生活保護受給権、身分上の権利(親権など)が該当します。
これはなんとなく想像できるかと思います。
全く勉強していないのに医師免許を持っていたら、誰もその先生にはお願いしたくないですよね...
ちなみに生命保険金については一般的には受取人固有の財産としています。
生命保険と相続の関係性については別テーマで取り上げます。
ここを抑える!民法 第897条について
次に民法第897条です。
ここでは祭祀(さいし)財産について述べています。
祭祀財産は位牌、仏壇、墓石などの管理が必要な場合があり、
遺言書を記載する場合は祭祀主宰者を指定します。
祭祀主宰者とは単にお墓を守る人と捉えれば大丈夫です。
系譜(家系図)、祭具(位牌、仏壇、神棚など)、墳墓(墓石、墓地の所有権など)など、
金銭的価値よりも精神的・宗教的意義が強い財産であり、通常の相続財産(民法896条)とは区別されます。
承継としては、次の順番で優先されます。
①被相続人の指定(遺言や生前の意思表示)が最優先
②慣習(地域・家のしきたり)
③家庭裁判所の審判(承継者がいない場合)
ここを抑える!民法 第898条について
次に民法第898条です。
ここで抑えるのは共同相続(複数人で相続する場合)では、相続財産は全相続人の共有状態となることです。
遺産分割協議が完了したら財産は各相続人に分けられますが、完了するまで、各相続人の権利は潜在的に共有持分として扱われます。
遺言書があれば遺産分割協議書も不要で遺言書通りに財産が分けられますが、遺言書がなければ、まず相続人の共有となります。
相続人全員の同意なしに、個別の遺産を売却・処分はできません(民法第251条)ので注意しましょう!
ここを抑える!民法 第899条について
民法第899条は相続財産がいつ、誰に承継されるのかを明確に定めたものです。
①「相続開始の時」(=被相続人の死亡時)に、
②自動的かつ包括的に相続人に承継されます
不動産・預貯金・株式などの権利は、被相続人の死亡と同時に相続人に移転します。
つまり相続開始後、すぐに相続人が管理責任を負うことになります。
ここを抑える!民法 第900条について
民法第900条は「法定相続分」の条文であり、相続を知るうえでは重要な条文です。
法定相続分とは被相続人(亡くなった人)に遺言がない場合に、民法によって定められた各相続人の相続割合のことです。
以下の基本パターンを抑えることで「相続人は誰なのか?」の回答に近づくことができます。
相続人ごとの法定相続分(基本パターン)
被相続人に 配偶者がいるかどうか によって整理されます
➤ ① 配偶者と子どもがいる場合
- 配偶者:1/2
- 子ども(複数いれば等分):1/2
例:配偶者+子2人 → 配偶者1/2、子A 1/4、子B 1/4
➤ ② 配偶者と直系尊属(親・祖父母)がいる場合
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3(複数いれば等分)
➤ ③ 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いれば等分)
➤ ④ 配偶者のみが相続人でない場合(配偶者がいない)
- 子ども、親、兄弟姉妹が順に相続人になります(※同時に相続することはありません)
補足事項
- 配偶者は常に相続人になります(法定相続分は状況により変動)。
- 養子も実子と同じく相続人になります。
- 内縁の配偶者(婚姻届を出していない事実婚)は法定相続人ではないため、相続権はありません(→遺言が必要)。
ここを抑える!民法 第901条について
次に民法第901条についてです。
ここでは代襲相続における相続分について触れています。
代襲相続についてのワードの確認は以下の通りです。
代襲相続とは?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(=被代襲者)が、
- 被相続人より先に亡くなっていた場合や、
- 相続欠格(※犯罪などで相続権を失う)や廃除(※遺留分を奪われる)により相続権を失った場合に、
その人の子や孫(直系卑属)**が代わりに相続する制度です。
この条文は、「代襲相続が起きたときの相続分をどう計算するか」について定めています。
基本的に代襲したら、本来相続人が得ていたはずの相続分を代襲相続人が取得することになります。
ここを抑える!民法 第903条について
最後に民法第903条です。
これは基本に入れるかどうか迷いましたが、知っていただきたいので基本原則に入れました。
相続において生前に贈与を受けた場合は相続分が減る仕組みになっています。
ワードの確認と具体例は以下の通りです。
特別受益とは?
被相続人(亡くなった人)が、相続人の一部に対して、
- 婚姻資金
- 住宅購入資金
- 事業資金
- 生前贈与
- 遺贈(遺言による財産の贈与)
などを与えていた場合、それは遺産の“前渡し”とみなすという考え方です。
このような特別な利益を受けた相続人がいる場合には、他の相続人との公平性を保つために、調整が必要です。
● 実際の計算方法(遺産への「持戻し」)
- 遺産総額に特別受益を加えた「みなし相続財産」を算出
- その全体から相続分を計算
- 特別受益を受けた人は、すでにもらった分を引いて相続分を調整
●具体例
- 被相続人の遺産:4,000万円
- 子が2人(AとB)
- Bは生前に1,000万円の住宅資金を援助されていた(=特別受益)
➤ みなし相続財産
→ 4,000万円(遺産)+1,000万円(特別受益)=5,000万円
➤ 相続分
→ A・Bは法定相続分1/2ずつ
→ 各2,500万円ずつが目安➤ 実際の配分
- Bはすでに1,000万円受け取っているので、残り1,500万円を相続
- Aは2,500万円を相続
このようにして、特別受益を考慮して公平に分けます。
⚠️ ただし書き:被相続人が「特別受益としない」と明示した場合
もし被相続人が、「これは特別受益ではなく、単なるプレゼントや支援だよ」と意思表示していた場合には、その分を相続分の計算に含めないことができます。
→ 遺言書などに「この贈与は持戻しの対象にしない」と書くことが多いです。
おわりに
基本原則が長すぎて大変恐縮ですが、以上までが基本原則となります。
前編・後編の知識だけでも、全く見えてこなかった相続についてイメージできたかと思います。
行政書士に相談しようにも、何を相談したら良いかわからないという方の原因として、
そもそも相続についてよくわかっていないというものがあるかと思います。
今回の記事で学び、少しでもそうした方のお力になることができましたら幸いです。
当事務所においては相続手続き、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成など、
相続に関するお悩みについて相談窓口となっていますので、ぜひご相談ください。
※その他の関連記事になります