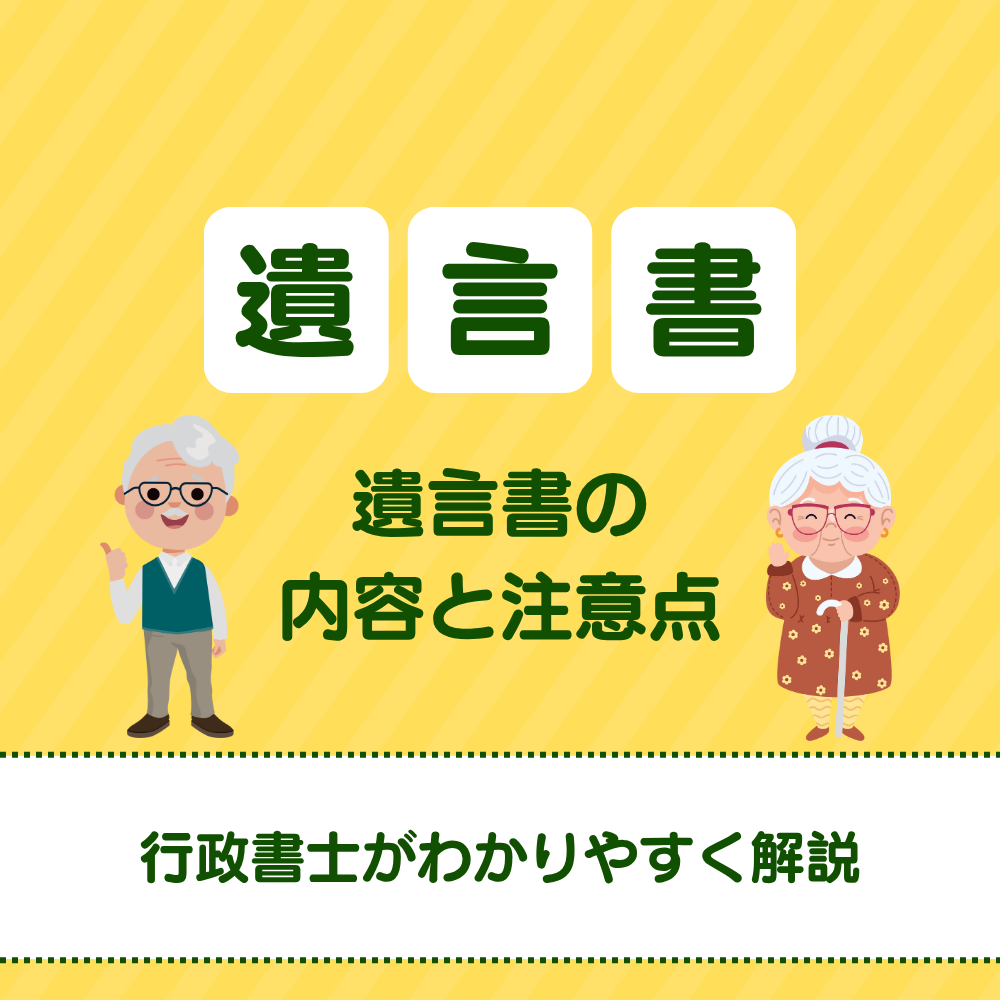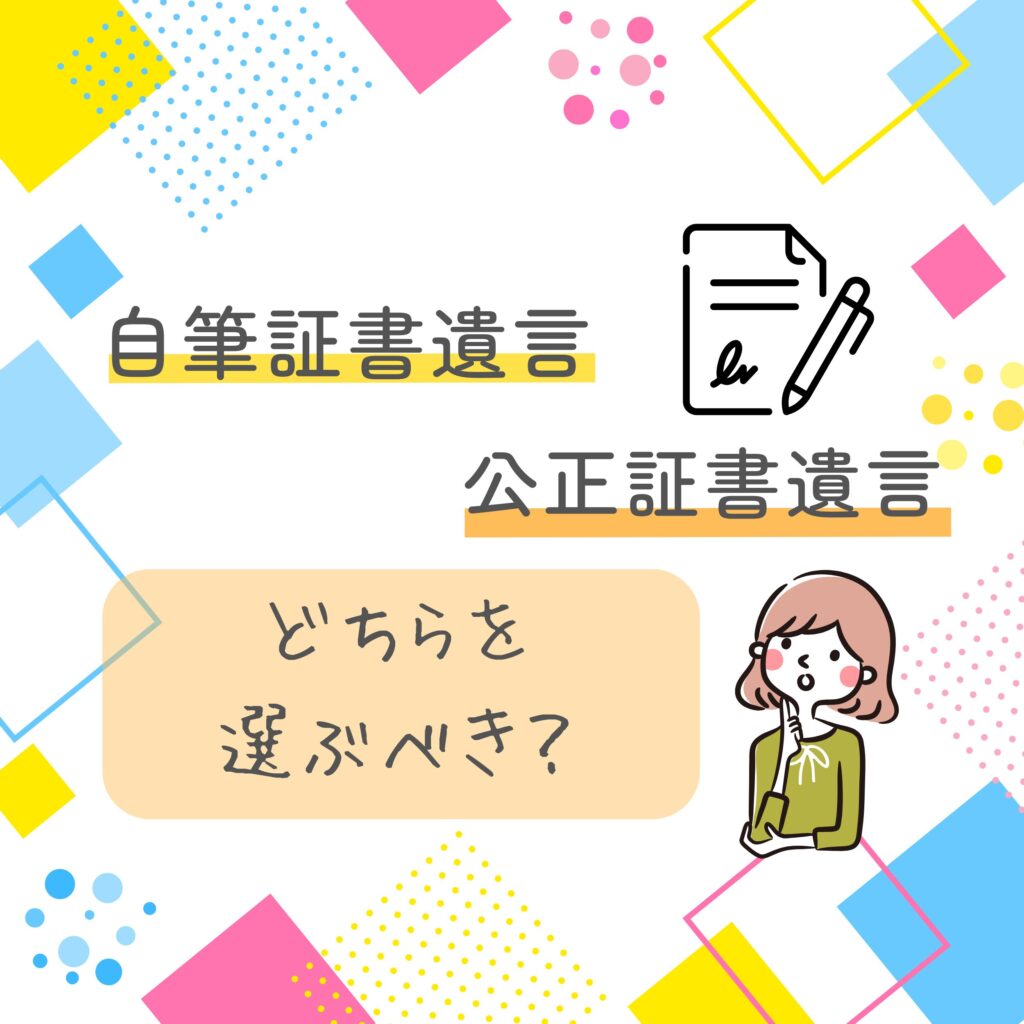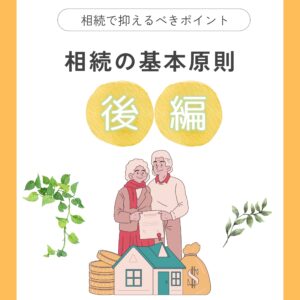法務局に遺言書を預けた話~前編

目次
はじめに
皆さん、法務局の遺言書保管してもらえるのを知ってますでしょうか。
私は制度は知っていましたが利用したことがなかったため、重い腰を上げて申請を行いました...
利用したことが無い方が多いかと思いますので、検討している方の参考になれればと思い記事にしました。
今回のテーマも前編と後編に分けており、
前編は制度の概要と保管するメリットについて、
後編は申請方法について実体験をもとに記事にしました。
制度の概要
まず概要をお話しする前に、前提として遺言書にいくつか種類があることを確認する必要があります。
遺言書は民法で厳格に形式が定められており、
大きく自筆証書遺言(民法第968条)、公正証書遺言 (民法第969条) 、秘密証書遺言民法(第970条) に分かれます。
自筆証書遺言は自分で書く、公正証書遺言は公証役場にいる公証人が作成するという認識だけで大丈夫です。
秘密証書遺言は利用が少ないため、自筆証書遺言か公正証書遺言が主に利用されます。
法務局に保管申請できるのは自筆証書遺言によって作成した遺言のみとなります。
遺言書の書き方などについて関連記事は下記より。
🔹 民法第968条
(遺言の方式)
第968条
- 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、自筆証書に、財産の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。
この場合においては、その目録の各頁に署名し、印を押さなければならない。
民法第969条(公正証書遺言)
第969条(公正証書による遺言)
遺言は、次に掲げる方式により、公正証書によってすることができる。
- 証人二人以上の立会いがあること。
- 遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口授すること。
- 公証人が、その口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか、又は閲覧させること。
- 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した上で、各自これに署名し、印を押すこと。
- 公証人が、その証書を法律に定める方式に従い作成した旨を付記し、これに署名し、印を押すこと。
制度の背景について
法務局に保管ができるようになった背景としては、
自筆証書遺言のデメリットを取り除いて自筆証書遺言の利用を促進するためだと考えられます。
本来の自筆証書遺言と異なる点
では法務局に保管することでどういう点でプラスになるのかを解説します。
こちらについては本来の自筆証書遺言のデメリットを見ていけばだいたいわかります。
まず最大のデメリットは自分で自由に書いてしまったことにより無効となることです。
自筆証書遺言は民法第968条に記載があり,
形式通りでない場合は遺言自体が無効となり、
相続人どうしで遺産分割協議が必要となってしまいます。
専門家に文案を依頼をすれば遺言が無効となることはありませんが、
自分で書いて無効となれば書いた意味がなくなります。
これが一番のデメリットです。
2つ目のデメリットとして、
本来の自筆証書遺言は相続人が遺言書を発見できないという懸念があります。
準備をしっかり行った方であれば事前に相続人に「遺言書の有無と場所」についてお伝えする思いますが、
せっかく書いた遺言が発見できなかったり、紛失している場合は当然ながら遺言の効力を発生することはできません。
3つ目のデメリットは遺言書を発見しても開封できず、
家庭裁判所にて検認手続きが必要なことです。
遺言書を勝手に開封してしまうと5万円の過料(行政罰)に処せられます(民法第1005条)。
上記のデメリットを補うことができるのが法務局に保管申請を行うメリットになります。
1つずつ解説します。
遺言書の方式確認
条文に記載のある通り、
財産目録を除いて自筆証書遺言は「全文自書」、「日付・氏名の記載」、「捺印」の要件があります。
ひとつでも要件が欠けていた場合は無効となります。
そこで保管申請の際に法務局の担当者が内容を確認して形式に沿っているかどうかを確認し、
間違いがあれば指摘してくれますので形式については間違いが起こらなくなります。
しかし注意したいのは遺言の記載内容についての指摘はありません。
例えば遺言書の記載で相続人でない人に財産を渡す場合は「遺贈する」という内容で書きますが、
「相続させる」と書いてしまっていたなど。
あくまで形式の確認になりますので、
保管した遺言書の内容が無効である可能性も十分に考えられます。
このデメリットを防ぐために文案を専門家に指導を受けたうえで作成し、
文案通りに自分で書いていくという作業をしてことをおすすめします。
ちなみに公正証書遺言については、
公証人がヒアリングした内容をもとに公証人が文案を作成しますので、
無効となる可能性はありませんので、
あまりにも神経質になる場合は公正証書遺言に切りえるべきです。
原本は50年間保管と死亡の通知
保管申請をした場合、
原本は遺言者が死亡後50年間は保管してくれます。
さらに遺言者が死亡後、
指定した方に遺言書の保管場所について通知をしてくれる制度がありますので、
通知する方の住所に変更がある場合は変更の届け出が都度必要になりますが、
法務局から指定した方に通知してくれるので相続人が遺言書を発見できないというリスクが無くなります。
※ちなみに遺言の公正証書については原本の保管は遺言者の死亡後50年間となります
検認手続きが不要であること
検認(けんにん)とは家庭裁判所で行われる手続きの一つで、
遺言書が遺言者の最後の意思に基づいたものであることを確認するための手続きです。
具体的には、遺言者が亡くなった後、
遺言書が発見された際にその内容や真偽を確かめるために家庭裁判所で行います。
本来は自筆証書遺言を発見したら相続人は家庭裁判所に「遺言書の検認申立書」を提出します。
しかし法務局に預けた場合は検認手続きは不要となりますので、
余計なストレスがかからず容易に遺言の執行手続きと移行することができます。
申請費用は3,900円!?
申請費用はお財布にやさしく3,900円になります。
費用は申請書に収入印紙という形で貼付しますが事前に準備する必要が無く、
まず必要書類を提出して法務局の担当のから「こちらで受理します」という話がありましたら、
法務局2階(郡山市の法務局の場合)で収入印紙を購入します。
おわりに
以上が主な概要になります。
自筆証書遺言で遺言を作成する場合は上記メリットの恩恵があるため,
法務局に保管することを推奨します。
保管したとしても保管後に新しい遺言を書いた場合、いつでも撤回ができます。
一度預けてみると想定より簡単だったことに気付けるかと思いますので、
気軽に「とりあえず書いて預けてみる」いう動きもアリかと思います。
後編は具体的な申請内容について解説していきたいと思います。