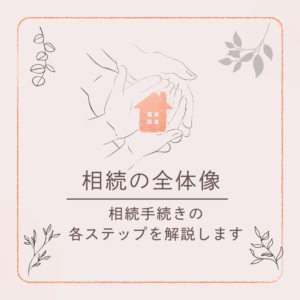農地付き空き家を買うには許可が必要!?農地法の許可申請と調査方法について
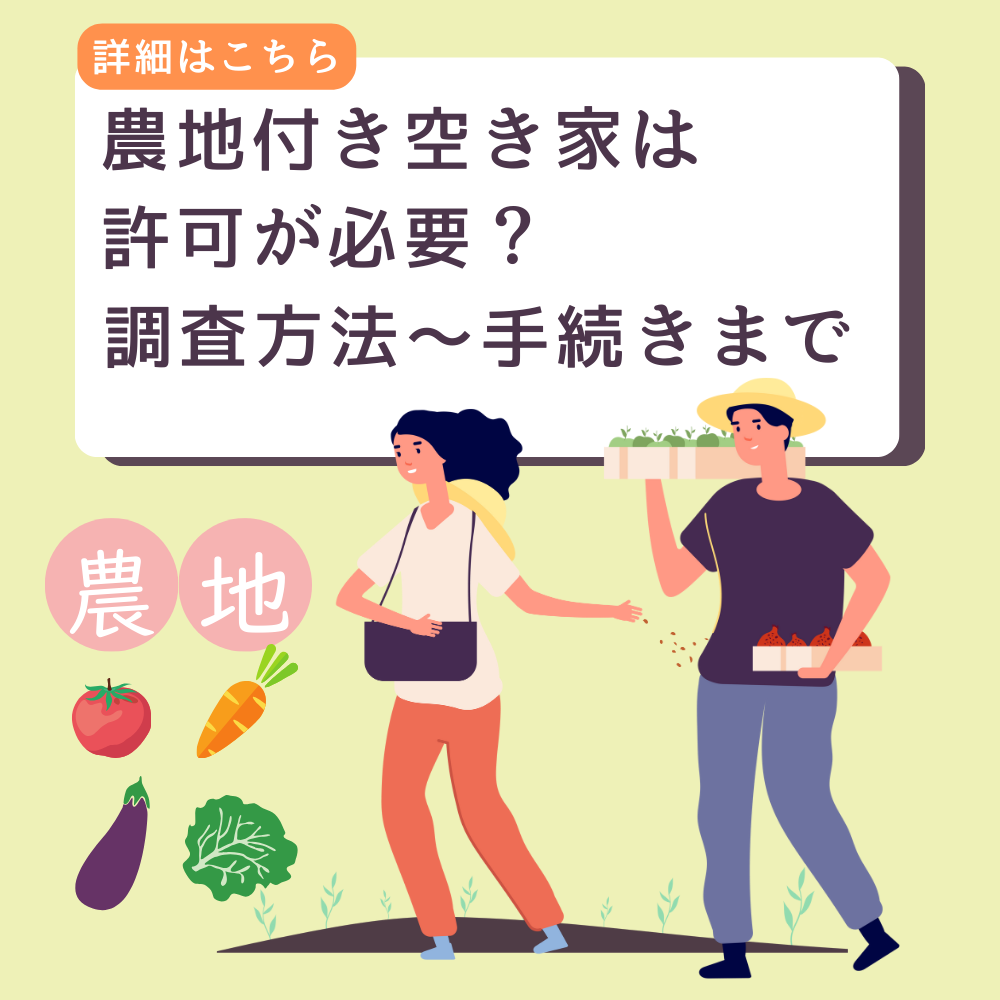
目次
はじめに
移住して農業をはじめたい!と考えたときに、
物件探しが最初の壁となって立ちはだかります。
家と農地は安く買って、安くリフォームして暮らせたら....
そんな淡い夢を持っていると現実は全く違うことが多く、がっかりするかと思います。
本テーマは農地付き空き家の実情と、
素敵な農地付き空き家を購入したい!となった場合の手続きや調査方法について解説します。
これから農業をはじめるのに空き家を探しいる方、
不動産業者で農地付き空き家の取り扱いが不安...という方向けの記事になります。
まず農地とは耕作の目的に供されている土地を指します。
日本では農地の売買や贈与、賃貸といったものに厳格なルールが定められており、
これは主に「農地法」によって規制されています。
登記簿上の地目は「田」や「畑」が農地に該当する可能性が高く、
登記上は宅地でも、実際に耕作していれば「農地法の許可」が必要になるケースがあります。
実務として現況農地として利用している場合は農地法の許可が必要になる可能性が高いです。
場所によっては農地判定にならない土地もあるので、農業委員会に確認が必要になります。
✅ 法律上の定義
農地法第2条第1項
この法律において「農地」とは、耕作の目的に供される土地(作物の栽培、牧草の栽培等)をいう。
農地付き空き家の実情
不動産情報を見ると「農地」の情報はほとんど見当たらないことが多いです。
理由としては、「農地」は土地値が安く、
立地も各不動産会社の事務所から遠く、
買主は「農業経験者」もしくは「これから農業をはじめたい人」に限定されてしまうことがあることから、
積極的に取り扱おうとはしないものです。
しかしこれから農業をはじめたい人にとっては、
情報がない中で農地を探すことに大変苦労することが多いのが実態としてあります。
さらに農地付き空き家に関しては、建物の劣化が進んでおり、
物件購入費用よりリフォーム費用の方が高くなってしまうというようなケースも多々見られます。
リフォームを簡易的にやってから住めるようにすれば大丈夫だろう...
そんな気持ちでいると多額のリフォーム費用をかけないと住めないことわかり、
大変がっかりすることになります。
私が見てきた農地付き空き家は屋根の修繕も必要なところが多いです。
雨漏りの跡のようなシミも見受けられます。
床は一部シロアリに食われてベコベコしているお部屋もあったりします。
また上水道は井戸水であったり、下水も昔ながらの汲み取り式のこともあります。
そうなると屋根修繕、シロアリ対策、水道管の引込費用や浄化槽の設置も必要であり、
建物屋内だけでなく外構工事だけで多額になることも推測できます。
その他農地にかかる「農地法の許認可申請」、中古住宅購入に係る「仲介手数料」も考慮すると、
市街地にあるような中古住宅と比較すると、通常より費用がかかることは、
覚悟しておく必要があります。
農地付き空き家はどのような許可が必要か?
農地付き空き家は農地については「農地法」の許認可申請が必要です。
農地法の許可申請には農地の利用方法によって許可の内容が異なります。
まず農地を農地のまま売買する場合は「農地法3条許可申請」になります。※贈与も同様
農地法第3条許可申請は、農地の所有権・賃借権などの権利移転や設定を行う場合に必要な手続きです。
これは、農地を農地のまま利用する前提で行うもので、転用(宅地化など)は含まれません。
■ 農地法第3条許可とは
根拠法令:
農地法第3条第1項
農地または採草放牧地について、所有権・賃借権などの権利を設定・移転するには、農業委員会の許可が必要。
✅ 3条許可が必要なケース
行為 許可の有無 農地を農業従事者に売る ✅ 必要 農地を農業従事者に貸す(賃貸借・使用貸借) ✅ 必要 農地を農業法人へ譲渡 ✅ 必要(法人要件あり) 相続・遺産分割 ❌ 不要(登記変更のみ) 農地→宅地(転用) ❌ 不可(※第5条許可)
農地を農地以外の利用するために購入する場合は「農地法5条」の許可申請が必要になります。
農地法第5条は「農地を農地以外の用途に転用する場合」に適用される規定で、
農地の売買・賃貸などとあわせて用途を変更する(例:宅地・駐車場・資材置場にする)場合に許可が必要です。
✅ 農地法第5条の概要
□ 根拠条文(農地法第5条第1項)
農地または採草放牧地について、その所有権、地上権、賃借権等を移転・設定し、かつ、その土地を農地以外に転用するには、都道府県知事または農業委員会の許可を受けなければならない。
📌 適用されるケース(典型例)
行為内容 許可必要? 備考 農地を購入し、住宅を建てる ✅ 必要 売買+転用のため 農地を借りて、駐車場にする ✅ 必要 賃貸+転用のため 農地を自己所有のまま住宅地に変える ❌ 第4条に該当 所有権移転なしのため 農地を農地として売る ❌ 第3条に該当 転用なしのため
農業振興地域地区域内の農地について
農業振興地域地区域内の農地とは、
農業振興地域整備法に基づいて市町村が指定した「農業振興地域(農振地域)」の中で、
さらに農業振興を特に図るべき土地として線引きされた農地のことを指します。
農地の中でも「農業振興地域地区域内の農地」は農地転用が原則禁止であるため、
転用をする場合は事前に「農振除外の申し出」を行い、その後に転用許可申請を実施します。
原則転用は禁止であるため、転用するにはそれなりの事情と理由付け及び周辺環境との影響を考慮する必要があり、
田んぼに囲まれた土地を「農振除外の申し出」を行い、農地転用を行うことはできません。
「農振除外の申し出」は郡山市では4月、8月、12月の年3回の締切があり、
申し出後の許可は半年ほど時間がかかりますので、不動産の取引の関係上、
手付契約で農地法の許可申請を停止条件付契約とし、引き渡し時期が翌年というパターンになることが多いです。
停止条件付契約とは民法に定められています。
📖 民法127条(停止条件成就の効力発生時期)
条文:
第127条 停止条件付法律行為は、条件が成就したときからその効力を生ずる。
農地付き空き家の調査方法
最後に農地付き空き家の調査方法について下記内容でまとめました。
全くの初心者の場合、すべてを調査するのが時間も労力もかかりますので、
専門家に依頼することをオススメします。
🔎 農地付き空き家の調査方法
① 物件の基本情報を押さえる
- 所在の確認
→ 番地、地番を特定。
→ 住宅と農地で地番が分かれている場合が多い。
② 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得
- 法務局で地番ごとに取得
- 土地:宅地、田、畑ごとに登記簿を取る。
- 建物:家屋番号を確認して建物登記を取る。
- 内容からわかること
- 所有者(相続登記未了の可能性も多い)
- 抵当権・差押などの権利関係
- 地目(宅地、田、畑など)
③ 公図・地積測量図・航空写真の活用
- 公図(法務局):地番の位置を確認。
- 地積測量図:境界や面積を確認(ない場合も多い)。
- 航空写真(Googleマップや自治体のGIS):現況が農地か荒廃地かを確認。
④ 名寄帳もしくは固定資産税課税台帳の閲覧
- 市町村役場の資産税課で確認。
- 納税通知書が所有者に届いているかどうか。
- 名寄帳を取れば、その所有者が持っている不動産を一括把握可能。
- 相続未登記の場合、納税義務者が「代表相続人」になっていることもある。
⑤ 農地台帳の活用
- 農業委員会の農地台帳:誰が耕作しているか、農地利用の状況がわかる。
- 農振マップや都市計画図:農地が「農振農用地」かどうかを確認。
⑥ 農業委員会調査
- 農地の種類と転用可能かどうかの有無
- 農地法の過去における違反状況(違反が是正されていないと許可申請の受付ができない可能性がある)
⑦ 現地調査
- 農地の周辺状況を確認 ※転用を希望する場合は周辺の農地に影響がないかどうかを確認