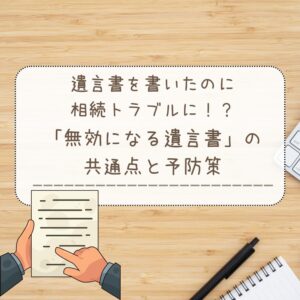相続人がいない人の遺言書対策|「遺贈」で想いを託す

目次
はじめに:相続人がいないと財産はどうなる?
配偶者や子、父母・兄弟姉妹などの相続人がいない場合、
遺言がなければ財産は「相続人不存在」の手続へ進み、最終的には国庫に帰属します。
「大切にしてくれた友人へ」「お世話になった団体へ」「地域の子どもたちのために」
こうした想いは、遺言で「遺贈」を指定しておくことで初めて実現します。
遺贈は「法律で保証された最後の意思表示」。
相続人がいない方こそ、早めの設計が要です。
遺贈でできること/できないこと
個人への遺贈
特定の人物へ金銭や不動産、預貯金、有価証券、貴金属、コレクション等を贈れます。
相続人がいないため、遺留分の争いが生じない点が実務上のメリットです。
法人・団体への遺贈
法人(会社・医療法人・社会福祉法人等)や学校法人、公益法人、
認定NPO、自治体、基金等にも遺贈できます。
社会貢献や顕名(寄附者名の明示)を希望する場合は、
受け手側の受入方針や顕名可否を事前に確認しましょう。
負担付遺贈・条件付遺贈
「墓守をすること」「ペットを終生飼養すること」「奨学金原資として使うこと」等の負担や条件を付けられます
負担の内容が不明確だと実行不能になるため、
履行内容・期限・費用負担・報告方法を具体的に書き込みます。
よくある誤解
- ペットへの直接遺贈は不可。 財産は人または法人へ。ペットを守るには、受遺者を人/法人にし、「終生飼養」「医療・食費の支給方法」等を負担として明記します。
- 包括遺贈と特定遺贈の違い。 すべて(又は一定割合)を渡すのが包括遺贈、物や金額を特定するのが特定遺贈。残余財産条項と併用し、漏れが出ない設計に。
最適な遺言方式と本文設計
自筆証書遺言+保管制度/公正証書遺言
- 公正証書遺言:公証人が関与し方式不備リスクが低い。原本が公証役場で保管され、発見・検認の負担が少ないため、相続人がいないケースと相性◎。
- 自筆証書遺言+法務局保管:費用を抑えやすい。法務局保管で「遺言が見つからない」リスクを低減。財産目録はパソコン作成・通帳コピー添付OKだが、本文は自筆が原則。
付言事項・予備条項・残余財産条項
- 付言事項:なぜその人(団体)に託すのか、使い道の希望、感謝の言葉。法的効力は限定的でも、実務運用の指針になります。
- 予備条項:受遺者が先に亡くなった/受け取り不能な場合の「予備受遺者」を指定。
- 残余財産条項:「上記以外の財産一切は〇〇へ包括して遺贈する」と明記し、漏れや新規財産に対応。
遺言執行者の指定
実行役=遺言執行者を必ず置きましょう。
相続人がいないと利害調整役が不在になりやすく、銀行解約・名義変更・寄附手続・負担付遺贈の履行確認等で強い権限が必要です
。専門職(行政書士・弁護士等)を第1候補、信頼できる個人を第2候補にする二段指定も有効。
ケース別の設計例
例1:友人+母校への遺贈寄附
- 第1条 私の普通預金のうち300万円を、友人A(住所…)に特定遺贈する。
- 第2条 上記以外の一切の財産を、母校〇〇高等学校の奨学金基金(受入窓口:学校法人△△学園)に包括遺贈する。使途は「経済的困難な生徒の学費支援」とする。
- 第3条 予備条項:前条の受遺者が受贈不能の場合、同基金の後継組織に包括遺贈する。
- 第4条 遺言執行者として、行政書士〇〇(事務所所在地…)を指定する。
- 付言事項:学びに助けられた人生でした。次の世代に機会を手渡してください。
例2:介護で世話になった知人への負担付遺贈
- 第1条 私の自宅不動産(所在…)を知人Bに遺贈する。Bは、私の葬儀・納骨・墓地管理(年1回の清掃・献花)を行う負担を負う。費用は本遺贈の範囲で充当する。
- 第2条 上記負担の履行完了後、遺言執行者に報告書(写真・領収書添付)を提出すること。
- 第3条 残余財産は、地域の社会福祉協議会に包括遺贈する。
例3:ペットの終生飼養を条件にした設計
- 第1条 私の預貯金のうち500万円を、知人Cに負担付遺贈する。負担は、愛犬Dの終生飼養(食費・医療費・散歩等)であり、飼養不能の場合は動物保護団体Eへ委託する。
- 第2条 遺言執行者は年1回、飼養状況の報告を受け、必要に応じ監督・費用支出を承認する。
- 第3条 残余財産条項…(同上)
税務と手続きの注意点(要点だけ)
・受遺者が個人の場合は、原則として相続税の対象。
・受遺者が法人・団体の場合は法人税の扱い。
公益法人や認定NPO等は非課税・軽減の特例がある場合あり。実際の課税関係や評価は税理士と連携して確認。
・不動産は登録免許税・不動産取得税の検討が必要。
負担付遺贈では対価性の判断が絡むため、実務での設計と説明資料を整備。
・受け手側の受入規程・顕名可否・使途制限・寄附手続の所要書類は事前照会しておくとスムーズ。
行政書士に依頼するメリットと進め方
メリット
- 財産・想い・受け手の規程を踏まえた文言最適化(負担・条件の具体化、残余条項、予備条項)
- 遺言執行者受任により、銀行解約・寄附実行・報告取得をワンストップで代行
- 団体との事前調整(顕名/匿名、使途指定、記念銘板の可否 等)
- 税理士・司法書士・不動産業者と専門連携(評価・名義変更・換価等)
相談の流れ
①初回面談(想いのヒアリング・受遺候補の選定)
②財産棚卸(預貯金・有価証券・不動産・デジタル資産)
③設計案提示(負担・条件・予備条項・残余条項)
④公証役場での公正証書遺言作成 or 自筆+保管手続
⑤受け手側の受入確認書(任意)/実行時の運用ファイル整備
よくある質問
Q1. 相続人がいないと、財産は必ず国に没収されてしまうのですか?
はい、最終的には「国庫帰属」となります。
民法第959条では、相続人がいない場合、
家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」が債務弁済などを行い、
それでも残余財産があれば国庫に帰属すると定められています。
つまり、遺言書で「遺贈先」を指定していなければ、
どんなに想いがあっても自動的に国に行ってしまうのです。
これを防ぐには、遺言で受遺者(人・団体)を明示することが唯一の方法です。
Q2. 少額でも遺贈や寄附をする意味はありますか?
あります。
金額の大小よりも、「意思を明確にしておく」こと自体に大きな価値があります。
例えば、10万円程度の遺贈寄附でも感謝状や活動報告を送ってくれる団体は多く
あなたの名前が次の世代に残るケースもあります。
また、遺贈先を複数に分けることも可能です。
たとえば「Aさんに50万円」「郡山市の動物保護団体に20万円」と指定できます。
少額でも「誰に、何のために」を明確に書くことが大切です。
Q3. 遺贈したい団体がまだ決まっていません。どうすればいいですか?
団体が未定でも構いません。
現段階では「目的ベース」で遺言を作り、
「受遺先は将来指定する」としておく方法があります。
または、行政書士を遺言執行者に指定し、
将来、あなたの意思を確認しながら最適な団体を選定する「付託型遺言」を作ることも可能です。
遺贈先は、たとえば以下のような分類で整理すると見つけやすくなります:
- 医療・福祉系(赤十字、社会福祉法人など)
- 教育系(母校・奨学金財団)
- 地域貢献(自治体基金・社会福祉協議会)
- 動物保護・環境保全系(NPO・財団)
Q4. ペットを守るために遺言でお金を残せますか?
ペットは「法律上の人」ではないため、直接お金を渡すことはできません。
ただし、負担付遺贈の形で
「○○さんに500万円を遺贈する。ただし愛犬△△の終生飼養を負担とする」と記載すれば、法的に有効です。
また、動物保護団体に寄附して終生飼養を委託する方法や、
ペット信託制度(信託銀行・士業連携)を利用する方法もあります。
行政書士に相談すれば、あなたのペットの年齢・健康状態・飼養費用を踏まえた現実的な設計が可能です。
Q5. 遺言書は一度作れば一生有効ですか?
形式的には有効ですが、実務的には定期的な見直しが必須です。
財産内容や受遺者の状況が変われば、遺言内容が現実に合わなくなります。
たとえば受遺者が先に亡くなった、団体が解散した、財産を売却した、などのケース。
目安として3~5年ごと、または次のようなタイミングで更新するのが理想です。
- 不動産を売却・購入した
- 新しい預金・証券口座を開いた
- 受遺者の事情が変わった(離婚・死亡など)
- 自身の健康や価値観に変化があった
Q6. 遺言を作るのは何歳くらいが適切ですか?
法律上は「15歳以上」であれば有効ですが、
現実には判断能力が十分あるうちに作成することが大切です。
高齢で作ると、「意思能力がなかった」と主張されて無効になるリスクがあります。
60代前後での初回作成+10年ごとの見直しが理想的です。
体調を崩す前、または施設入居・介護契約を考え始めた段階が最適タイミングです。
Q7. 遺言書を家に保管しておくのは危険ですか?
はい。自宅保管は「紛失」「破棄」「発見遅れ」のリスクがあります。
相続人がいない場合、発見者が誰もいないことも想定されるため、
法務局の自筆証書遺言保管制度または公正証書遺言を利用するのが確実です。
特に公正証書遺言なら、公証役場に原本が保管され、
全国の公証人連合会データベースで検索できます。
遺言執行者を同時に指定すれば、
あなたの死後すぐに内容が実行される仕組みが整います。
Q8. 遺言執行者は誰を選ぶべきですか?
最も重要な役割です。
相続人がいないケースでは、財産を実際に動かす権限者がいないため、
遺言執行者の指定がなければ遺言が「絵に描いた餅」になります。
おすすめは、
- 専門職(行政書士・弁護士・司法書士)
- 「信頼できる友人+専門職」の共同指定の2段構え。
実行力・公正性・継続性を担保できます。
まとめ:意思を「仕組み」に変える
相続人がいない場合、遺言がなければ財産は国庫へ。
遺贈は、あなたの想いを人・団体・地域に確実にバトンパスする仕組みです。
方式選択(公正証書◎)、遺言執行者の指定、負担・条件の具体化、残余・予備条項の整備
——この4点を押さえれば、実行力の高い遺言が完成します。
迷ったら、まずは想いを書き出すことからはじめましょう。