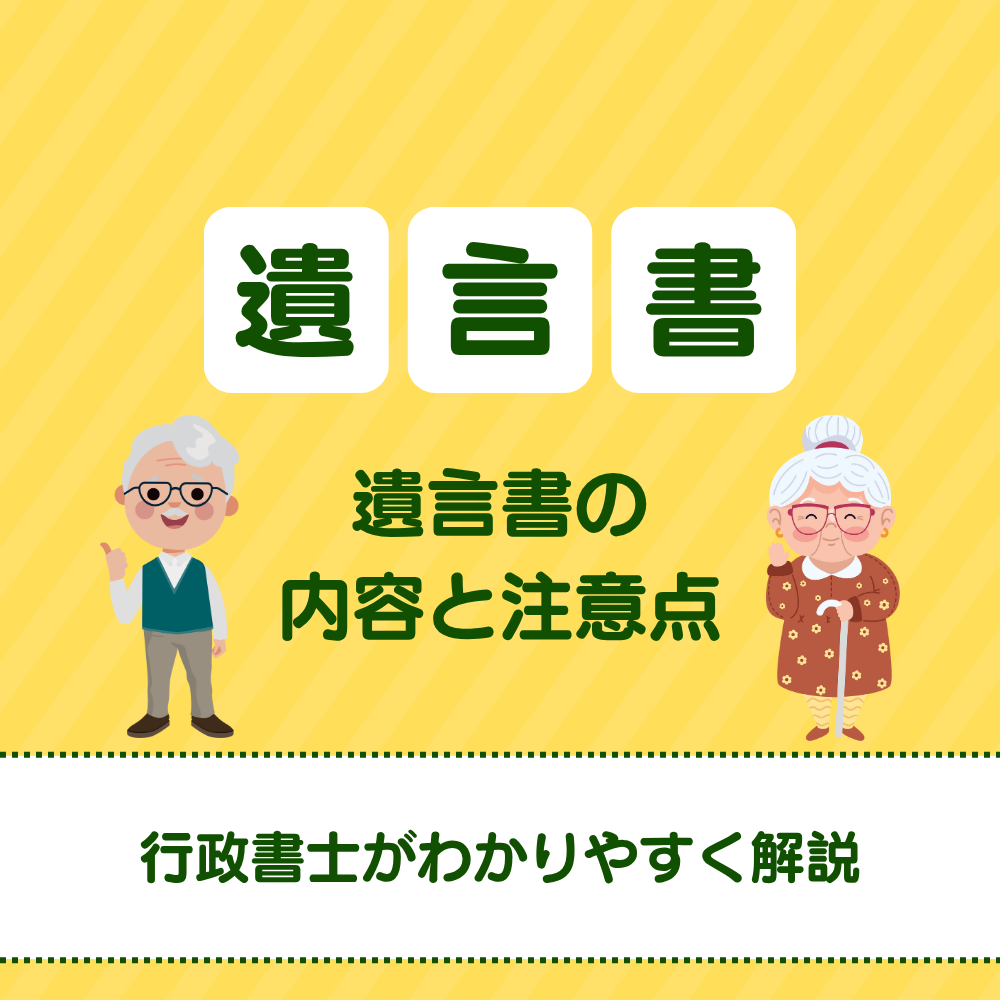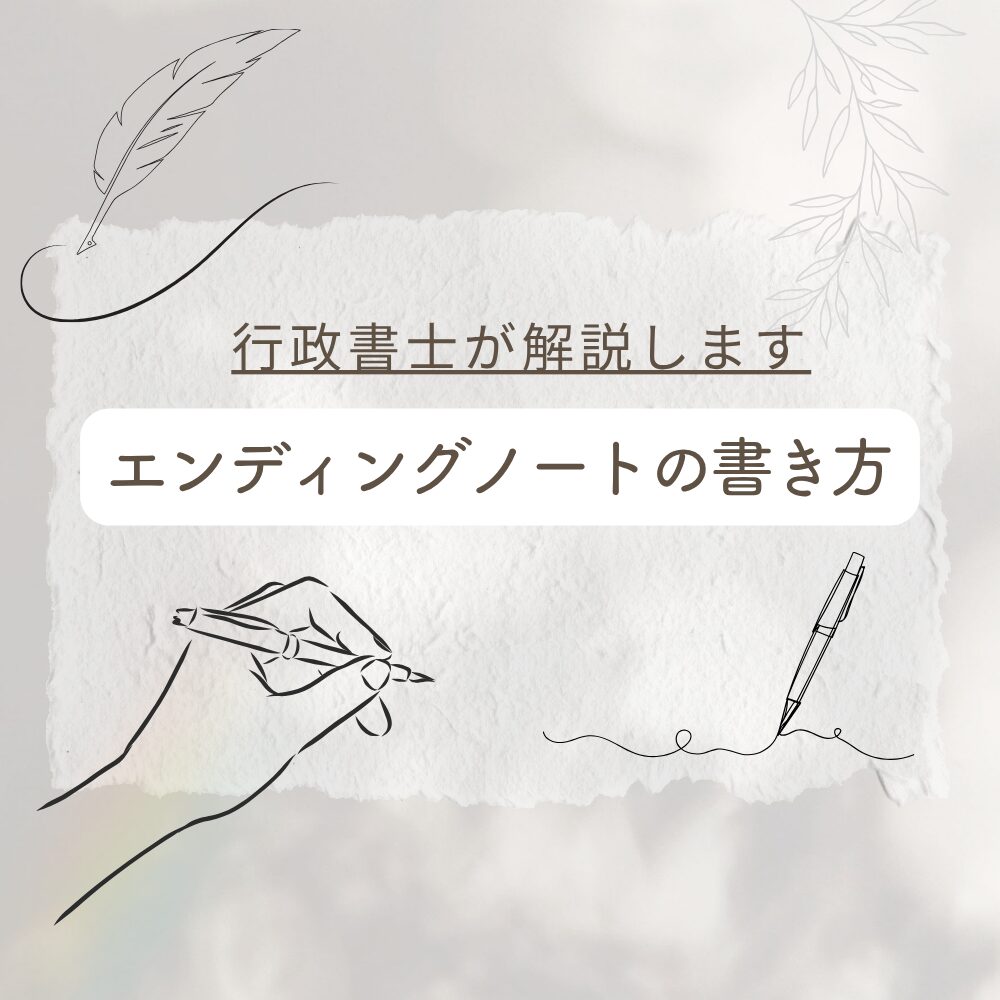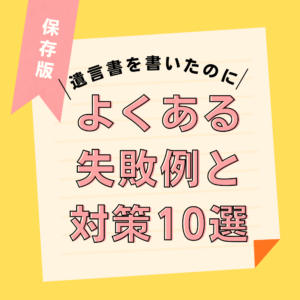任意後見契約書の文例と作成のポイント~自分の将来を守るために知っておきたい実務知識~
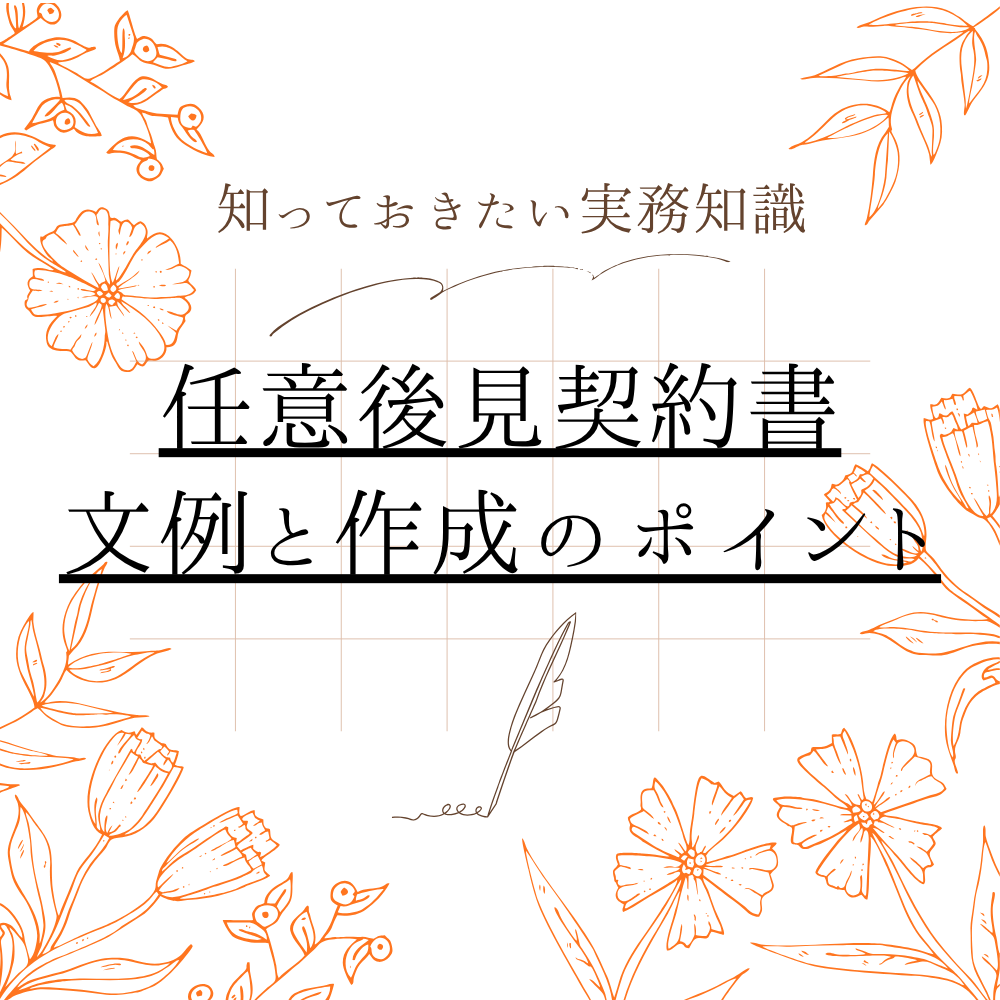
目次
はじめに:老後の安心は「契約書の内容」で決まる
近年、おひとりさまの高齢者増加に伴い、
「任意後見契約書を作りたい」という相談が増えることが予想されます。
しかし、いざ作ろうとすると
「どんな内容を書けばいいのか」
「どこまで任せてよいのか」がわからず、悩む方が多いのも事実です。
任意後見契約書は、
将来の自分の生活・財産をどう守るかを決める最重要書類です。
内容次第で、老後の安心度が大きく変わります。
この記事では、
任意後見契約書の文例(ひな形)と作成のポイントをわかりやすく解説します。
任意後見契約書とは?
任意後見契約書とは、
本人が判断能力を失う前に、
信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援を委ねる契約を定めた書面です。
契約は公正証書で作成し、
後見が開始されるのは家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点です。
つまり、
- 「契約=将来への準備」
- 「発効=実際に判断能力が低下したとき」
という2段階の仕組みになっています。
任意後見契約書の基本構成
任意後見契約書には、大まかな内容としては次のような条項を設けます。
| 条項名 | 内容の概要 |
|---|---|
| 第1条 契約の目的 | 任意後見契約を締結する目的を明記 |
| 第2条 後見人の指定 | 誰を任意後見人とするかを定める |
| 第3条 後見の開始 | 効力が発生する条件(家庭裁判所の監督人選任) |
| 第4条 委任事務の範囲 | 財産管理・身上監護などの範囲 |
| 第5条 報酬・費用 | 任意後見人への報酬規定 |
| 第6条 契約の変更・解除 | 双方の合意や事情変更に備えた規定 |
| 第7条 紛争解決方法(任意) | 管轄裁判所などの定め |
これらの条項を、
本人の希望や家族構成に応じて設計することがポイントです。
任意後見契約書の内容について(ひな形)
以下は一般的な文例です。
※実際に使用する場合は、個別事情に応じた修正が必要です。
任意後見契約書(文例)
第1条(契約の目的)
甲(本人)は、将来判断能力が不十分となった場合に備え、乙(任意後見人)に対し、
自己の生活、療養看護および財産管理に関する事務を行わせることを目的として、本契約を締結する。
第2条(任意後見人の指定)
甲は、乙を任意後見人とし、乙はこれを承諾した。
第3条(任意後見の開始)
本契約は、甲の判断能力が不十分になり、
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力を生ずる。
第4条(事務の範囲)
- 財産管理に関する事務
① 預貯金の管理・解約・振替等
② 不動産の管理、修繕、賃貸借契約の締結
③ 年金・保険・公共料金等の支払い・受領 - 身上監護に関する事務
① 医療機関への入院手続き
② 介護サービス契約および施設入所契約の締結
③ 日常生活の支援および福祉機関との連絡調整
第5条(報酬・費用)
乙の業務に対する報酬は、甲の財産から支払うものとし、金額は月額○円とする。
第6条(契約の変更・解除)
甲または乙が契約内容の変更または解除を希望する場合は、双方の合意により行うものとする。
第7条(紛争解決)
本契約に関して紛争が生じた場合は、
郡山市を管轄する家庭裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
このように、文例を参考にしながらも、
実際は「生活の実態」や「家族構成」に合わせて、
カスタマイズすることが重要です。
任意後見契約書を作成する際のポイント
① 「誰に任せるか」を慎重に選ぶ
任意後見人は、あなたの生活や財産を長期間にわたって支える存在です。
家族、行政書士、信託会社など候補はさまざまですが、
最も大切なのは「信頼」と「継続性」です。
一人暮らしの場合は、
行政書士や専門職後見人を選ぶケースも増えています。
② 委任範囲を具体的に記載する
任意後見契約では、
後見人が行う業務の範囲を契約書に明記しなければなりません。
たとえば、
- 財産管理(預金・不動産・保険)
- 医療・介護契約の締結
- 郵便物の受取・住民票の手続き
など、どこまで任せたいかを具体的に決めておくことが重要です。
③ 「見守り契約」「財産管理契約」と併用する
任意後見契約は「将来発動型」のため、
元気なうちは効力がありません。
そのため、契約と同時に「見守り契約」
「財産管理委任契約」を締結しておくのがベストです。
これにより、
- 判断能力があるうちは「見守り契約」で支援
- 判断能力が低下したら「任意後見契約」が発動
という切れ目のないサポート体制を築くことができます。
④ 公正証書で作成する必要がある
任意後見契約は公正証書でなければ効力がないと定められています。
行政書士が文案を作成し、
公証役場で正式に契約書を作成する流れです。
公証人手数料もあり費用はかかります。
また費用は契約内容によって変動します。
⑤ 家庭裁判所の監督体制を理解する
任意後見契約が発動すると、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。
監督人は後見人の業務をチェックする立場で、
月1〜2万円ほどの報酬が発生します。
※報酬額は財産額によって異なります
契約段階でこの費用も見込んでおくと安心です。
文例を活かす実践アドバイス
任意後見契約書の文例を使う際は、
以下の3点を意識しましょう。
① 「テンプレートのまま使わない」
ネット上にある文例をそのまま使うと、
内容が抽象的になりがちです。
特に「財産管理の範囲」「医療行為の同意」「報酬設定」などは、個別設計が必要です。
② 「家族の合意形成」を忘れずに
契約は本人の意思で行うものですが、
家族とよく話し合っておくことがトラブル防止につながります。
行政書士が同席して説明を行うことで、家族の理解を得やすくなります。
③ 「他の終活契約」との整合性をチェック
任意後見契約は、
遺言書・死後事務委任契約・エンディングノートと組み合わせることで効果が最大化します。
それぞれの内容が矛盾しないよう、
契約前に全体設計を行うことが理想です。
行政書士に依頼するメリット
任意後見契約は「法的書面」であり、
将来にわたって有効に機能させるためには専門知識が不可欠です。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 本人の希望に沿った条項設計ができる
- 公証人との調整・書類準備を代行
- 財産・生活設計を踏まえた総合的提案が可能
- 見守り契約・死後事務契約など一体的支援
行政書士は「あなたの意思を形にする専門家」です。
とくに福島県郡山市のように高齢化が進む地域では、
地元密着の行政書士による継続支援が求められています。
まとめ:将来への「契約の備え」が安心を生む
任意後見契約書は、将来の自分を守る「人生設計書」と言えます。
内容をしっかり設計し、信頼できる人に任せることで、
「もしもの時」にも安心して生活を続けることができます。
行政書士は、その契約を法的に正しく、
そして安心できる形でサポートします。
もし「どのように作ればいいか分からない」
「家族と話し合うきっかけがほしい」という方は、
一度専門家へ相談してみてください。
早めの準備が、老後の安心を確実なものにします。