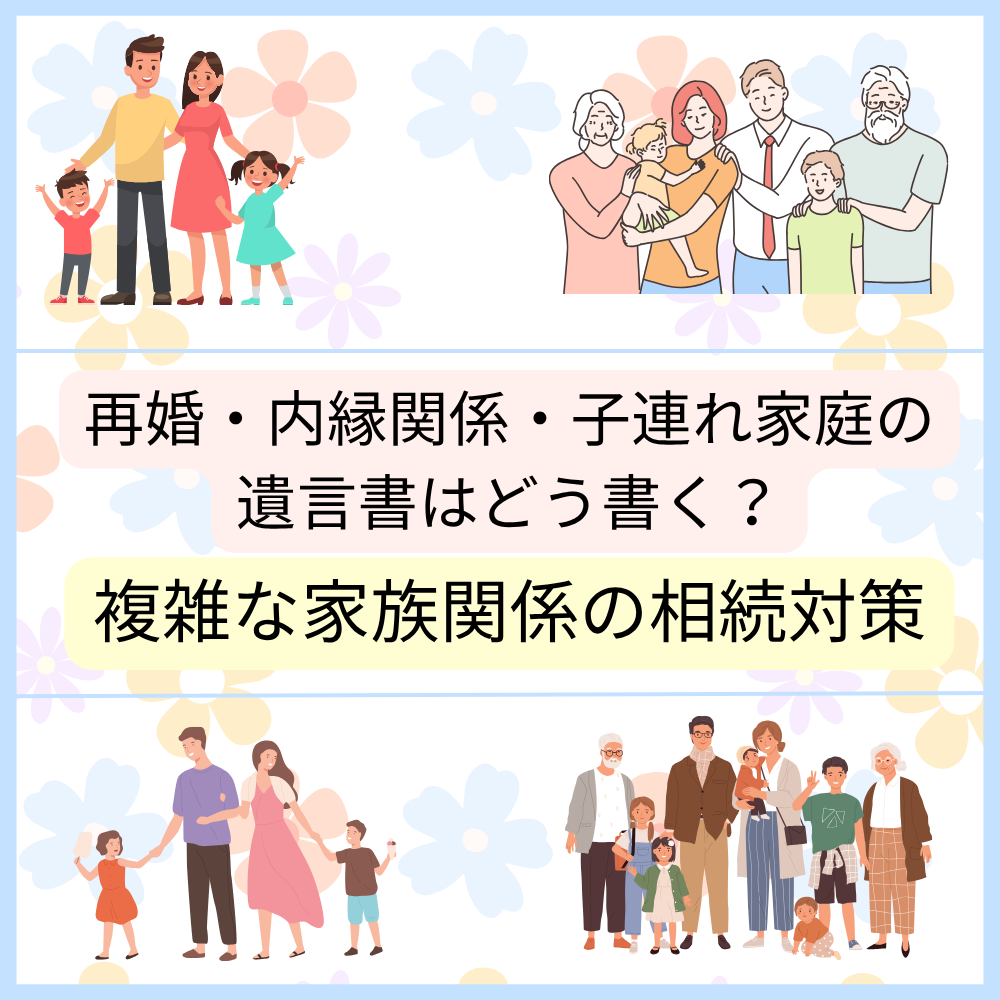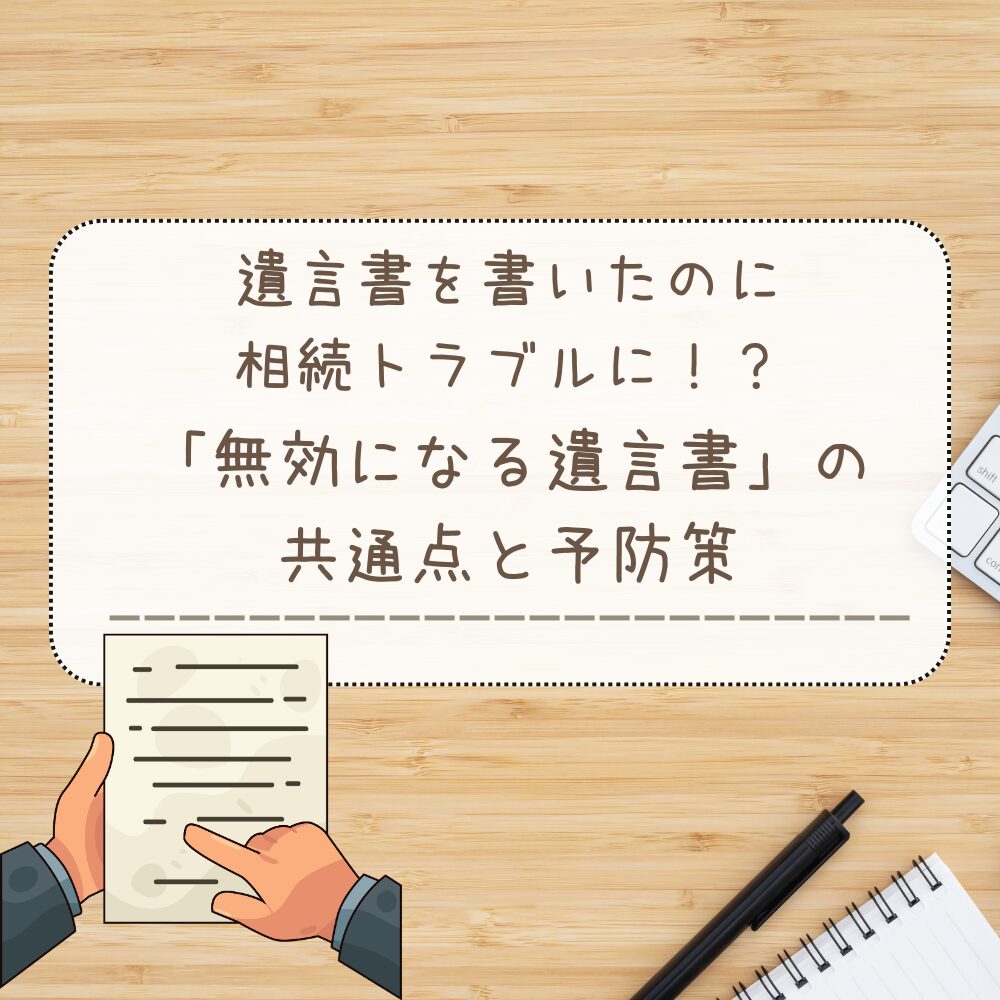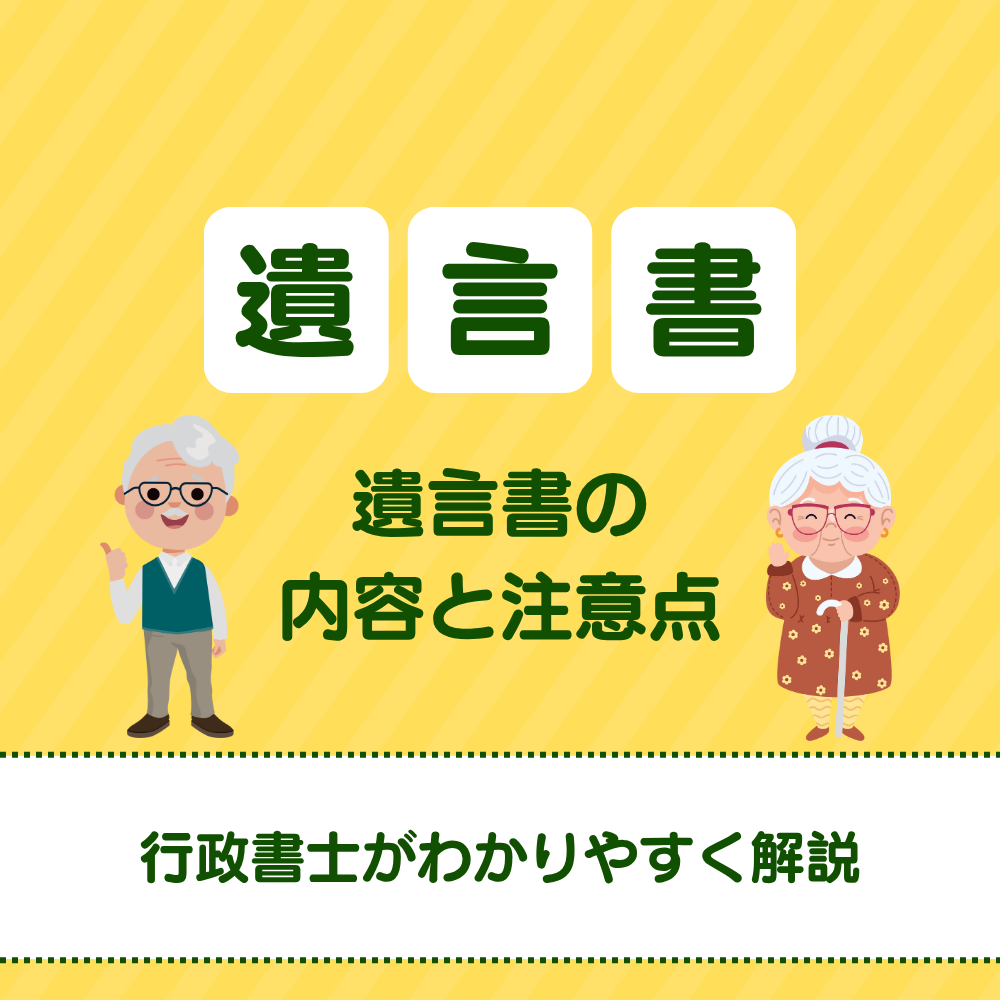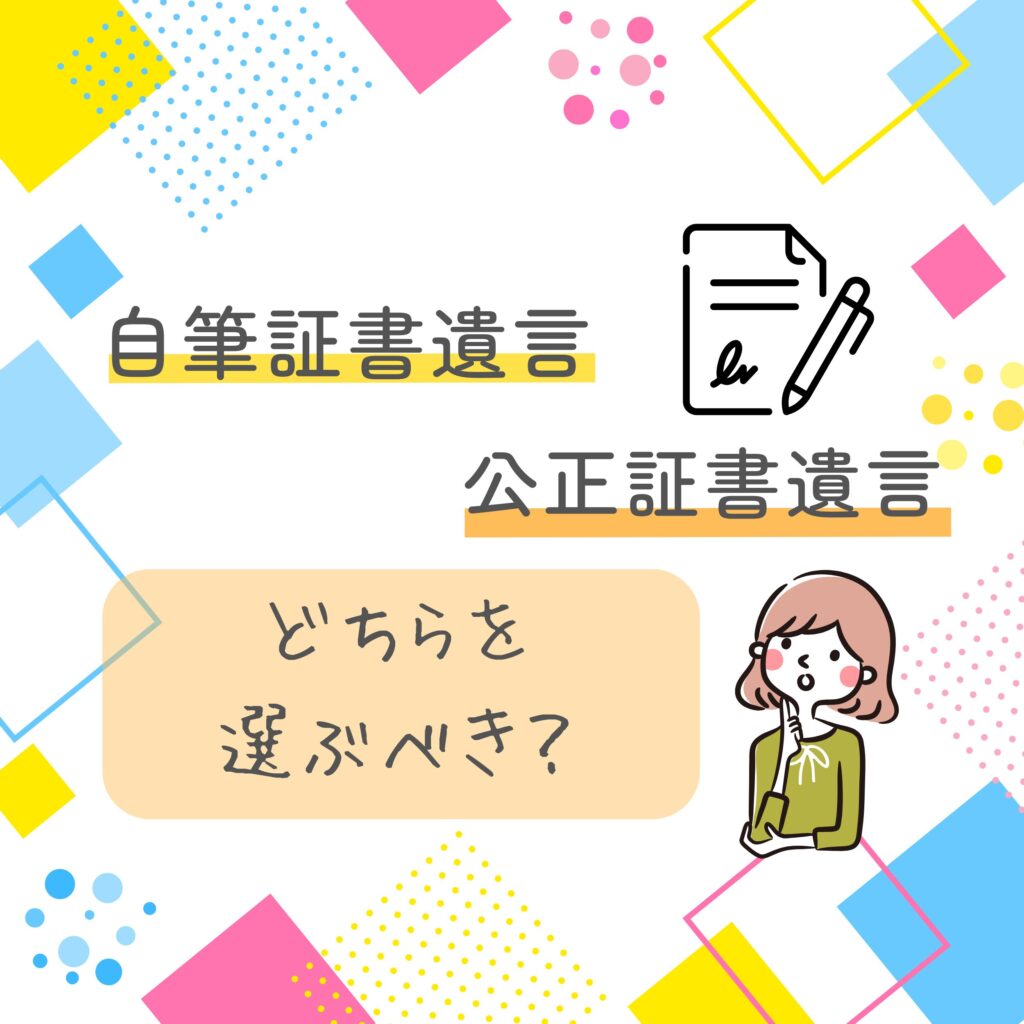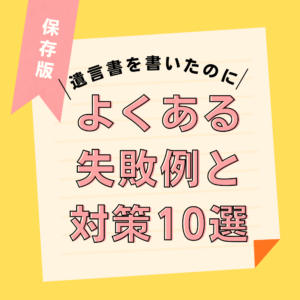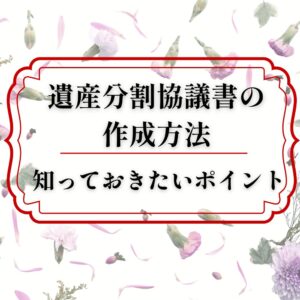遺言書を作るベストタイミングとは?行政書士が解説する「後悔しない準備の始め方」

目次
はじめに
人生100年時代。
相続トラブルや高齢化に伴う認知症リスクが増える中、
「遺言書の準備」が注目されています。
特に、家族構成が複雑な方・不動産を所有している方・子どもがいないご夫婦などは、
早めの対策が重要です。
しかし、
「いつ書けばいいの?」
「まだ早いのでは?」という声も多く聞かれます。
本記事では遺言書を作るベストタイミングについて解説します。
そもそも遺言書とは?
遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかを定める法的文書です。
民法では、本人の意思を尊重するための仕組みとして、いくつかの方式が定められています。
主な種類は次のとおりです。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 手書きで作成 | 費用がかからない | 不備で無効の可能性あり |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 法的に確実・紛失リスクなし | 費用がかかる |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にできる | 公証役場で保管可能 | 実務上あまり使われない |
特に公正証書遺言は、専門家や公証人が関わるため、最も安心できる方法です。
遺言書を作るタイミングを間違えるとどうなる?
多くの方が「まだ元気だから」「財産は少ないから」と遺言を後回しにします。
しかし、遺言の準備が遅れると次のようなリスクがあります。
(1)認知症による判断能力の低下
遺言書は、作成時に判断能力があることが前提です。
認知症が進行してしまうと、遺言書を作ること自体ができなくなり、
後から作ったものが無効とされるケースもあります。
(2)相続人間のトラブル
「うちは仲がいいから大丈夫」という家庭でも、
不動産や預金の分け方をめぐる争いは珍しくありません。
農地や実家の土地を誰が継ぐかという問題で揉めるケースが多いです。
(3)自分の想いが伝わらない
遺言書がなければ、法定相続分に基づいて機械的に分けられます。
「この家は長男に残したい」
「世話になった次女に多く残したい」といった想いが伝わらず、後悔につながることも。
遺言書を作る「ベストタイミング」はいつ?
「迷ったら今がベストタイミング」です。
ただし、ライフイベントごとに明確な目安もあります。
(1)結婚・再婚をしたとき
家族構成が変わる瞬間は、遺言書作成の第一のタイミングです。
特に再婚・内縁関係では、法定相続人が複雑になり、
前婚の子どもと現配偶者の間でトラブルが起こりやすいです。
(2)子どもが独立・家を出たとき
相続人の生活基盤が分かれていく時期。
将来、実家や不動産を誰が引き継ぐかを決めておくと安心です。
(3)不動産や事業を取得・売却したとき
郡山市内でも多いのが、
土地を複数所有している方や小規模事業を営む方。
財産の内容が変わるたびに、遺言書の見直しをおすすめします。
(4)病気・入院・手術の前後
万が一に備える意味で、健康上の不安が出てきたときは作成の好機です。
この時期に作ることで、家族も安心できます。
(5)退職・年金受給の開始時
「現役を引退したら一度整理する」
——これは非常に良い考えです。
老後の資産計画を見直すタイミングで、遺言もセットで準備するのが理想です。
遺言書は「一度作って終わり」ではない
多くの方が誤解していますが、遺言書は何度でも書き直し可能です。
人生の節目ごとに内容を見直すことが大切です。
【見直しの目安】
- 財産を売却・購入したとき
- 相続人(配偶者・子など)が亡くなったとき
- 介護や扶養の状況が変わったとき
- 法改正があったとき(例:2020年以降の自筆証書遺言保管制度)
郡山市では、遺言書保管制度を利用し、法務局で安全に保管しておく方も増えています。
遺言書を早めに作るメリット
- 家族の不安を減らせる
生前から想いを伝えることで、相続時のトラブルを未然に防げます。- 認知症などのリスクに備えられる
判断能力があるうちに作ることで、法的に有効な遺言を残せます。- 付言事項で“心のメッセージ”を残せる
「ありがとう」「感謝しています」など、家族への思いも遺せます。- 行政書士によるチェックで安心
専門家が関与することで、無効リスクを防ぎ、保管・証人手続きまで一括サポート可能です。
「公正証書遺言+尊厳死宣言」
最近は、単なる財産分配にとどまらず、
「人生の最期をどう迎えるか」まで意思表示する方が増えています。
「尊厳死宣言公正証書」や「延命治療に関する意思表示」などを遺言書と合わせて作成する方も多いです。
これはまさに、終活の総まとめとしての生前の自己決定。
郡山市では、地元の行政書士が公証役場と連携し、
「遺言書+尊厳死宣言」を同時にサポートする事例も増えています。
遺言書を作るときに行政書士に相談すべき理由
- 法律に沿った有効な文面を作れる
- 相続人関係を整理し、トラブル防止できる
- 公証人や法務局との連携もスムーズ
- 相続手続きや農地・不動産の名義変更まで一貫対応
行政書士は、「想いを形にする法務の専門家」です。
特に郡山市など地方では、不動産の関係が複雑なため、
実務経験豊富な行政書士への相談が欠かせません。
まとめ:遺言書を作るベストタイミングは「思い立った今」
人生のどの段階でも、「まだ早い」はありません。
むしろ、「遺言書を考えたときが、作るべきとき」です。
将来の安心のために、まずは行政書士に相談してみましょう。
手続きだけでなく、あなたの想いを法律という形にして家族へ託すサポートをいたします。
※遺言書に関する記事は下記よりご覧いただけます。