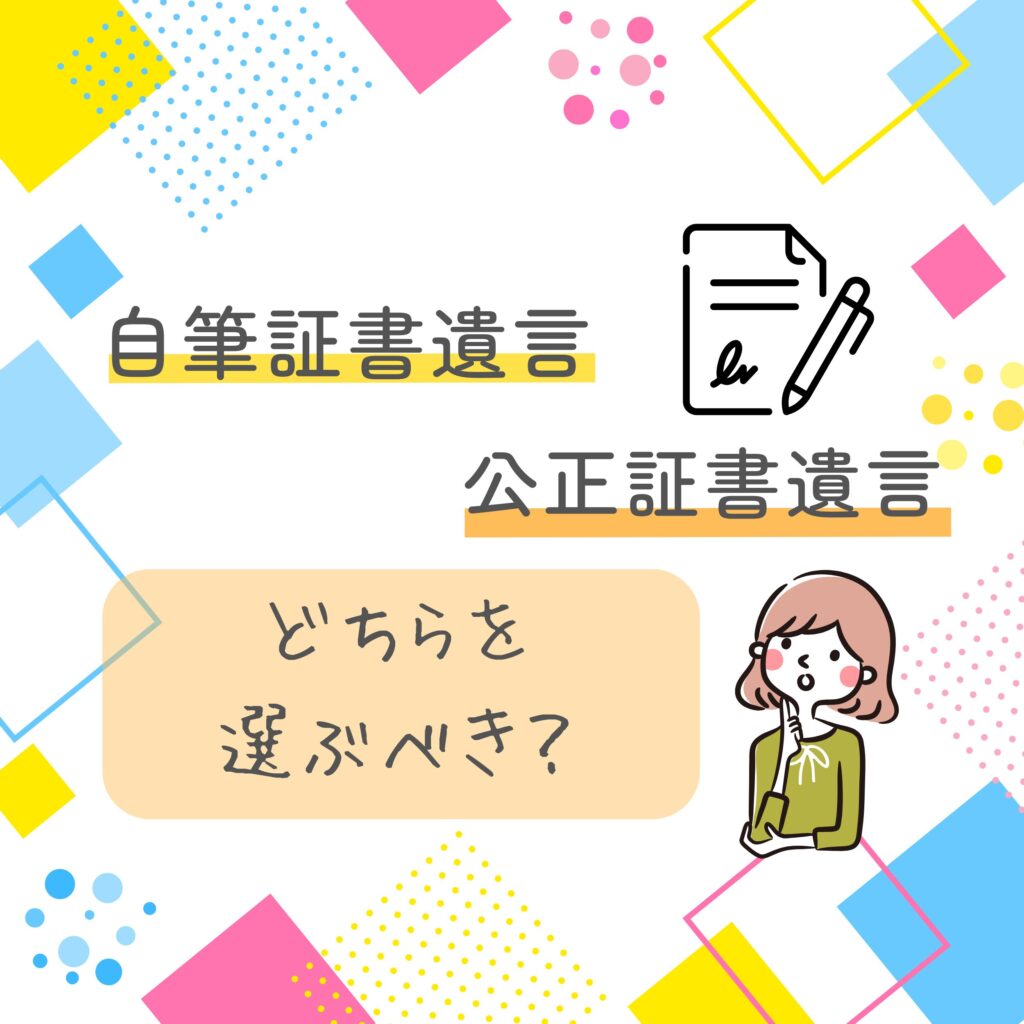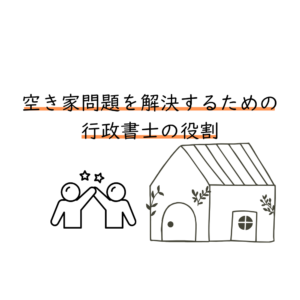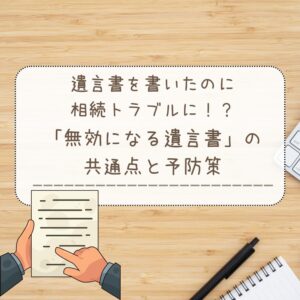遺言書には何を書く?行政書士がわかりやすく解説する遺言書の内容と注意点
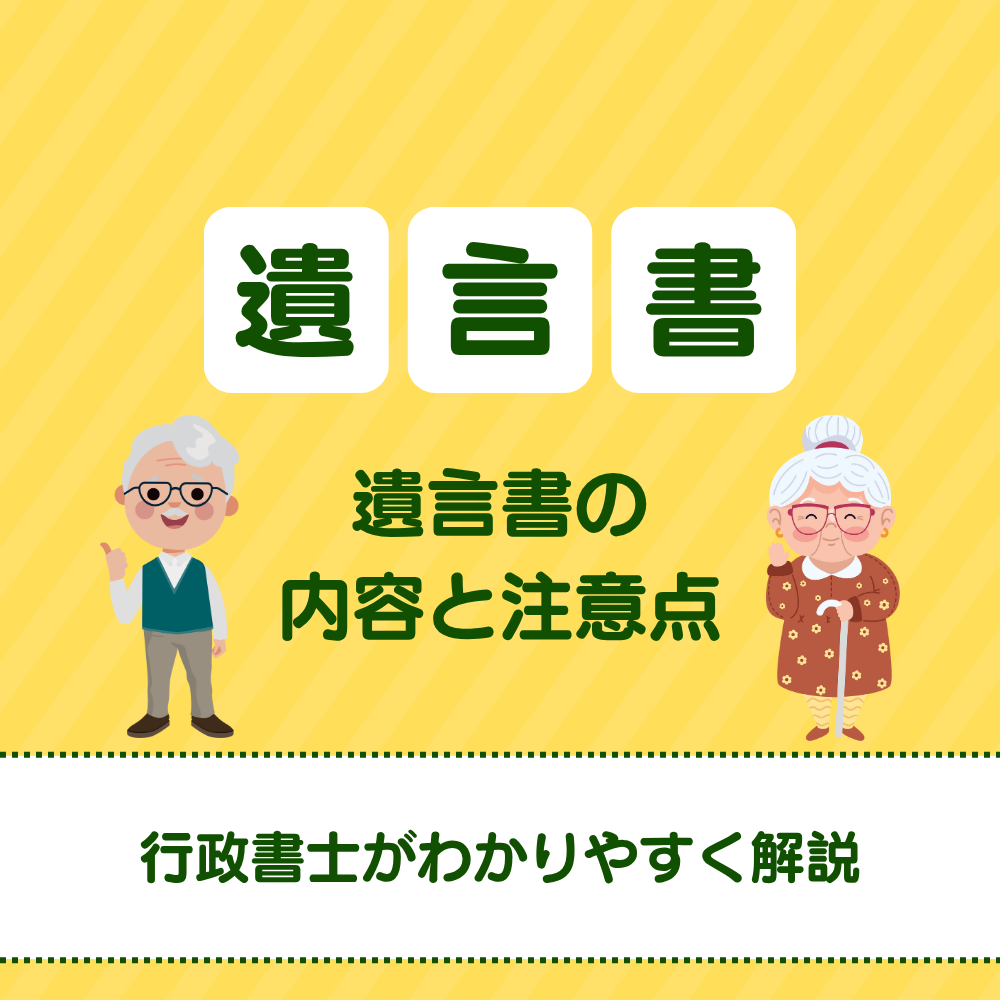
目次
はじめに
相続のトラブルを防ぐために、近年では遺言書を作成する方が増えています。
しかし、
「遺言書には何を書けばいいのか分からない」
「財産以外のことも書けるの?」という質問をよく受けます。
本記事では、行政書士の立場から「遺言書に書ける内容」と「書いてはいけない内容」、
そして実際に遺言書を作成する際のポイントを解説します。
まずはじめに公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが正解かというと、
私は公正証書遺言をおすすめしています。
理由は下記より詳しく解説しています。
遺言書に書ける内容とは?
遺言書は、「法律行為の意思表示」です。
つまり、単なる希望やメッセージではなく、法的な効力を持つ最終意思の宣言です。
そのため書ける内容には一定のルールがあり、法律的に無効となる場合、
遺言書の効力自体が無効となります。
大きく分けて以下のようなものが認められています。
① 財産の分け方(遺産分割の指定)
もっとも重要なのが、誰にどの財産を相続させるかという部分です。
これを「遺産分割の指定」と呼びます。
たとえば次のように書くことができます。
- 長男〇〇に郡山市〇〇町の土地建物を相続させる
- 次男〇〇に預金口座(〇〇銀行〇〇支店)全額を相続させる
- 妻〇〇に私の所有する自家用車を相続させる
このように、財産ごとに具体的に指定することがポイントです。
「長男に不動産、次男に預金」などと明記することで、相続人間の争いを防ぐことができます。
② 遺言執行者の指定
遺言書の内容を実際に実行するための代表者を「遺言執行者」といいます。
たとえば、遺言書で「不動産を長男に相続させる」と書いてあっても、
相続登記などの手続きは誰かが行わなければなりません。
その役割を担うのが遺言執行者です。
行政書士・司法書士・弁護士などの専門家を指定しておくことで、相続人の手間を大きく減らすことができます。
実際、専門家が入ることで、手続きのスピードや正確性が格段に上がります。
③ 特定の人への遺贈(相続人以外への贈与)
相続人ではない人にも財産を渡したい場合、
「遺贈」という形で遺言書に書くことができます。
たとえば以下のようなケースです。
- 長年介護してくれた甥に〇〇万円を遺贈する
- 生前支援してくれた友人〇〇に土地の一部を遺贈する
- 社会福祉法人〇〇会に寄付金を遺贈する
このような「感謝の気持ち」を形にできるのも遺言書の魅力です。
ただし、相続人の「遺留分(法律で保障された最低限の取り分)」を侵害しないよう注意が必要です。
遺留分の記事は下記より解説しています。
④ 相続分の指定・変更
相続人全員に対して「どの割合で相続させるか」を指定することも可能です。
民法では法定相続分が決まっていますが、遺言によって変更できます。
たとえば、
「妻に全財産の3分の2、長男に3分の1を相続させる」
と指定すれば、法定相続分(妻1/2・子1/2)とは異なる割合にすることができます。
⑤ 相続人の廃除・取消し
特定の相続人に対して「相続させたくない」という場合は、「廃除」を定めることも可能です。
ただし、単なる不仲では認められず、「虐待・重大な侮辱・著しい非行」など、正当な理由が必要です。
また、廃除を取り消す(許す)ことも遺言で行えます。
この場合は家庭裁判所の手続きも関わるため専門家に相談するのが安心です。
⑥ 未成年後見人・後見監督人の指定
未成年の子がいる場合、親が亡くなった後に誰がその子を保護・監督するかを遺言で指定できます。
これを「未成年後見人の指定」と言います。
信頼できる親族や知人を指定しておくことで、子どもの生活を守ることができます。
同時に、後見人の行動を監督する「後見監督人」を定めることも可能です。
⑦ 遺産分割方法の指定・禁止
「相続人同士で話し合って決めてほしい」とすることもできますが、逆に
「遺産分割は5年間行ってはならない」
といった指定も可能です。
事業承継や不動産管理の都合上、すぐに分割してほしくない場合などに使われます。
⑧ 葬儀や供養に関する希望
法的拘束力はありませんが、
遺言書には葬儀の形や墓地に関する希望も記しておくとよいでしょう。
たとえば、
- 通夜・葬儀は家族葬で行ってほしい
- 戒名は〇〇院〇〇居士とする
- お墓は郡山市〇〇寺の先祖墓に入れてほしい
- 海への散骨を希望する
などです。
これらは法的効力を持ちませんが、遺族にとって重要な指針となります。
「付言事項(ふげんじこう)」として柔らかく書くのが一般的です。
⑨ 家族への感謝・メッセージ
遺言書の最後に、「これまでありがとう」「仲良く暮らしてほしい」などの一文を添えることで、
残された家族の心の支えになります。
法的効力はありませんが、「付言事項」として書いておくことで、
遺族の心情や相続協議の雰囲気に良い影響を与えることが多いです。
行政書士としても、この一文が相続トラブルを防ぐ大きな要素になると感じています。
書いてはいけない内容・注意点
遺言書は自由に書けるとはいえ、法律に反する内容や、実現不可能な内容は無効です。
たとえば次のような例は注意が必要です。
- 法定相続人の遺留分を完全に無視した遺贈
- 登記名義人でない土地の相続指定
- 「全財産を〇〇にやる」という曖昧な表現
また、感情的な表現や誤字脱字もトラブルの原因になります。
たとえば「長男〇一」と書くべきところを「次男〇二」と誤記した場合、
どちらが正しいか不明となり、無効となる恐れもあります。
遺言書作成の3つのポイント
遺言書作成のポイントは以下の3つです。
1. 財産目録を整理する
まずは自分の財産をすべてリスト化します。
不動産、預金、株式、保険、車、貴金属などを一覧にすることで、漏れなく指定できます。2. 書き方の形式を確認する
自筆証書遺言の場合は、全文・日付・署名・押印が必要です。
財産目録はパソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名・押印を忘れずに。3. 保管場所・証人を考える
自筆証書遺言は法務局での保管制度を活用すると安心です。
公正証書遺言の場合は、公証人と行政書士が内容確認から手続きまでサポートします。
行政書士ができるサポート
行政書士は、遺言書の文案作成や内容チェック、公正証書遺言の原案作成などを行います。
法律用語や相続関係を整理し、
「想いが確実に伝わる形」に整えることが可能です。
また、相続人や財産関係を調査し、相続後の手続きがスムーズになるように設計します。
まとめ、おわりに
要点をまとめます。
・遺言書には、財産の分け方・遺贈・相続分・後見人・付言事項などを書ける
・書き方を間違えると無効になるリスクがある
・自筆よりも専門家のチェックを受けた方が確実
家族への感謝や想いも「付言事項」として残すことで、心の相続になる
遺言書は「死後のための書類」ではなく、
「家族への最後のメッセージ」です。
あなたの意思を正しく形にするために、
専門家と一緒にじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所では遺言書の作成サポートを行っております。
作成に関してお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。