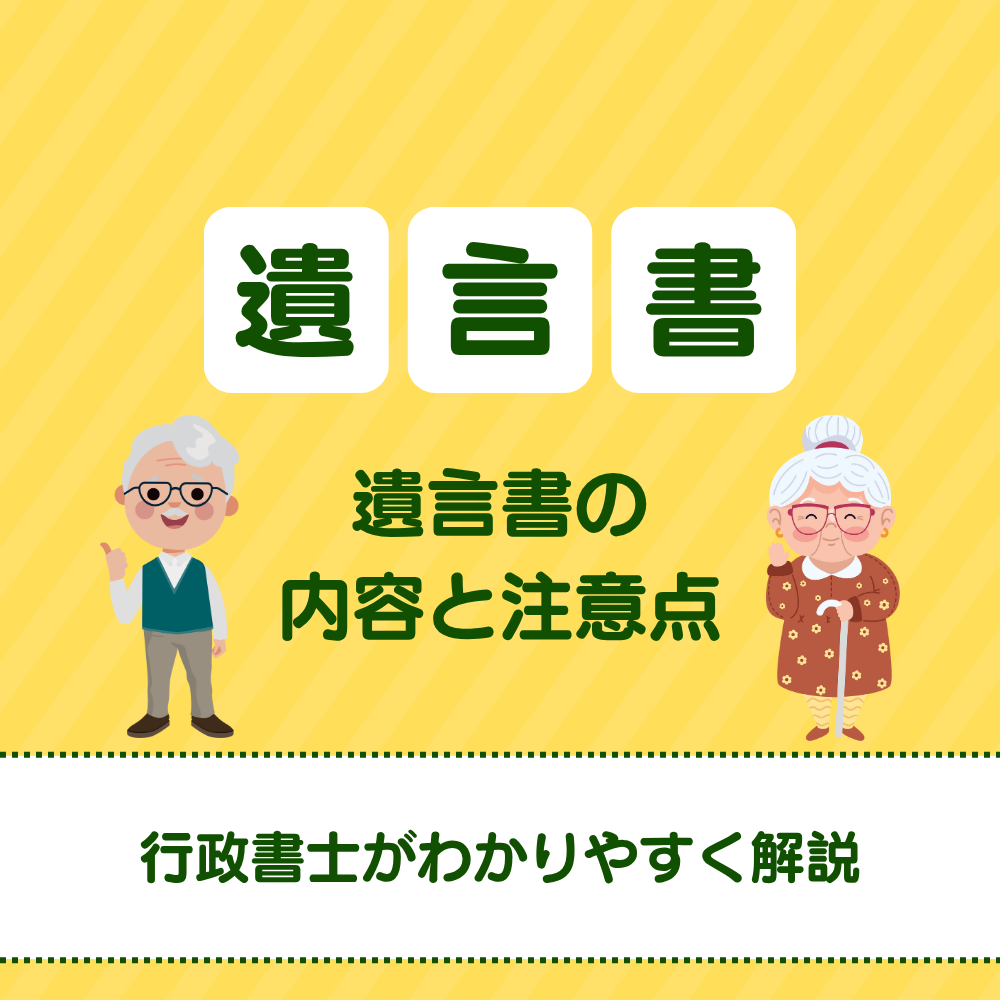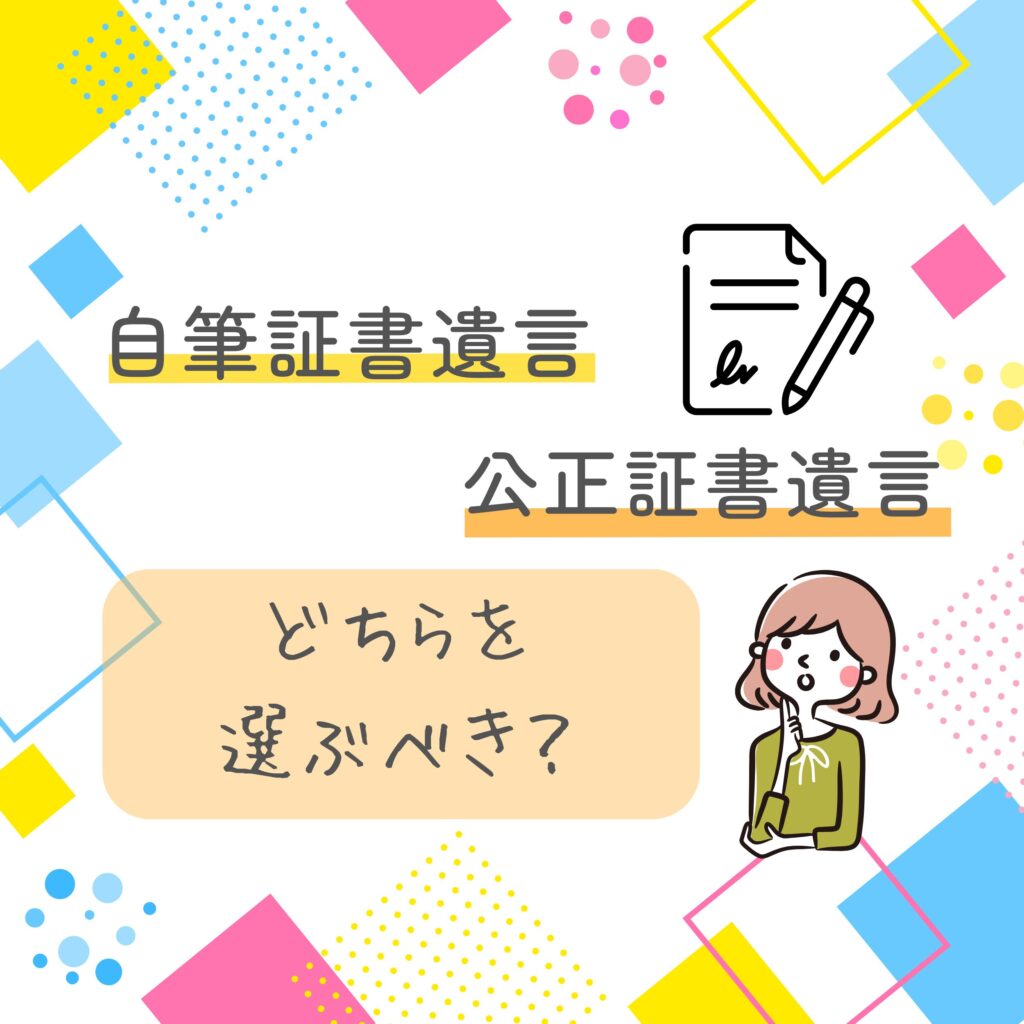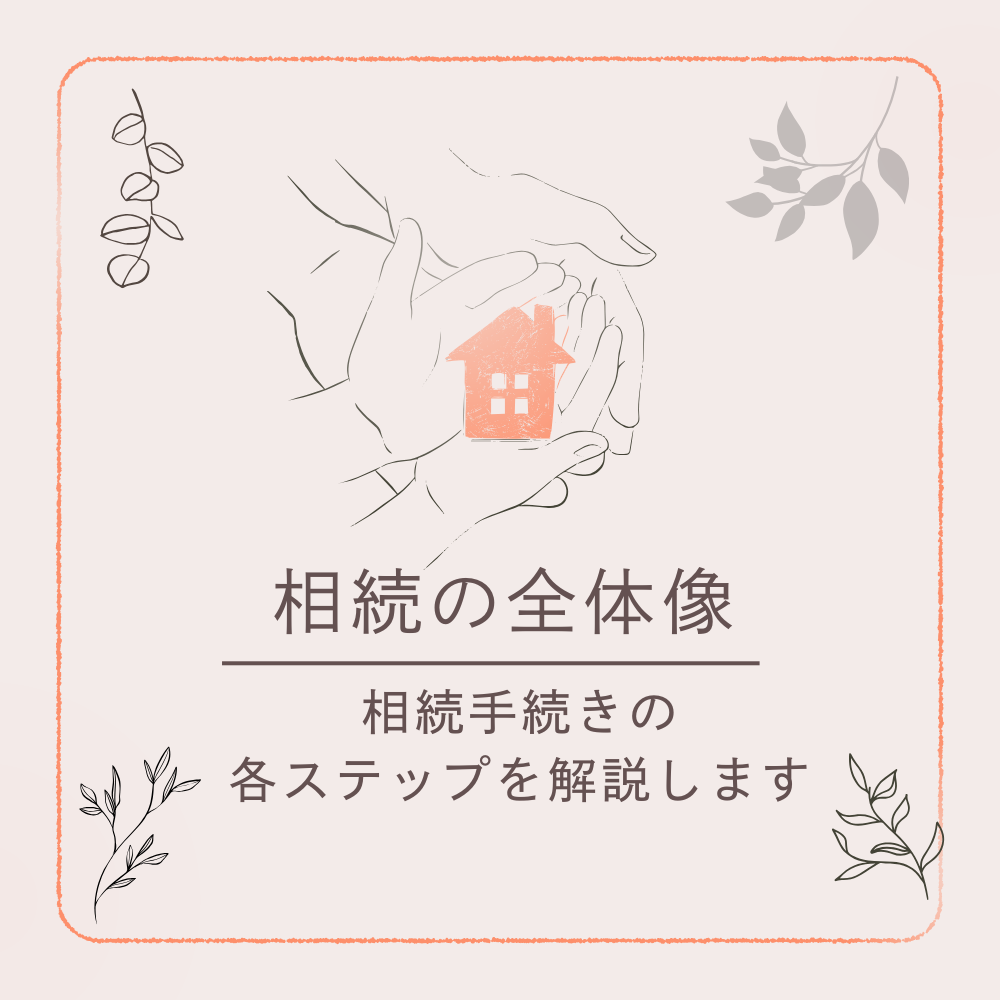行政書士が解説!エンディングノートの正しい書き方と相続トラブルを防ぐ活用法
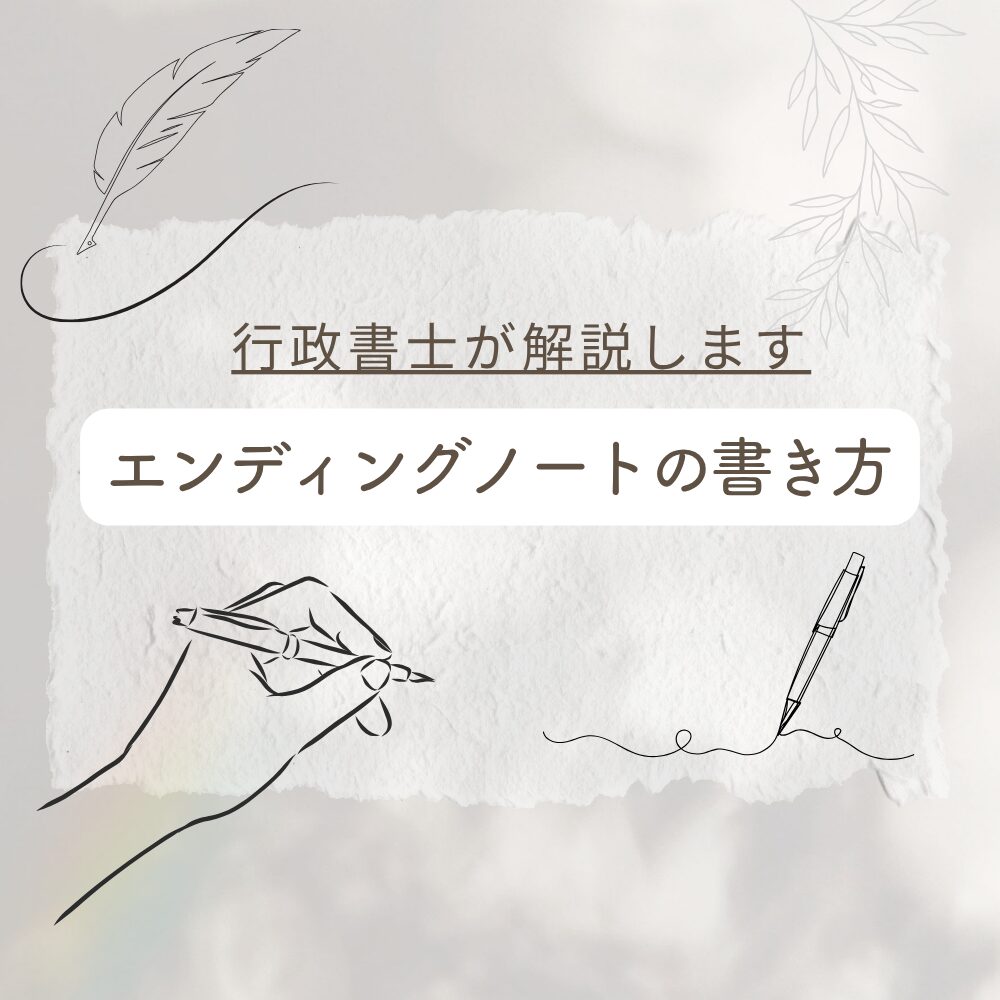
目次
はじめに
「もし自分に何かあったとき、家族に迷惑をかけたくない」
「自分の想いをきちんと残しておきたい」
――そんな気持ちから注目されているのが「エンディングノート」です。
近年、「終活」という言葉が浸透するなかで、
エンディングノートを作る人が増えています。
しかし実際には、
「どんな内容を書けばいいのか」「遺言書とはどう違うのか」が分からず、
書き始められない方も多いのが現実です。
エンディングノートは家族の絆を深め、
トラブルを防ぐ大切な橋渡しになることを期待されます。
本記事では、
行政書士の立場からエンディングノートの意味・書き方・注意点・遺言書との違いを分かりやすく解説します。
エンディングノートとは?
エンディングノートとは、
「自分の人生の終わり方」や「死後に伝えたいこと」を書き残すノートです。
法的な効力はありませんが、
家族や大切な人に自分の気持を伝えるための記録として大きな役割を果たします。
エンディングノートを書く目的
- 家族への感謝の言葉を残す
- 財産や葬儀の希望を整理する
- 医療・介護の希望を明確にしておく
- 相続・遺言の準備をスムーズにする
行政書士として特に強調したいのは、
「相続トラブルの予防になる」という点です。
多くの相続争いは「本人の意思が不明確」「遺言がない」ことが原因で起こります。
エンディングノートを通じて、自分の想いを記録しておくことが、
家族にとって最大の安心材料になるのです。
遺言書との違い
エンディングノートと遺言書は混同されがちですが、
目的と性質が大きく異なります。
| 項目 | エンディングノート | 遺言書 |
|---|---|---|
| 法的効力 | なし | あり(民法に基づく) |
| 形式 | 自由(ノート・手書き・デジタル) | 厳格な要件あり(自筆証書・公正証書など) |
| 内容 | 想い・希望・人生記録など | 財産の分け方・相続人指定など |
| 主な目的 | 家族へのメッセージ | 法的な相続の整理 |
行政書士としては、エンディングノートと遺言書を併用することを強くおすすめします。
たとえば、エンディングノートで
「なぜそのように財産を分けたのか」
「家族にどんな想いがあるのか」を補足すれば、
遺言書に書けない心のメッセージが伝わります。
遺言書は「法的整理」、
エンディングノートは「想いの共有」
——この2つを組み合わせることで、家族が納得しやすい終活になります。
エンディングノートに書くべき項目一覧
エンディングノートは、自由に書ける点が魅力です。
ただし、以下のような基本項目を押さえると、
より実用的で家族に伝わりやすいノートになります。
① 基本情報
- 氏名、生年月日、本籍、マイナンバー、血液型
- 緊急連絡先、かかりつけ医、保険証の保管場所など
→ 災害や急病時の連絡にも役立ちます。
② 家族・親族について
- 家族構成、親族の連絡先、疎遠になっている人の情報など
- 家族や友人への感謝のメッセージも記載すると良いでしょう。
→ 形式ばかりではなく感情を伝えるページとして使うことが大切です。
③ 財産に関する情報
- 銀行口座、保険、不動産、株式、借入金、年金など
- 行政書士のアドバイス:
通帳のコピーを貼るより、「銀行名・支店名・保管場所」を記す程度が安全。
残高や明細までは書かず、相続時の整理がしやすい形にするのがコツです。
④ 医療・介護の希望
- 延命治療を希望するかどうか
- 介護施設に入りたい・自宅で過ごしたいなどの希望
- 臓器提供・献体に関する意思表示
→ 家族が判断を迫られる場面で「本人の意思」があるだけで大きな安心になります。
⑤ 葬儀・お墓・宗教関係
- 葬儀の規模や形式、宗派、菩提寺、納骨方法
- 「誰を呼んでほしいか」「遺影写真の希望」など具体的に書くと家族が助かります。
⑥ デジタル遺品
- スマホやパソコンのパスワード、SNSやネット銀行の情報など
- 放置すると家族がアクセスできず、請求や契約の停止が困難に。
「パスワードそのもの」ではなく「保管場所」を書くことを推奨します。
セキュリティを保ちつつ、家族に引き継ぐことができます。
⑦ ペット・趣味・メッセージ欄
- ペットの世話を託す人の名前
- 趣味のコレクションや形見分けの希望
- 家族・友人・地域への感謝メッセージなど
→ 感情的な内容も自由に書いて構いません。
最後は「ありがとう」で締めくくると温かい印象になります。
書くときのポイント・注意点
1. 完璧を目指さない
「全部書かなければ」と考えると手が止まります。
まずは思いついた項目から書き始め、
あとで少しずつ追記していけば十分です。
2. 定期的に見直す
人生の節目(誕生日・結婚・退職など)に内容を更新しましょう。
行政書士としては、年に一度の「終活チェック」をおすすめします。
毎年内容の確認サポートを受ける方も増えています。
3. 家族と共有するタイミングを考える
書いたノートをすぐに渡す必要はありません。
「今はまだ話しづらい」という方は、
信頼できる人(行政書士・友人など)に預けても構いません。
家族に伝えるのは「準備が整ったとき」で大丈夫です。
4. 保管場所を明確にする
せっかく書いても、見つからなければ意味がありません。
金庫・机の引き出し・行政書士への預託など、
確実に家族がアクセスできる場所を選びましょう。
行政書士ができるエンディングノート支援
行政書士は、法的書類の専門家として、
エンディングノートの作成を多角的に支援できます。
行政書士が提供できるサポート例
- ノート内容の整理・構成アドバイス
項目の漏れがないようにチェックし、家族が理解しやすい形に整える。 - 遺言書・財産目録との連携
ノートの内容を法的効力のある遺言書に反映。 - 見守り契約・死後事務委任契約の提案
本人亡き後の手続きを行政書士が代行する仕組み。 - 相続・後見制度との連携支援
認知症や相続トラブルへの事前備えを法的にサポート。
行政書士に相談することで、
感情面と法的手続きの両面から支援が受けられます。
単なるノート作成ではなく、
「自分の人生を整理し、家族を守る仕組みづくり」まで踏み込める点が大きな魅力です。
まとめ
エンディングノートは、「死の準備」ではなく「生き方の記録」です。
書くことで、自分の人生を振り返り、
これからどう生きたいかを考えるきっかけにもなります。
行政書士としてお伝えしたいのは、
「エンディングノートを書くことが、相続トラブルを防ぐ最初の一歩」だということです。
想いを残し、家族の負担を減らすために、
まずは一行でも書き始めてみてください。
書くことは「未来の家族への手紙」です。
あなたの言葉が、残された家族の心を支えます。
なお遺言書についてはこちらの記事よりご確認ください。
📞 行政書士くろす綜合法務事務所では
当事務所ではエンディングノートの作成支援(1冊分プレゼント)を行っています。
また当事務所における対応可能な相続業務については下記よりご確認いただけます。
お気軽にご相談ください。