介護をしてくれた子に多く遺したい場合の遺言書の書き方|行政書士が解説する想いの伝え方と法的ポイント
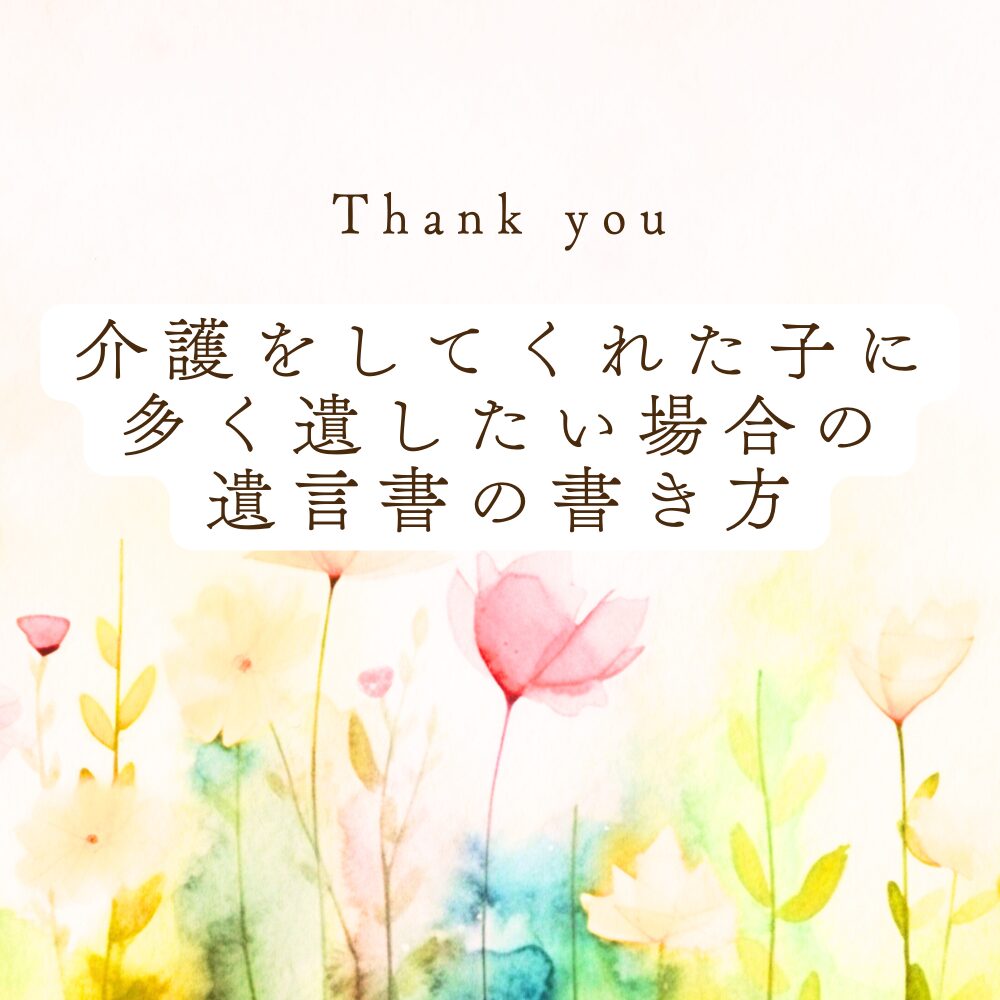
目次
はじめに:介護への感謝を形に残すには
高齢になり、生活の支えをしてくれる子どもへの感謝を「遺言書」で伝えたい
——そう考える方は年々増えています。
「他の兄弟は離れて暮らしているけれど、長男(長女)がずっと介護してくれた」
「お金で気持ちを伝えるのは難しいけれど、少しでも報いたい」
しかし、相続には法的なルール(遺留分・公平性・手続き)があり、
単純に「介護してくれた子に多く遺す」と書くだけでは、
トラブルになるケースも少なくありません。
この記事では、行政書士の立場から、
介護をしてくれた子に多く遺したい場合の遺言書の書き方と注意点を詳しく解説します。
介護の「感謝」を遺言で伝える意味
家族の介護は、時間・体力・精神力のすべてを使う大変な行為です。
にもかかわらず、
介護した子が必ず多く相続できるわけではありません。
なぜなら、日本の相続制度では「法定相続分」が決められており、
特別な事情がない限りは平等に分けるのが原則だからです。
しかし、現実には次のようなケースがよくあります。
- 長女が自宅で同居し、数年間介護を続けてきた
- 他の兄弟は遠方でほとんど関わっていない
- 親の財産は自宅と預貯金程度
このような場合、「長女に多く遺してあげたい」と思うのは自然な気持ちです。
遺言書を作ることで、
その感謝を明確に法的効力のある形で伝えることが可能になります。
介護した子に多く遺すための3つの方法
介護の貢献を考慮して財産を多く渡す方法は、大きく分けて次の3つです。
① 遺言書で具体的に遺産分割の割合を指定する
もっとも基本的な方法が、遺言書で相続分を指定することです。
たとえば以下のように書くことができます。
第○条 長女〇〇〇〇に対し、私の預金全額および自宅建物・敷地を相続させる。
第○条 長男〇〇〇〇には相続分を与えない。
ただし、これを行うときは注意が必要です。
他の相続人には「遺留分(法律で保証された最低限の取り分)」があるため、
それを侵害すると後で「遺留分侵害額請求」を受けるおそれがあります。
したがって、遺留分を考慮したうえで、
現実的なバランスを取ることが大切です。
※遺留分に関する詳しい記事は下記よりご覧いただくことができます。
② 「遺言の付言事項」で感謝の気持ちを添える
遺言の中で、法的効力を持たない部分として「付言事項(ふげんじこう)」があります。
これは、遺言者の想いや背景を自由に記すことができる部分です。
たとえば以下のように書くことで、他の兄弟の理解を得やすくする効果があります。
【付言事項】
私の介護を長年にわたり支えてくれた長女〇〇に深く感謝しています。
その恩に報いる気持ちから、他の兄弟よりも多くの財産を遺すことにしました。
他の家族にはこの思いを理解し、円満に相続を進めてほしいと思います。
付言事項は法的拘束力こそありませんが、
「なぜそうしたのか」を明確に残すことで、感情的なトラブルを防ぐ非常に効果的な手段です。
③ 生前贈与・介護報酬の形で渡す
遺言だけでなく、生前に感謝を形にするという選択肢もあります。
たとえば次のような方法です。
- 介護に対する報酬として、一定の金額を支払う契約を結ぶ
- 毎年少しずつ贈与する(年間110万円以内なら非課税枠内)
- 介護の協力者として「死後事務委任契約」や「任意後見契約」を締結する
これにより、生前から明確な感謝の意思表示を示すことができ、
トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
「寄与分」と「特別寄与料」を理解する
介護の貢献があった場合、
相続の場では寄与分(きよぶん)または特別寄与料(とくべつきよりょう)という
制度を利用できる可能性があります。
寄与分とは
相続人のうち、被相続人(親)の財産維持や増加に特別な貢献をした人がいる場合、
その人の取り分を増やす制度です。
たとえば、次のようなケースが対象です。
- 親の介護を長年続けた
- 親の事業を無報酬で手伝ってきた
- 親の生活費を援助していた
ただし、寄与分を認めてもらうには、他の相続人との話し合いや家庭裁判所の判断が必要です。
特別寄与料とは(2019年の民法改正で新設)
以前は、相続人でない長男の妻などが介護をしても、
報われないケースが多くありました。
これを救済するため、2019年の民法改正で「特別寄与料」の制度ができました。
つまり、相続人でない人でも、
介護などの貢献があれば相続財産から金銭を請求できるという仕組みです。
遺言書がなくても救済される場合はありますが、トラブルになりやすいため、
やはり遺言で明確にしておくことが望ましいです。
実際の遺言書の書き方例(簡易的な例)
ここでは、実際に「介護をしてくれた子に多く遺したい」場合の具体的な書き方例を紹介します。
◆公正証書遺言の例
第1条 私は、長女〇〇〇〇に対し、私の所有する福島県郡山市〇〇町〇丁目所在の宅地および建物をすべて相続させる。
第2条 私は、次女〇〇〇〇および長男〇〇〇〇に対し、預貯金のうち合計300万円をそれぞれ相続させる。
第3条 本遺言書に定めのない財産については、長女〇〇〇〇に相続させる。
【付言事項】
長年にわたり私の介護を担ってくれた長女〇〇〇〇に、心から感謝しています。
その献身的な支えに報いるため、本遺言のとおり長女に多くの財産を遺すことにしました。
他の家族もこの気持ちを理解し、円満に手続きを進めてくれることを願っています。
このように、「理由」と「感謝」を丁寧に書くことで、
他の相続人の納得を得やすくなります。
注意すべきポイント
1. 遺留分を侵害しないようにする
介護してくれた子に多く遺すことは自由ですが、
他の相続人の遺留分(法定相続分の1/2)を侵害すると、
後で請求される可能性があります。
そのため、遺産の総額と各相続人の法定相続分を試算し、バランスを取ることが大切です。
2. 自筆証書遺言よりも「公正証書遺言」がおすすめ
介護を理由に財産配分を変更する場合、
内容の有効性が問われることが多いです。
したがって、公証人と証人の立ち合いで作成する「公正証書遺言」が最も安全です。
3. 介護の実態を記録に残しておく
「介護していた」「感謝している」という主張を裏付けるため、
- 介護日誌
- 介護記録(介護保険サービス計画書など)
- 同居の状況
を残しておくと、後日の紛争防止に役立ちます。
行政書士に相談するメリット
遺言書は「書ければいい」ものではありません。
特に「介護をしてくれた子に多く遺したい」というケースでは、
家族の感情と法律のバランスを取る必要があります。
行政書士に相談することで、
- 公証人とのやり取りを代行してもらえる
- 家族構成や財産に応じた最適な分割案を提案してもらえる
- 相続後のトラブル防止に配慮した付言文を一緒に作成できる
といったメリットがあります。
地元の家族関係や不動産事情を踏まえた実務対応ができる行政書士に相談することが安心です。
まとめ:介護の「ありがとう」をトラブルなく伝えるために
介護してくれた子に多く遺したいという気持ちは、
親として自然で温かいものです。
しかし、その思いを遺言書という法的な形で残すには、
慎重な手続きが必要です。
- 遺言で具体的に分け方を指定する
- 感謝の言葉を付言事項として添える
- 遺留分に配慮する
- 公正証書遺言で確実に残す
これらを意識すれば、「ありがとう」の気持ちを、トラブルなく確実に伝えることができます。
おわりに:専門家とともに“想いのある遺言”を
遺言書は「財産の分け方」だけでなく、
「人生のメッセージ」です。
介護してくれた子に多く遺したいと考える方こそ、
法的な有効性と家族の納得を両立する設計が大切になります。
当事務所では郡山市で相続・遺言サポートを行っており、
「争いにならない優しい遺言」「家族に想いが伝わる遺言」
をテーマに、サポートをしております。
もし「どのように書けばよいか」「公証人との手続きが不安」という方は、
ぜひ一度ご相談ください。
あなたの想いを、次の世代へ正しく伝えるお手伝いをいたします。




