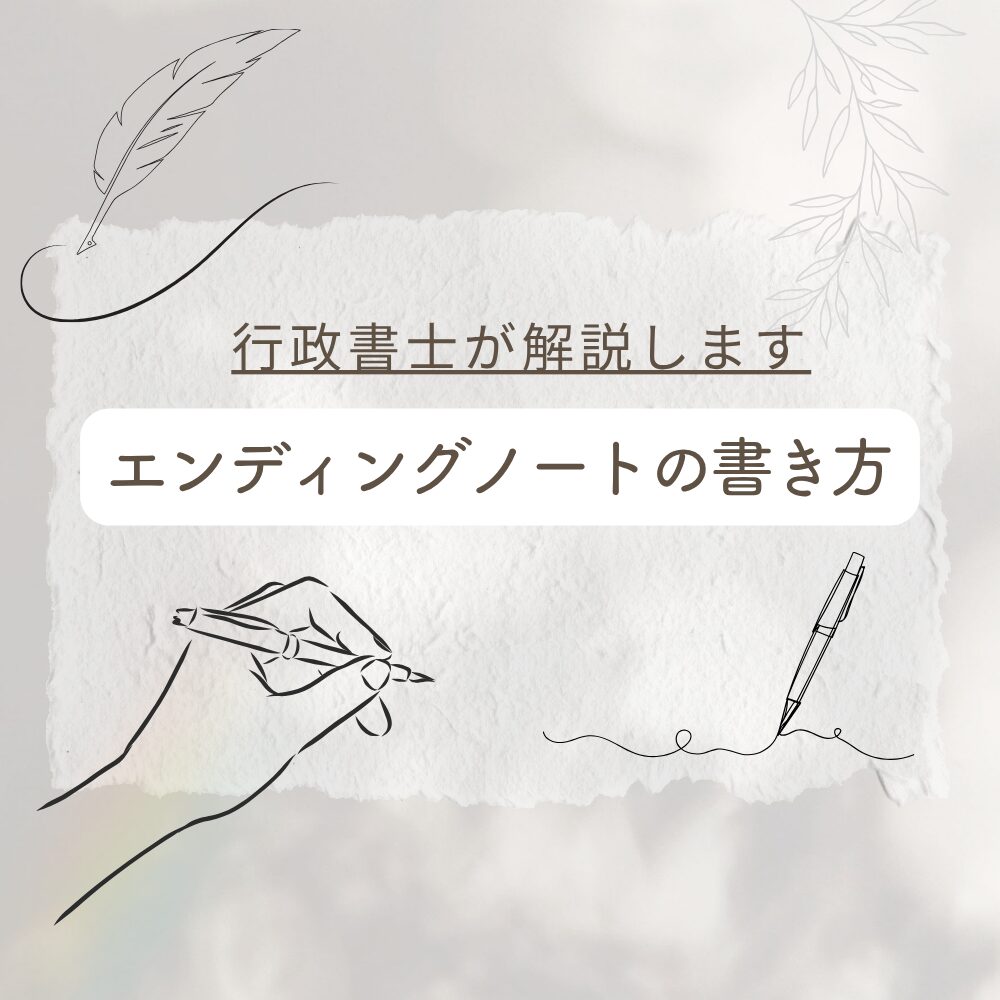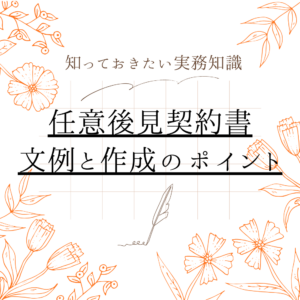法定後見との違いを徹底解説!任意後見のメリット・デメリット

目次
はじめに:自分らしい「老後の安心」を選ぶ時代に
近年、高齢化の進展とともに
「認知症による判断能力の低下」に備える制度として、
任意後見制度への関心が高まっています。
しかし、いざ調べてみると
「法定後見と何が違うの?」
「どちらを利用すべきかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
任意後見と法定後見の違いをわかりやすく整理し、
それぞれのメリット・デメリット、
利用の判断基準までを徹底解説します。
そもそも「後見制度」とは?
まず、「後見制度」とは、
判断能力が不十分になった人の生活や財産を法律的にサポートする仕組みです。
大きく分けて次の2種類があります。
| 区分 | 開始のタイミング | 申立てを行う人 | 主な内容 |
|---|---|---|---|
| 任意後見制度 | 本人が元気なうちに契約しておく | 本人 | 将来に備えて自分で後見人を選ぶ |
| 法定後見制度 | 判断能力が低下した後に申立てる | 家族など | 裁判所が後見人を選任する |
つまり、「任意後見=自分で決める制度」、
「法定後見=裁判所が決める制度」と覚えると理解しやすいでしょう。
任意後見制度の仕組みと流れ
① 契約の締結
任意後見は、本人が元気なうちに信頼できる人と
「任意後見契約」を結ぶことから始まります。
契約は公正証書で作成し、公証役場で手続きを行います。
② 後見開始の条件
契約をしただけではすぐに後見が始まるわけではありません。
実際に判断能力が低下し、
家庭裁判所へ申立てを行い、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任してから効力が発生します。
つまり、「将来に備えて準備しておく制度」という特徴があります。
③ 主な内容
契約内容には、財産管理・医療介護の契約代行・入院手続きなど、
具体的に委任できる範囲を明記します。
信頼できる家族や行政書士などを後見人に指定できる点が安心材料です。
法定後見制度の仕組みと種類
一方で、法定後見制度はすでに判断能力が不十分になった後に、
家庭裁判所へ申立てを行い開始されます。
申立てできるのは、配偶者・子ども・親族などです。
法定後見には判断能力の程度に応じて3段階があります。
| 区分 | 対象者 | 主な権限 | 裁判所が選任する人 |
|---|---|---|---|
| 成年後見 | 判断能力がほとんどない | 財産全般の管理・契約代行 | 成年後見人 |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 重要な契約の同意 | 保佐人 |
| 補助 | 判断能力がやや不十分 | 限定的な支援 | 補助人 |
裁判所が選任するため、公平性は高い反面、
「誰が後見人になるかわからない」
「本人の意思が反映されにくい」というデメリットもあります。
任意後見と法定後見の違いを比較
比較項目 任意後見制度 法定後見制度 開始時期 元気なうちに契約 判断能力が低下した後 後見人の選び方 本人が自由に選べる 裁判所が選任 契約方法 公正証書による契約 家庭裁判所への申立て 本人の意思の反映 高い 限定的 柔軟性 契約内容を自由に設計可能 法律上の範囲に限定 費用の目安 公証人費用・監督人報酬など 裁判費用・後見人報酬など 主な利用目的 将来の備え・安心確保 現在の支援・保護 つまり、「自分の意思を尊重して準備したいなら任意後見」、
「すでに判断能力が低下しているなら法定後見」と考えると整理しやすいでしょう。
任意後見制度のメリット
1. 信頼できる人を自分で選べる
法定後見では、裁判所が弁護士・司法書士など第三者を選任することも多いですが、
任意後見なら家族・行政書士・知人など信頼できる人を自分で指定できます。
2. 契約内容を自由に設計できる
財産管理だけでなく、介護施設への入所手続き、医療方針の希望など、
「生活支援」まで幅広く盛り込めるのが特徴です。
「自分らしい老後」を実現するための制度と言えます。
3. トラブル防止・家族の負担軽減
あらかじめ契約内容を明確にしておくことで、
将来的に家族間での「お金の使い方」や「介護方針」をめぐるトラブルを防止できます。
また、家庭裁判所の監督体制があるため、悪用リスクも低減されます。
任意後見制度のデメリット・注意点
1. 契約してもすぐには効力が発生しない
判断能力があるうちは任意後見契約は「準備段階」にとどまります。
実際に支援が必要になるまで時間がかかる点に注意が必要です。
2. 監督人が必ず選任されるため、費用がかかる
任意後見がスタートすると、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任します。
報酬は月1〜2万円ほどが一般的(財産額によって異なります)で、
長期間にわたるとコスト負担が大きくなる場合もあります。
3. 契約内容の設計ミスに注意
任意後見契約は、内容をどこまで委任するかが重要。
曖昧なまま作成すると、
後で「想定外の手続きができない」という不都合が起こることもあります。
行政書士など専門家のサポートを受けることが安心です。
まとめ
メリット
- 家庭裁判所の厳格な管理下で行われるため、不正防止効果が高い
- 「自分らしい老後」を実現するのに最適
- すでに判断能力が低下していても利用できる
デメリット
- 後見人を自分で選べない(第三者が選ばれることも多い)
- 手続きに時間と費用がかかる
- 本人の意思が十分に反映されにくい
法定後見と任意後見どちらを選ぶべき?判断のポイント
| 状況 | おすすめの制度 |
|---|---|
| 今は元気だが将来が心配 | 任意後見制度 |
| すでに認知症などで判断が難しい | 法定後見制度 |
| 家族が信頼できる人でサポート体制がある | 任意後見制度 |
| 家族間でトラブルが多い・距離がある | 法定後見制度(第三者選任) |
重要なのは、
「いつ」
「どんな支援を」
「誰に頼みたいか」を早めに考えることです。
特に一人暮らしの方や配偶者に先立たれた方は、
任意後見契約を検討することで安心が得られます。
行政書士ができるサポート
行政書士は、任意後見契約の作成や公証役場での手続き支援を行うことができます。
具体的には次のようなサポートが可能です。
- 任意後見契約書の原案作成
- 財産管理・医療・介護内容の設計アドバイス
- 公証人との調整・立会い
- 生活設計に合わせた「見守り契約」や「死後事務委任契約」の併用提案
任意後見は、遺言・エンディングノート・死後事務委任と組み合わせることで、
より強固な「終活設計」が可能になります。
おわりに:将来に備える「自分のための契約」を
法定後見は、判断能力が低下してからの「保護制度」。
任意後見は、判断能力があるうちに準備できる「安心の契約」です。
どちらが良い悪いではなく、
「今の自分の状況」と「将来どう生きたいか」で選択すべき制度です。
行政書士は、あなたの思いや家族関係を踏まえ、
最適な後見契約の形を一緒に設計します。
「将来に備えて安心したい」「老後の支援を信頼できる人に任せたい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
※関連記事