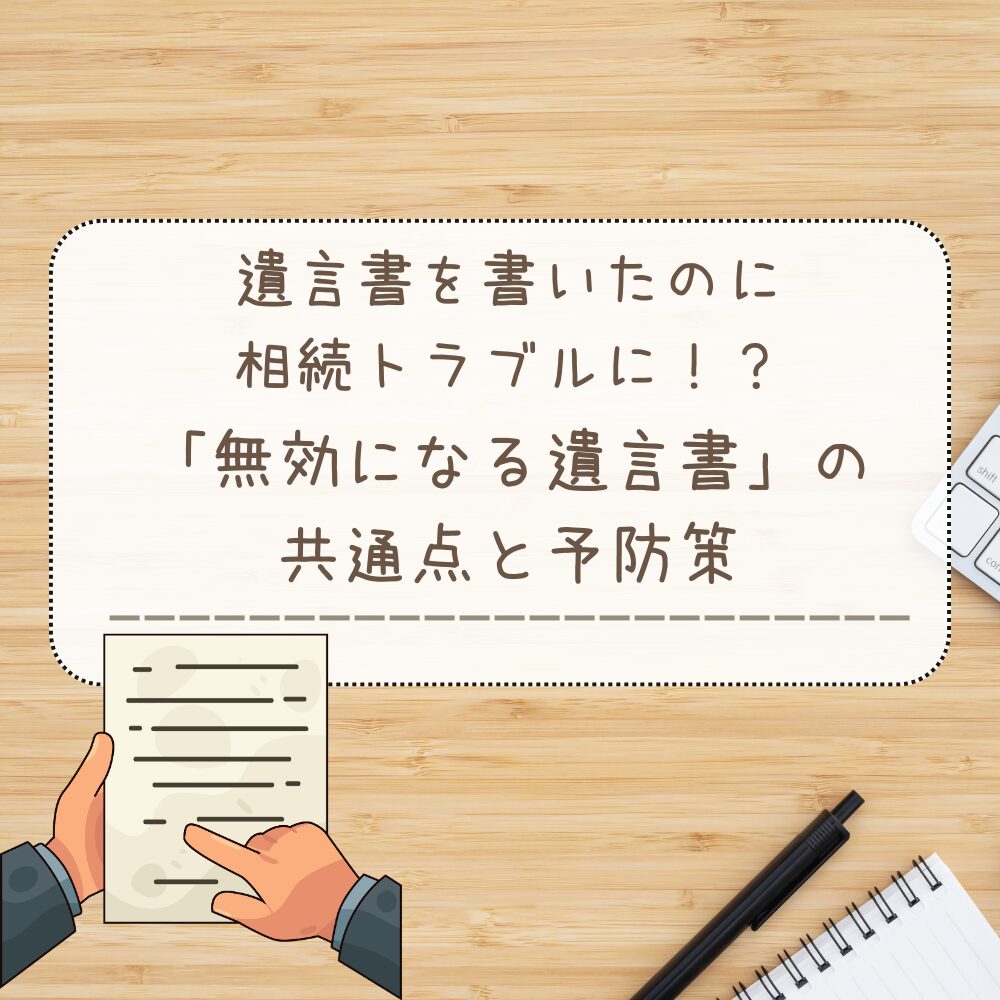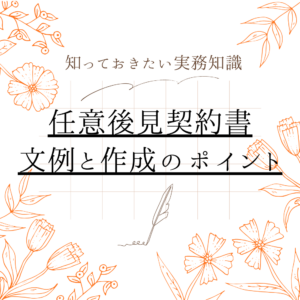遺言書を書いたのに揉めた!よくある失敗例と対策10選
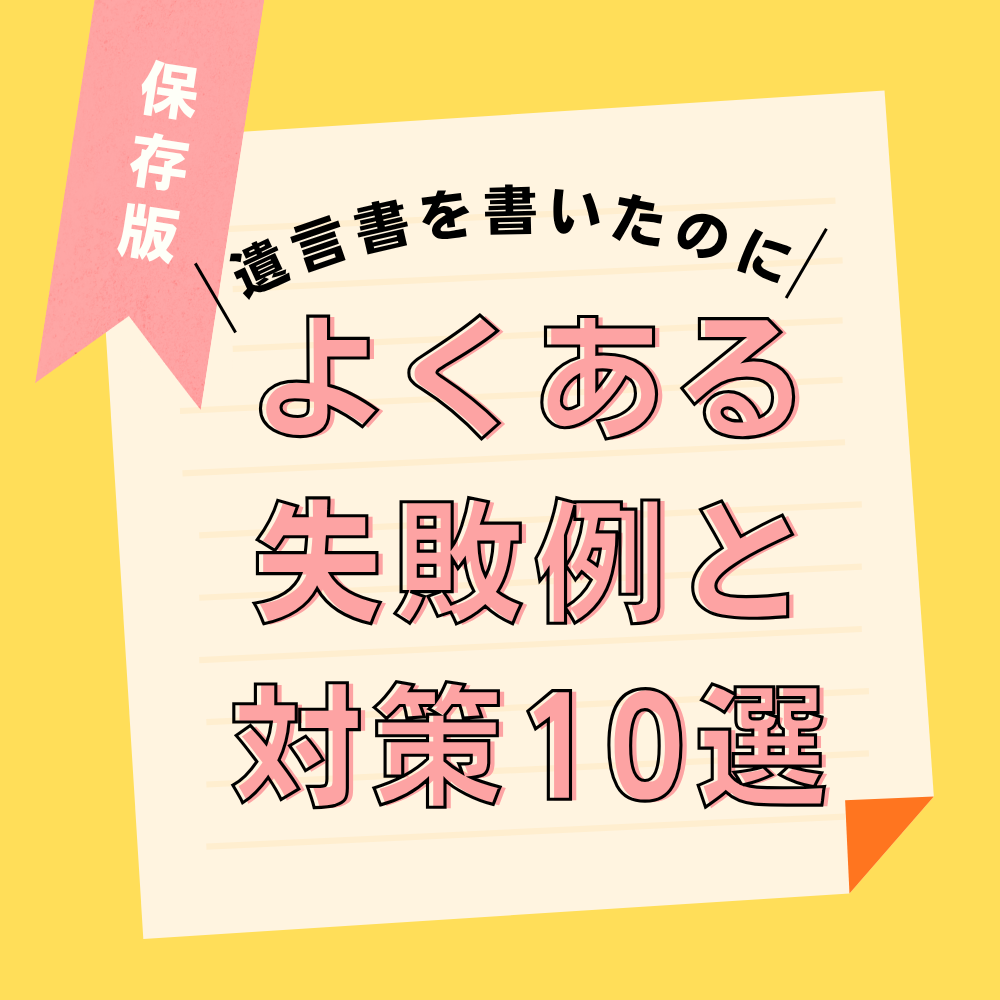
目次
はじめに:遺言書を書いたのに「揉める」ことは意外と多い
「遺言書を書けば、相続は安心」
――そう考える方は多いでしょう。
しかし、実際の現場ではこうした声が後を絶ちません。
「父が遺言書を残したのに、兄弟で争いになってしまった」
「母の気持ちを尊重したいけれど、書き方が曖昧で手続きが止まっている」
行政書士として数多くの相続・遺言案件を見ると、
遺言書があるのに揉めたケースがあります。
原因は「法的な不備」だけでなく、
「想いの伝え方」や「家族間の感情バランス」が影響しているのです。
この記事では、遺言書作成の失敗例と防止策を丁寧に解説します。
特に「介護をした子に多く残したい」
「不動産が複数ある」
「郡山市内に実家・農地を持っている」方にとって必見の内容です。
なぜ遺言書があっても揉めるのか?
1. 「形式的に正しい」だけでは不十分
遺言書は民法に定められた法的文書ですが、
その本質は「家族に想いを伝える手紙」に近いものです。
つまり、法律的に正しくても、感情的に納得できないと争いが起こるのです。
2. 相続トラブルの主な原因は誤解と説明不足
典型的なパターンは以下の3つです。
- 「なぜこの人だけが多いのか?」という説明不足
- 「書いてあるけど意味が曖昧」な文言ミス
- 「気持ちが伝わっていない」ことによる不信感
このように、家族間の感情のズレが争いを生みます。
法律的に正しくても、人間関係の温度差を埋めることが大切です。
3. 家族の構造変化と現代型トラブル
郡山市をはじめ、地方でも近年は「核家族+遠方の相続人」が増えています。
例えば、
- 長男が郡山で両親と同居
- 次男が東京で就職・結婚
という構成の場合、財産をどう分けても「公平感」の認識がズレるのです。
つまり、物理的な距離が心理的な距離に変わる。
これが現代の相続トラブルの根本原因です。
よくある遺言書の失敗例10選
失敗①:財産の特定があいまい
「自宅の土地を長男に相続させる」
という一文だけでは、登記上の地番が特定できず、
「どの土地?」「家屋はどうなる?」というトラブルが発生します。
対策:
登記事項証明書を確認し、
地番・家屋番号・地目・面積などを正確に記載する。
行政書士や司法書士が登記簿をチェックすると確実です。
失敗②:「相続させる」と「遺贈する」を混同
法律上、「相続させる」と「遺贈する」では意味が違います。
| 表現 | 対象者 | 効果発生時 | 登記方法 |
|---|---|---|---|
| 相続させる | 相続人 | 当然に取得 | 相続登記 |
| 遺贈する | 相続人以外(例:孫・友人) | 受諾が必要 | 贈与登記 |
対策:
法的文言を正しく使う。迷ったら専門家に文案をチェックしてもらう。
失敗③:付言事項(想いのメッセージ)がない
遺言の内容が法律的に正しくても、
「なぜこの分け方にしたのか」が書かれていないと、
感情的な納得が得られません。
対策:
付言事項で理由と感謝を伝える。
たとえば:
「長男には介護の負担をかけたため多くを相続させます。
他の兄弟も理解してほしいと思っています。」
失敗④:古い内容をそのまま放置
10年前の遺言書がそのまま残っており、
- 財産内容が変わっていた
- 相続人が亡くなっていた
- 家族関係が変化していた
というケースは非常に多いです。
対策:
少なくとも3年〜5年に1度は見直しを行う。
新しい遺言書を作れば、古いものは自動的に失効します。
失敗⑤:自筆証書で形式ミス
- 日付が抜けている
- 財産目録に押印がない
- 代筆してしまった
こうした形式不備は遺言書が無効になる原因です。
対策:
公正証書遺言を利用する。
費用はかかりますが、法的・心理的安心度が圧倒的に高いです。
失敗⑥:共有不動産を分割せずに指定
「兄弟2人で半分ずつ相続」と書いた結果、
売却・賃貸・管理すべてに両者の同意が必要となり、後々の対立要因になります。
対策:
原則、共有指定は避ける。
どうしても必要な場合は、「将来の分割方法」も記載しておく。
失敗⑦:代償分割を曖昧に記載
「長男が不動産を相続し、次男に金銭で補償する」とだけ書いてしまうと、
金額や支払い期限を巡って揉めます。
対策:
「次男に対して500万円を、相続開始後6か月以内に支払うものとする」
など、金額・時期を明確化する。
失敗⑧:相続人以外に遺贈したことで争いに
「介護をしてくれた親族以外の人」に遺贈すると、
他の相続人が「不当だ」と感じて訴訟になることもあります。
対策:
感謝の気持ちは付言事項で伝えつつ、
遺贈の金額や範囲を控えめに設定する。
失敗⑨:遺留分を侵害していた
遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続割合です。
これを侵害すると、遺留分侵害額請求(訴訟)を起こされる可能性があります。
対策:
相続税評価額をもとに配分を決める。
不動産・預金・保険のトータルバランスで調整を。
失敗⑩:遺言執行者を指定していない
誰が遺言を実行するのか決まっていないと、
登記・解約・名義変更の手続きが進まず、
遺産分割協議と同様の混乱が起きます。
対策:
信頼できる行政書士・司法書士を遺言執行者に指定する。
家族の負担を減らし、スムーズな相続を実現できます。
※その他遺言書に関する無効の例は下記より
その他トラブル事例集
事例①:農地を長男に相続 → 兄弟で対立
農家の父が「農地は長男に相続させる」と書いたが、
付言事項がなく、「なぜ次男には分けなかったのか」が不明。
結果、兄弟間で不信感が生まれ、遺留分請求に発展。
➡ 対策:
「農業を継いでくれる長男に託す。
次男には別途現金を相続させる。」
と書けば、争いは防げた。
事例②:実家の家屋だけ指定 → 土地が漏れて登記不可
「郡山市〇丁目〇番地の家を長女に相続させる」とだけ記載し、
土地部分が記載漏れ。登記ができず、手続きが1年遅延。
➡ 対策:
建物と土地をセットで指定する。
「上記建物の敷地である土地も併せて相続させる。」
事例③:付言事項に“差をつけた”言葉
「長男は親不孝だったので一切相続させない」
と書いた遺言書が発見され、長男が訴訟。家族関係が完全に破綻。
➡ 対策:
否定的な表現は絶対に避ける。
不平等を設けるときは感謝・理由・願いを添える。
トラブルを防ぐ「付言事項」活用術
付言事項は、争いを防ぐ「心のクッション」です。
以下のような書き方をすると、家族全員の納得を得やすくなります。
付言事項のおすすめ文例
① 感謝を伝える
私の財産は家族の支えで築いたものです。
今まで本当にありがとう。
② 分け方の理由を説明
長男には農業を継いでくれた感謝を込めて、農地を託します。
他の兄弟も理解してくれることを願っています。
③ 家族への願い
私がいなくなったあとも、兄弟仲良く支え合っていってください。
④ 介護をしてくれた子への感謝
最後まで看てくれた○○に、心からありがとう。
あなたのおかげで穏やかな時間を過ごせました。
遺言書を「正しく」作るための7つのステップ
1.財産をリスト化する(不動産・預金・保険など)
2.相続人を確定する(戸籍で確認)
3.分け方を検討する(バランス・意向)
4.付言事項で想いを添える
5.遺言執行者を指定する
6.公証役場で公正証書遺言を作成する
7.定期的に見直す
遺言書を確実に機能させるための「専門家チェックポイント」
| チェック項目 | 内容 |
|---|
| 財産の特定 | 登記事項証明書・通帳・保険証書をもとに作成 |
| 相続人確認 | 戸籍で正確に特定(再婚・認知など注意) |
| 文言の整合性 | 相続・遺贈・代償分割の区別を明確に |
| 付言事項 | 感謝・理由・希望を記載 |
| 執行者 | 専門家を指定して実務を円滑化 |
| 定期更新 | 3〜5年ごとに見直し |
郡山市などの地域で想定される遺言トラブルと地域的特徴
福島県郡山市は、
- 農地+自宅+預金を所有する高齢者が多い
- 相続人の一部が県外在住
- 二世帯同居・兄弟介護が多い
といった地域特性があります。
そのため、農地法・不動産登記・感情面の三重構造トラブルが発生しやすいと想定されます。
対策:
- 農地を相続する場合は、農地法3条の届出が必要。
- 郡山市の農業委員会との事前相談で「営農継続性」を説明。
- 家族会議で「誰が農地を維持するか」を明確化。
遺言書にこれらを明記しておくことで、許可・登記・実務がスムーズに進みます。
争わない遺言を作るために必要な3つの意識
- 財産の多寡よりも「思いやり」を重視する
- 公平=平等ではないことを理解する
- 家族に感謝を伝える勇気を持つ
「ありがとう」を一行書くだけで、家族は争わなくなります。
まとめ:遺言書は法律書ではなく家族への手紙
遺言書は、財産の分け方を決めるだけの文書ではありません。
それは、「これから家族が仲良く生きていくためのメッセージ」です。
行政書士として多くの現場を見てきた経験から言えることは、
遺言書で大切なのは「法」と「情」の両方を整えること。
法律的に正しく、想いが伝わる遺言書こそ、真の争わない遺言書です。